建設業にはどんな職種がある?仕事内容や適性について解説
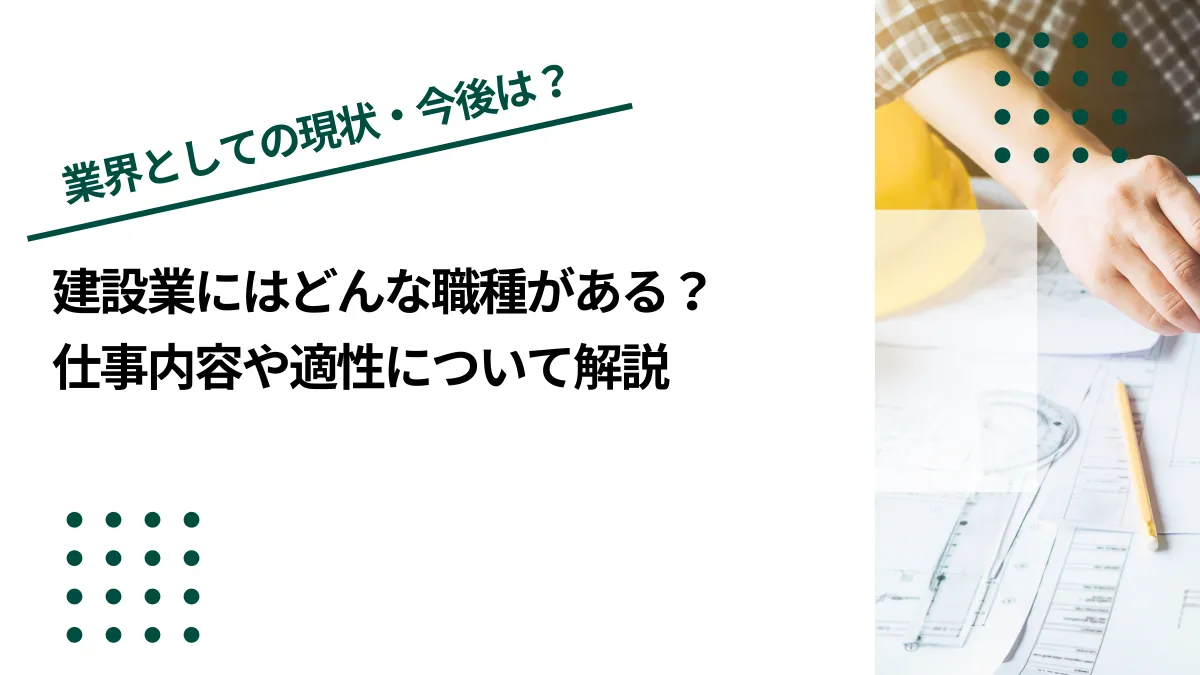
目次
- 建設業の主な職種
- 【施工管理職】職種の分類
- 土木施工管理
- 設備施工管理
- 建築施工管理
- プラント施工管理
- 【設計職】職種の分類
- 設備設計
- 意匠設計
- 構造設計
- CADオペレーター
- 【工事・技術職】職種の分類
- 職人
- 技術開発
- 【営業・事務・管理職】職種の分類
- 営業
- 事務管理
- 維持管理職
- 安全部門
- 【職種別】建設業の適性について
- 施工管理職に向いている人
- 設計職に向いている人
- 工事・技術職に向いている人
- 営業職に向いている人
- 職種とあわせて覚えておきたい建設業の今後
- 建設業界の現状・課題
- 建設業界の将来性
- 今後の建設業界に求められる人材の傾向
- 責任感が強い
- 発想力に優れている
- まとめ:建設業の職種は多岐にわたり、それぞれ適性がある
「手に職をつける」ことを実現するため、建設業界での就業を目指す方も多いでしょう。
しかし、実際に建設業で働くうえでは、どういった職種があるのか事前に把握しておくことが大切です。
この記事では、
- 建設業の主な職種
- 職種ごとの分類
- 建設業の適性について
- 建設業の今後
- 建設業界に求められる人材
について詳しく解説します。
建設業の主な職種
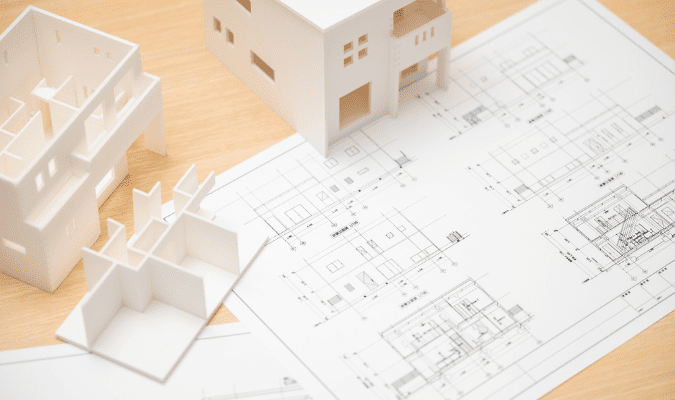
建設業の職種は、主に以下4つに分類されます。
- 施工管理職
- 設計職
- 工事・技術職
- 営業・事務・管理職
これらの職種はさらに細分化され、それぞれ業務内容が異なります。
建設業における各職種の分類とその業務内容を理解することが大切です。
【施工管理職】職種の分類
建設業における施工管理職とは、建設工事の予算管理・資材発注・スケジュール調整・人員の手配といった計画を行う職種のことです。
ここでは、施工管理職の分類である、土木施工管理・設備施工管理・建築施工管理・プラント施工管理について解説します。
土木施工管理
水道や電力、道路やトンネルといったインフラを対象とした施工を行う、土木工事における施工管理を担当します。
土木施工管理が取得すべき国家資格には「土木施工管理技士」があり、1級・2級の2つが存在します。
2級を取得すること主任技術者と名乗ることができ、1級は監理技術者を専任することが可能です。
設備施工管理
電気や配管、通信や造園といった設備に関連する施工・工程管理を行うのが設備施工管理の仕事です。
「電気工事施工管理技士」「管工事施工管理技士」「電気通信工事施工管理技士」といった資格を取得しておくと、実際に働くうえで優位となるでしょう。
建築施工管理
建築施工管理は戸建て住宅やマンション、ビルや商業施設といった建物の建築に関わる施工管理を行う仕事です。
主な業務内容は、以下のとおりです。
- 施工計画
- 工程管理
- 安全管理
- 品質管理
なお、建築施工管理の仕事をする際は「建築施工管理技士」の資格を取得すると優位になりやすいでしょう。
プラント施工管理
作業工程におけるリスクやスケジュール管理を担当するのがプラント施工管理者の役割です。
プラントの設計や製造、品質検査などを業務として実施します。
プラント施工管理の仕事に就くうえで必須の資格は特にありませんが、危機管理能力やマネジメントスキルなどを有しておくべきと考えられています。
【設計職】職種の分類
建設における設計職とは、着工前の設計や図面作成を行う仕事です。
設計職の分類である、設備設計・意匠設計・構造設計・CADオペレーターについて詳しく解説します。
設備設計
電気や水道、ガスや空調などの設備におけるレイアウトを担当する仕事です。
建築物におけるインフラの機能性だけではなく、室内環境やランニングコストにも配慮した設計が求められます。
意匠設計
建築物のデザインを考案するのが、意匠設計の仕事です。
依頼主の考えるコンセプトや要望を形にしつつ、工程・予算に応じた最適なプランを考える必要があります。
そのため、依頼主や社内の人間と積極的にコミュニケーションをとり、現実的なプランを考案することが求められるでしょう。
構造設計
建築物の安全性を考慮した設計を行うのが、構造設計です。
建築物や設備の重量はもちろん、自然災害の影響に配慮した骨格や土台の設計が求められます。
依頼者のニーズに応えつつ、建築基準法にクリアできる設計を目指すことが構造設計担当者の重要な役割です。
CADオペレーター
「CAD」と呼ばれるツールを活用し、図面の作成・修正を行うのがCADオペレーターです。
手書きの図面をベースにした作業を行う場合も多いため、図面を読む能力や建築用語の理解力が求められます。
CADのような複雑な作業は、今後台頭が予想されるAIに取って代わりにくい領域であるため、将来性が高い仕事と考えられるでしょう。
【工事・技術職】職種の分類
実際に現場で建築物を作り出すのに力を発揮するのが、工事・技術職です。
ここでは、職人と技術開発の仕事から、工事・技術職の役割を見ていきましょう。
職人
建設業界における「職人」とは、建設に関する特別なスキルを有している人材のことです。
例えば、高所での作業を専門に行う「とび職人」が該当します。
とび職人には、足場の組み立てや強度管理、作業効率化を考慮した段取りの力が求められるでしょう。
また建設業界における職人には「建具職人」も挙げられます。
建具職人とは、障子や扉、襖などの建具を制作・設置する仕事です。
開口部の寸法にマッチする建具を製作するために、繊細さが求められるでしょう。
技術開発
建築材料の開発など、住まいにおける快適性の向上に関わる技術開発を行う仕事です。
コンクリートなどの資材に使用する混合剤を変更し、コストダウンや耐久性アップを目指すといった仕事が例に挙げられます。
なお、新たな技術を開発するうえでは、既存の技術と比べた際のコストアップや、不具合の防止を前提としなければならないため、知識・経験が求められるでしょう。
【営業・事務・管理職】職種の分類
実際に建築の「作業」には携わらないものの、営業・事務・管理職も建築現場において重要な役割を担います。
いわゆる「縁の下の力持ち」である職種の分類について、解説していきます。
営業
建設業界における営業の役割は、自社が取り扱う建設工事を受注することです。
営業は、自社の建設工事について土地の所有者にアピールし、受注のうえで会社の売上を伸ばすことが求められます。
事務管理
建設プロジェクトの計画から竣工までの過程に必要なサポートを提供するのが、事務管理の役割です。
建設業界独自の法律や、規制に関連する特殊な業務を行うこともあるため、業界における専門知識の会得も求められるでしょう。
維持管理職
維持管理職は、現存する建造物やインフラを、健全かつ最適な状態で使用し続けるために重要な仕事です。
年数の経過で劣化する各種インフラは、定期的な点検・メンテナンスが必要不可欠です。
そのため、インフラが正常に作動し続けるための管理を行う維持管理職は、非常に需要のある仕事といえるでしょう。
安全部門
重機の取り扱いや高所作業が発生する現場において、事故のリスクを管理する仕事です。
建築現場での危険箇所の確認や、作業員に対して安全に関する教育を行うこともあります。
【職種別】建設業の適性について

さまざまな職種や役割のある建設業ですが、どういった人が「向いている」とされるのでしょうか。
ここでは、建設業の適性について職種別に紹介しているので、自身がどの職種に向いているのか客観的に把握するうえでの参考にしてください。
施工管理職に向いている人
施工管理職に向いている人の特徴は、以下のとおりです。
- コミュニケーション能力に自信がある
- リーダーシップがある
- マネジメント能力がある
- 自分の意見を臆せずいえる
- 計画を立てるのが得意
- スケジュール管理ができる
- 細かい作業が得意
- コツコツ真面目に取り組める
- 体力に自信がある
- メンタルが強い
- 臨機応変な対応ができる
- 危険察知能力がある
- 観察力がある
- 物事の全体像を掴むのが得意
- 0からものづくりをすることが好き
設計職に向いている人
以下の特徴に当てはまる人は、設計職に向いているといえるでしょう。
- こだわりや工夫を仕事に反映したい
- クオリティの高いアイディア創出に自信がある
- 図面を作れる
- 期間が定められていても最大限の仕事ができる
- さまざまな知識を必要とする仕事にポジティブに取り組める
- 考えることが好きな
- ひとりで黙々と仕事をしたい
- ものづくりの仕事が好きな
- 興味関心を持って根強く取り組める
- 不明点についてすぐ調べられる
- 自分自身の能力を成長させられるように努力できる
工事・技術職に向いている人
実際に現場で働く工事職や技術職に就くのであれば、以下の適性に自身が当てはまっているか確認しておきましょう。
- 体力がある
- 建築に興味がある
- 現場で活躍できる技術力を有している
- 注意力・集中力がある
- 論理的な思考力とマネジメント能力がある
- 課題解決能力がある
- 効率的に物事を進められる
- コミュニケーション能力に自信がある
- 好奇心が旺盛
- 新しい知識やスキルを身に付けることに抵抗がない
- 忍耐力がある
営業職に向いている人
建築業の営業職は、建築に関する知識に加え、以下の適性に当てはまっていることが大切です。
- コミュニケーション能力が高い
- 精神的にタフである
- リサーチ力がある
- 競争心が強い
- ノルマに対するプレッシャーを感じにくい
- 常に学習しスキルアップする意欲がある
- 相手の反応を見て行動できる
職種とあわせて覚えておきたい建設業の今後

建設業で働くことを目指す際は、職種の傾向だけでなく「業界」としての動きを把握しておくことも大切です。
ここでは、建設業界の現状や課題、将来性について解説します。
建設業界の現状・課題
建設業界は現状、以下のようなさまざまな課題を抱えています。
<人手不足>
少子高齢化の影響で、建設業就業者数は年々減少しています。特に、若年層の流出が深刻で、このままでは技術継承も難しくなることが懸念されています。
建設業界の若者離れに関しては「建設業の若者離れは当たり前」と言われる理由と今後の対策案で詳しく解説してますので、コチラもご覧ください。
<労働環境の改善>
建設現場は長時間労働や重労働のイメージが強く、若者にとって魅力的な職場とはいえません。近年は改善が進められているものの、依然として課題が残されています。
<生産性の低さ>
建設業界は、他の産業に比べて生産性が低いといわれています。これは、現場作業の多くが手作業に頼っていることなどが原因です。
<コスト上昇>
資材価格の高騰や人件費の上昇により、建設コストも比例して上昇しています。
<デジタル化の遅れ>
建設業界は、他の産業に比べてデジタル化の遅れが目立ちます。これは、IT人材不足や、現場でのIT導入の難しさなどが原因です。
特に問題視されているのが、人手不足やそれに伴う高齢化ではないでしょうか。
国土交通省が発表したデータによると、建設業就業者の現状は以下のとおりです。
- 建設業就業者:685万人(H9)→ 504万人(H22)→479万人(R4)
- 技術者:41万人(H9)→31万人(H22)→37万人(R4)
- 技能者:455万人(H9)→331万人(H22)→302万人(R4)
また、55歳以上が35.9%、29歳以下が11.7%と高齢化が進行しており、次世代への技術承継が大きな課題となっています。
こういった課題を解決するため、労働水準や待遇の改善、IT化による業務効率化などを対策として考案することが重要になると考えられるでしょう。
建設業界の将来性
課題が多いとされる建設業界ですが、業界としての将来性に関してはポジティブな意見も多くあります。
- 需要が途切れるリスクが少なく、安定している
- 建設技術者の需要が高い
- 建設投資の需要が増加傾向にある
- 技能者の処遇改善の可能性が高い(建設キャリアアップシステムなどの取り組みによるもの)
- 給与アップが期待しやすい(資格を取得することで)
- 住宅やインフラの需要が高まる見込みがある(世界的な人口増加や都市化の進展に伴うもの)
加えて、今後の課題とされる人材不足をIT技術の推進により解決できれば、業界としてのさらなる発展も期待できるのではないでしょうか。
今後の建設業界に求められる人材の傾向

今後の建設業界においては、現状の課題と将来性にも関連し、以下の特徴に当てはまる人材が求められると考えられます。
- 責任感が強い
- 発想力に優れている
責任感が強い
建設の仕事の多くは、多種多様な職種の人材が結束して行うものです。
大勢の人間が関わる仕事においては、自身に与えられた役割をしっかり遂行する、強い責任感が求められます。
特に、人手不足や生産性の低さが課題とされている建設業において、いかに自身の役割を理解し、最適化を図る意識を持つ事が重要と考えられるでしょう。
発想力に優れている
今後の建設業界では、AIでは実現できないアイデア・発想力を持つことが重要になるかもしれません。
建設業界においても、今後はIT技術が浸透していくと考えられています。
ただし、建築関係のデザインについては、機械ではなく人間の知恵や発想が重視される場面も多いでしょう。
業界としての課題であるデジタル化の遅れを解消しつつ、デジタルでは実現しにくいアイデアを考える力を養うことが、今後の建築業界において重要な能力といえるのではないでしょうか。
まとめ:建設業の職種は多岐にわたり、それぞれ適性がある
今回は、建設業の職種とそれぞれに関連する内容について、以下のとおり解説しました。
- 建設業の職種には「施工管理職」「設計職」「工事・技術職」「営業・事務・管理職」
- 職種ごとに役割があり、適性も異なる
- 建設業には人手不足などの課題があり、解決に向けた対策・工夫が必要
- 今後の建設業界には責任感の強さや発想力が求められる
建設業の仕事は多岐にわたり、それぞれが建設物を作り出すうえで重要な役割を担っています。
今後建設業での就業を目指すうえでは、職種ごとの役割に加え、適性や業界としての現状・課題、今後求められる人材の傾向をしっかり理解しておくことが大切です。
