建設業でかかる人工代の請求書の書き方|相場や計算方法について
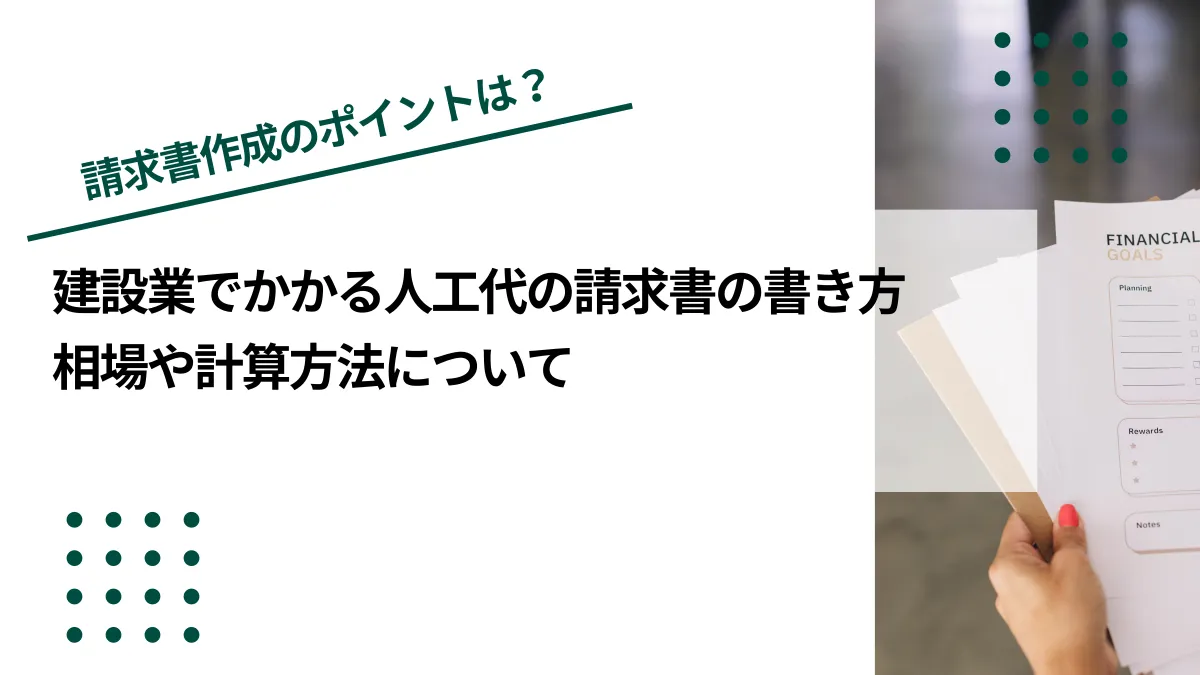
目次
一般的な業界とは異なり、建設業の請求書には「人工代」という項目があります。
しかし、人工代という言葉に聞き馴染みがない、人工代をどう計算すべきかわからないという方も多いでしょう。
この記事では、
- 建設業における「人工代」の相場や計算方法
- 人工代の取り扱いや税金との関連性
- 人工代の請求書の書き方
- 人工代を含んだ請求書作成に関するポイント
について詳しく解説します。
建設業における人工代とは「作業員1人あたりの1日の人件費を示す用語」のこと
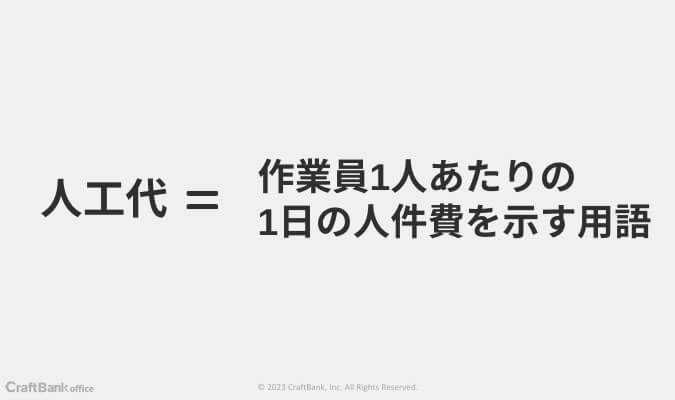
建設業における「人工代」とは、作業員1人あたりの1日の人件費を示す用語です。
請負業者から発注者に対して請求される費用で、請求書には、人工代の内訳として日給・残業代・休日出勤手当・その他手当などの記載が必要です。
ここからは、建設業における人工代について以下の視点から解説します。
- 人工代の相場
- 人工代の計算方法
- 人工代の取り扱い
- 人工代と税金の関連性
1つずつ見ていきましょう。
人工代の相場
人工代と完全に一致するわけではありませんが、ある程度関連している「公共工事設計労務単価」を紹介します。
国土交通省が発表した「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」のデータによると、建設業の公共工事設計労務単価は職種ごとで以下のようになっています。
職種 | 全国平均値 | 令和5年度比 |
|---|---|---|
特殊作業員 | 25,598円 | +6.2% |
普通作業員 | 21,818円 | +5.5% |
軽作業員 | 16,929円 | +6.3% |
とび工 | 28,461円 | +6.2% |
鉄筋工 | 28,352円 | +6.6% |
運転手(特殊) | 26,856円 | +6.3% |
運転手(一般) | 23,454円 | +7.2% |
型わく工 | 28,891円 | +6.6% |
大工 | 27,721円 | +4.9% |
左官 | 27,414円 | +5.0% |
交通誘導警備員A | 16,961円 | +6.4% |
交通誘導警備員B | 14,909円 | +7.7% |
上述した主要職種での公共工事設計労務単価の相場は22,100円で前年比の+6.2%と増加しています。
なお、建設業の全職種における公共工事設計労務単価の相場は23,600円と、前年のデータと比べて+5.9%となっているため、業界全体で人工代の相場が高くなっているといえるでしょう。
人工代の取り扱い
人工代は、建設業における重要なコストの一つであり、外注費として取り扱うのが一般的です。
ただし、外注費とみなされるには、職人自身が事業者でないといけません。
また、人工代は、給与として取り扱われる場合もあります。
請負契約である場合は外注費、雇用契約における役務提供の場合は給与とされるのが一般的なようです。
人工代と税金の関連性
人工代と税金の関連性は、人工代の取り扱いによって大きく異なります。
例えば人工代を外注費として取り扱う場合、支払い側は外注費として経費に計上できます。
この場合、支払いを受ける側には「事業所得」として課税されるため、消費税を納税しなければなりません。
人工代を支払う側が給与として経費に計上する場合は、支払いを受ける側は「給与所得」として課税されます。
そのため、支払い側は源泉徴収を徴収し、納税しなければなりません。併せて、支払いを受ける側は、社会保険に加入する必要があります。
建設業者が覚えておくべき請求書への人工代の書き方

人工代について請求書へ記載する際は、まず請求書に「人工代」の項目を設置する必要があります。
なお、請求書に人工代を記載する際は、以下のような点に注意する必要があります。
- 人工代は1日あたりの金額であるため、実働時間にかかわらず同様の金額となる(例:実働時間が3時間でも8時間前提で設定された金額と同じになる)
- 工事内容に、人工代(何人 × 何日間)と記載する
- 数量は「人数×日数」の数字を記載し、単位を「人工」にする
- 複数の現場で作業をした場合は、備考欄にどの現場の金額かを明示しておく
人工代を記載した請求書の項目については、後述する「請求書の基本的な作り方」を参考にしてください。
人工代の請求書を作成に関するポイント

建設業の方が人工代の請求書を作成する際は、さまざまなポイントを把握しておくことが大切です。
例えば、人工代を含めた請求書の項目やそれぞれの記載方法、フォーマットや送付方法などが挙げられます。
ここでは、人工代の請求書を作成に関するポイントをまとめているので、実際に請求書を作成・提出するうえでの参考にしてください。
請求書の基本的な作り方
建設業の請求書は人工代を含め、以下に挙げる項目の記載が必要です。
1.宛先 | ・発注者の氏名 |
|---|---|
2.請求内容 | ・提供した施工に関する「品目」(修理作業の名称や内容など実際の作業を明確に記載) |
3.消費税 | ・消費税の金額を記載する |
4.請求書の発行日 | ・一般的には発注者の指定する締日を記載する |
5.報酬の支払い期日 | ・施工側・依頼側双方で取り決めた支払い期日を記載する |
6.発行者 | ・請求書を発行する者の氏名を記載する |
7.請求書の番号 | ・請求書の右上に請求書番号を記載する |
8.振込先 | ・振込先に関する情報を記載する |
9.特記すべき事項 | ・請求と支払いにおける特別な条件などがある場合に必要な項目 |
10.適格請求書(インボイス)に関する項目 | ・インボイス制度に対応する請求書の項目を記載する |
さらに具体的な請求書の作り方は「建設業での請求書の書き方は?インボイスで記載すべき項目や注意点を解説!」をご覧ください。
請求書のフォーマットに決まったものはない
建設業の請求書について、決まったフォーマット自体はありません。
「請求書の基本的な作り方」で説明した基本的な項目をしっかり含めていれば、フォーマットは自由に選択できます。
送付方法は「郵送」or「メール」
建設業の請求書を送付する際は、郵送・メールのいずれかの方法を選択しましょう。
請求書を郵送する際は、送付状を併せて同封しておきましょう。
送付状には宛先や書類内容を記載しておくことで、送付プロセスにおけるミスを防止できます。
また、信用度向上にも寄与するので、ビジネスマナーの一環として送付状を同封すべきといえるでしょう。
一方、メールで請求書を送る場合は、送付状の内容をメール本文に記述しましょう。
送付状を別途用意する必要はありません。
なお、メールで請求書を送る際は、改ざん防止のためPDF形式で送るべきです。
まとめ:建設業の請求書には人件費である「人工代」の記載が必要
今回は、建設業の請求書に記載すべき「人工代」について、以下の視点で解説しました。
- 建設業における「人工代」とは作業員1人あたりの1日の人件費のこと
- 人工代の相場は増加傾向にある
- 人工代は外注費として扱うのが一般的
- 人工代は給与として計上することもある
- 請求書を作成する際は「人工代」の項目を設置のうえ、請求書における基本項目についても記載する
- 建設業の請求書には決まったフォーマットはない
- 郵送で送付する際は送付状を同封するのがおすすめ
- メールで請求書を送る場合は送付状に記載するような内容をメール本文に記載すべき
建設業の請求書には、いわゆる人件費を示す「人工代」を記載する必要があります。
一般的な請求書の項目に「人工代」をプラスし、そのうえで正確な内容を記載することで依頼側とのトラブルを防止できるでしょう。
また、請求書を正確かつスピーディーに作りたいなら、弊社の提供する「クラフトバンクオフィス」もおすすめです。
クラフトバンクオフィスの請求機能は、見積からの自動作成や入金管理、出来高ベースで作成したものの一元管理など、効率化と正確性アップが期待できます。
クラフトバンクオフィスの詳細は、サービス資料をダウンロードしてご覧ください。
