建設業での請求書の書き方は?インボイスで記載すべき項目や注意点を解説!
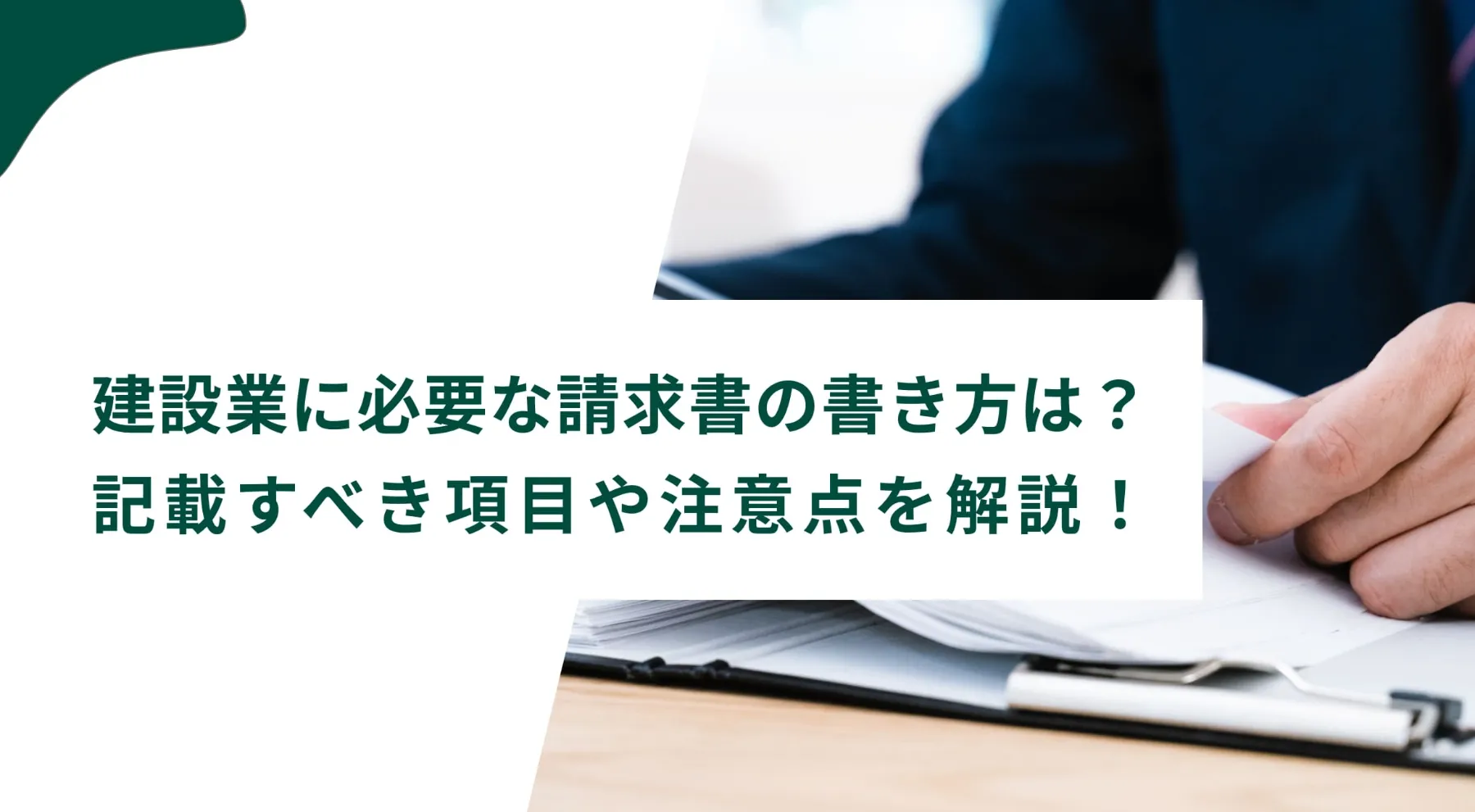
目次
建設業において、取引先との金銭のやり取りをする際に発行する請求書。
適正な内容で発行しなければ、後々トラブルにつながる可能性があります。
今回は、建設業における請求書について、
- 請求書とは何か
- 請求書の書き方
- 請求書を作る際の注意点
- 請求書に関するインボイス制度について
上記の内容を中心に詳しく紹介します。正確で適切な請求書作成を目指す方の参考になれば幸いです。
また、請求書を正確かつスピーディーに作りたいなら、弊社の提供する「クラフトバンクオフィス」がおすすめです。
エクセルの請求書はファイルの管理が大変で、事務の方以外はすぐに履歴を見返せなかったり、入金管理のために別のファイルを用意したりと、管理の負担がかかります。
クラフトバンクオフィスの請求機能は、見積からの自動作成や入金管理、出来高ベースで作成したものの一元管理など、効率化と正確性アップが期待できます。
クラフトバンクオフィスの詳細は、サービス資料をダウンロードしてご覧ください。
建設業の請求書作成に関係するインボイス制度について
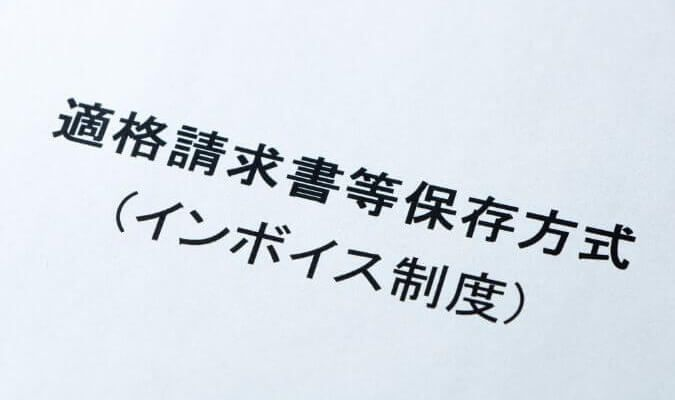
インボイス制度とは、「2023年10月より開始された事業者の納税額を正確に管理するための申告制度」です。
制度開始後は、下請会社(売り手側)が「インボイス(適格請求書)」を発行しない場合、元請会社(買い手側)は仕入税額控除を受けられません。
仕入税額控除を受けられないと、元請会社の消費税納税額が高くなる恐れがあります。
インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみです。
元請会社にインボイスを発行するには、下請会社は適格請求書発行事業者に登録する必要があります。
なお、適格請求書発行事業者への登録は任意です。
自社の状況や取引先を考慮した上で、登録を検討することがポイントといえます。
インボイス制度に対応した請求書では
- 登録番号
- 軽減税率の対象である旨の表記
- 税率ごとに区分して合計した税抜または税込対価の額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
上記4つの項目が必要です。
詳しい記入例に関しては、後述する「インボイス制度に対応した請求書の書き方」にて解説するので、ぜひチェックしてみてください。
建設業における請求書の書き方

ここからは、建設業における請求書の書き方を解説します。
なお、請求書に明確なフォーマットはなく、必要となる項目が記載されていれば問題ありません。イチから自作しても良いですが、テンプレートに沿ったほうが効率よく請求書を作成できます。
記入漏れも防げるので、素早く正確に請求書を作りたい方にはテンプレートの利用がおすすめです。
それでは、基本項目とインボイス対応の項目に分けて、それぞれ記入例を紹介します。
基本項目の記入例
請求書に記載する基本項目は、以下のとおりです。
- 題目
- 請求先
- 請求番号
- 請求日
- 発行者
- 合計金額
- 振込の期限
- 取引内容
- 小計・消費税・合計
- 振込先
- 備考
1つずつ見ていきましょう。
題目
書類名に関する項目なので「請求書」と記載します。
書類を受け取った側が、何の書類なのかをひと目で判断できるように、用紙の一番上に大きめの文字で書きましょう。
請求先
請求先の会社名や屋号、氏名などを明記します。
会社や屋号ならば「御中」を、個人名ならば「様」を最後に付けます。
請求先が法人の場合、部署名まで記載するケースが多いです。
略称や誤字は失礼にあたるので、提出前には正しく記入できているかを見直すようにしてください。
また、「御中」や「様」などの敬称は併用しないので入力する際には気を付けましょう。
請求番号
請求番号とは、請求書を管理するために発注者が割り振る番号です。
請求番号がない場合、請求先から問い合わせがあった際に、その都度請求書の中身を確認しなければいけません。
必要な書類をすぐに見返すために、請求番号を書いておくと便利です。
たとえば、請求番号の付け方には主に以下のような方法があります。
- 桁数を決めておき、発行順に採番(0001、0002、0003…)
- 企業先コード+発行順に採番(XXX-001、XXX-002、XXX-003…)
- 取引日付を使う(2023年1月に発行した場合は「202301」など)
有事の際などで過去の請求書を再発行する必要が出たときに、請求番号から請求書をすぐに見つけ出せる管理体制となっているのが理想です。
請求日
請求書の発行日を記します。
なお、締め日の扱いは企業によってルールが異なるので、事前に取引先に確認しておきましょう。
発行者
請求書の発行者について会社名や屋号、氏名を記入します。
住所や連絡先もあわせて書く場合が多いです。
押印は法的に必須ではありませんが、
- 書類の信頼性を高める
- 偽造・改ざんを防止できる
などの役割があり、取引先によっては求められるケースがあります。
合計金額
請求する合計金額を税込価格で提示します。
特に重要な項目なので、わかりやすいように大きく記載しましょう。
振込の期限
請求金額を取引先に支払ってもらう期日を明記します。
振込の期限を設けることで、未払いや支払遅延を防げます。
ただし、発注者が振込期限を勝手に決めると、トラブルに発展する恐れがあるので注意してください。
契約を交わすタイミングで、振込の期限を確認しておく必要があります。
取引内容
取引内容は
- 品目……作業内容・サービス内容・材料を記述する
- 数量……提供したサービスの数量や、材料を使用した量を記述する
- 単価……労働・材料の単価(キログラム、日、時間、平方メートルなど)を記述する
- 金額……「数量×単価」の金額を記述する
上記4つの項目で構成されます。
取引内容の記入例は、以下のとおりです。
【記入例】
品目 | 数量 | 単価 | 金額 |
鉄骨組立一式 | 1 | 300,000 | 300,000 |
内装仕上げ工事一式 | 1 | 50,0000 | 500,000 |
洗面台 〇〇製 型番✕✕ | 2 | 40,000 | 80,000 |
複雑な建設工事の場合、1つ1つの材料を記載していると、請求書の作成に手間がかかるケースがあります。
そのようなときは「一式」という表記を使用し、内容をまとめることが可能です。
ただし、すべてを一式表記にすると具体的な内容がわからなくなります。
初めて取引する相手には詳細を提示するなど、状況に応じて記述方法を使い分けましょう。
小計・消費税・合計
サービスごとの税抜価格を合計した額を「小計」に記載します。
そして、小計をもとに消費税額を計算し、合計金額を算出します。
また、インボイスに対応するには、税率の区分ごとに金額を分けて書かなければいけません。
振込先
振込先として
- 銀行名
- 支店名
- 口座種別(当座・普通など)
- 口座番号
- 口座名義
上記の情報を記します。
口座名義はカタカナで書くのが一般的です。
銀行コード・支店コードを記入しておくと、取引先が振込手続きを進めやすいです。
備考
備考欄には、振込手数料の有無や分割払い、支払い期限が変更となる条件などを記載します。
【記入例】
- 2分割払いとします
第1回ご請求金額:¥80,000 お支払い期限:〇〇年✕月✕日
第2回ご請求金額:¥80,000 お支払い期限:〇〇年△月△日
- 〇〇の場合、支払い期限は△△日となります。
- 振込手数料は御社でのご負担にてお願いいたします。
契約時に交わした取り決めを請求書に明記しておくと、トラブル防止に効果的です。
インボイス制度に対応した請求書の書き方
インボイス対応で必要となる項目は4つあります。
- 登録番号
- 軽減税率の対象である旨の表記
- 税率ごとに区分して合計した税抜または税込対価の額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
項目ごとに解説していきます。
登録番号
適格請求書発行事業者(請求する側)の登録番号を記入する欄です。
法人であれば「T+13桁の法人番号」を、個人であれば「T+事業者ごとに割り振られる13桁の数字」を明記します。
登録番号は、インボイス登録時に発行される「登録通知書」にて確認可能です。
軽減税率の対象である旨の表記
区分記載請求書から加えられた項目で、インボイス対応後も記載が必要となります。
記号や番号を割り振ることで、軽減税率の対象となる取引を区別します。
【記入例】
品目 | 数量 | 単価 | 金額 |
鉄骨組立一式 | 1 | 30,0000 | 300,000 |
商品A※ | 10 | 3,000 | 30,000 |
商品B※ | 5 | 6,000 | 30,000 |
※は軽減税率対象品目
税率ごとに区分して合計した税抜または税込対価の額および適用税率
税率ごとに区分して、税抜きまたは税込みの金額を提示しましょう。
なお、軽減税率対象の請求書と、それ以外の請求書を分けて作成しても構いません。
税率ごとに区分した消費税額等
対価だけでなく、消費税額も税率ごとに記入します。
税抜額・税込額を間違えないように注意しましょう。
【記入例】
対象額(税抜き) | 消費税 | |
10%対象 | ¥50,000 | ¥5,000 |
8%対象(※) | ¥50,000 | ¥4,000 |
小計 | ¥100,000 | ¥9,000 |
税込合計 | ¥109,000 |
建設業で請求書を書く際の注意点

建設業で請求書を書く際の注意点を、3つピックアップしました。
- 金額の書き方
- 人工代の書き方
- 端数の書き方
請求書を作成するときは、これらのポイントを意識してみてください。
金額の書き方
請求書における金額の書き方には、いくつかルールが存在します。
【金額の書き方に関するルール】
- 「¥」または「円」を用いる
- ¥の場合……数字の後ろに「-(伸ばし棒)」を付ける
- 円の場合……金額の後ろに「也」を付ける
- 3桁ごとにカンマを入れる
- ¥と円は混ぜない
【記入例】
- ¥50,000-
- 金50,000円也
数字の後ろに「-」や「也」を付けることで、金額の付け足しや書き換えを防止できます。
人工代の書き方
人工代とは、1日作業をして発生した人件費のことです。
何人が・何日作業を行ったのか、人工代として請求書に記載しましょう。
たとえば、1日3万円で1人が勤務すると「1人工=3万円」です。
上記の費用で2人が4日作業をすると「2人✕4日=8人工」となります。
請求書には、次のように記入します。
品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
人工代(2人✕4日間) | 8 | 人工 | 30,000 | 240,000 |
消費税・小計の計算方法などは、他の項目と変わりません。
端数の書き方
国税庁によると、端数処理の方法は「任意の方法でよい」と定められています。
【適格請求書に記載すべき消費税額等の端数について】
適格請求書の記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります。
なお、切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意の方法とすることができます。
引用URL:端数計算|国税庁
請求書の作成で端数が生じたときは
- 切り上げ
- 切り捨て
- 四捨五入
上記いずれかの方法で処理します。
請求側が勝手に計算方法を決めるとトラブルにつながるので、取引先と事前にルールを決めておきましょう。
建設業の請求書の保管期間

建設業の請求書の保管期間は、法人か個人事業主かで異なります。
それぞれの保管期間を、以下の表にまとめました。
保管期間 | |
法人(欠損金の繰越控除が適用されない) | 7年 |
法人(欠損金の繰越控除が適用される) | 10年 |
個人事業主(消費税課税事業者でない) | 5年 |
個人事業主(消費税課税事業者) | 7年 |
請求書が適切に保管されていなければ、追徴課税などのペナルティを受ける場合があるので注意してください。
請求書を作成する方法

ここまで請求書の書き方について説明してきました。
ですが「そもそも初めて請求書を作るんだけど…」といった方は、どう作れば良いのか悩む方も多いでしょう。
ということで、ここからは請求書の作成方法をいくつか紹介します。
テンプレートを使う
請求書は、Web上で配布されているテンプレートを利用しても作れます。
ひな型が設定されているので、空いている箇所に必要な情報を入力するだけで請求書が作成できるのが魅力。
無料のテンプレートも多く配布されているため、自社に合った項目が網羅されているものを探してみましょう。
また、テンプレートを元にカスタマイズすれば、請求書として必要な項目を網羅させつつ、オリジナルの請求書を作ることも可能です。
エクセル・ワードで作成する
エクセルやワードでも請求書を作れます。
自由なフォーマットで請求書を作れるので、自社のロゴやキャッチコピーを入れるなどオリジナリティのある書面を作ることも可能です。
エクセルやワードの扱いに慣れた方がいるとスムーズに作れるでしょう。
会計ソフトを使う
一般的な会計ソフトには、請求書を作る機能が備わっていることもあります。
企業向けに効率的に請求書を作れるように配慮されているソフトもあるため、簡単な操作で作成できるのがソフトを使う利点です。
取引件数が多い企業など、一括で複数の請求書を作成したい際にも、ソフトは活躍できるでしょう。
また、会計ソフトには保存された請求書データから、会計記帳や確定申告時の処理にも活用できるメリットがあります。
また、請求書を正確かつスピーディーに作りたいなら、弊社の提供する「クラフトバンクオフィス」もおすすめです。
クラフトバンクオフィスの請求機能は、見積からの自動作成や入金管理、出来高ベースで作成したものの一元管理など、効率化と正確性アップが期待できます。
クラフトバンクオフィスの詳細は、サービス資料をダウンロードしてご覧ください。
市販されている書式を使う
請求書は、文具店や100円ショップなどでも販売されています。
電子データで請求書を作る企業が多いですが、請求書は手書きでも問題ありません。
手書きで請求書を作成する場合は、市販されている様式を使うことで手間の軽減ができるためおすすめです。
もし手書きで請求書を書くときには、書き損じや数量の計算ミスに注意して作成を進めましょう。
取引先に指定されたフォーマットを使う
取引先によっては、先方から請求書のフォーマットを指定される場合もあります。
その際には、取引先から請求書のテンプレ―トファイルを受領し、指定された形式に沿って記入しましょう。
決められたフォーマットに沿わない請求書を送付すると、受領してもらえないこともあります。
事前に取引先へ請求書フォーマットの指定の有無を確認しておくと、やり取りをスムーズに進められるでしょう。
請求書の送付方法

請求書の書き方を把握したら、送付方法についても確認しておきましょう。
一般的な請求書の送り方は、以下の3つです。
- 郵送
- FAX
- メール
それぞれ紹介します。
郵送
建設業において、最も一般的な送付方法とされているのが郵送です。
なお、請求書は郵送物の種類として「信書」に分類されます。
信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と規定された郵送物となり、宅配便では送付できません。
また、請求書を送付する際には、送付状を同封しておくと親切です。
送付状には、以下の項目を記載しましょう。
- あて先
- 送付日
- 送信者の社名や氏名
- 送付状のタイトル
- 全文・・・簡単な挨拶文
- 主文・・・請求書についての文言
- 末文・・・締めくくり文
文言の書き方について悩む際には、Web上で掲載されている送付状のテンプレートを参考にすると良いです。
また、送付状は郵送時に送るべき書類とされているため、FAXやメールで請求書を送付する際には基本的に不要です。
FAX
急ぎの際や、取引先から指定があった際にはFAXで請求書を送ることも可能です。
ただし、請求書は原本を保管するのが基本となるため、後日に改めて郵送などで再度送付する必要があります。
また、FAXは送信エラーなどのトラブルが起きやすい点に留意しておきましょう。
送付後には、必ず取引先へ確認の電話を入れるのがビジネスマナーとして慣例とされています。
メール
エクセルやワードなどで請求書を作成した際には電子ファイルをメールで送付できます。
メールで送付する際の「件名」や「本文」には、ビジネスマナーに気を付けた文章を心がけましょう。
また、メールに添付する請求書のファイル形式についても注意しましょう。
取引先からファイル形式を指定された場合には、それに従った形式で請求書を作成します。
とくに指定がない場合は、ファイルの改ざんがしづらいPDFファイルを添付するのが一般的です。
まとめ
今回は、建設業における請求書の概要、書き方、作成する際の注意点を中心に紹介しました。
請求書は、工事などの請求に関しての取引証明や金銭の未払いなどのトラブルを防ぐ役割を持ちます。
請求書はビジネスにおいて重要度の高い書類の1つ。書き方をマスターし、ミスのない請求書作成を徹底しましょう。
また、請求書を正確かつスピーディーに作りたいなら、弊社の提供する「クラフトバンクオフィス」がおすすめです。
エクセルの請求書はファイルの管理が大変で、事務の方以外はすぐに履歴を見返せなかったり、入金管理のために別のファイルを用意したりと、管理の負担がかかります。
クラフトバンクオフィスの請求機能は、見積からの自動作成や入金管理、出来高ベースで作成したものの一元管理など、効率化と正確性アップが期待できます。
クラフトバンクオフィスの詳細は、サービス資料をダウンロードしてご覧ください。
