建設業における働き方改革の関連法と今後の動きについて
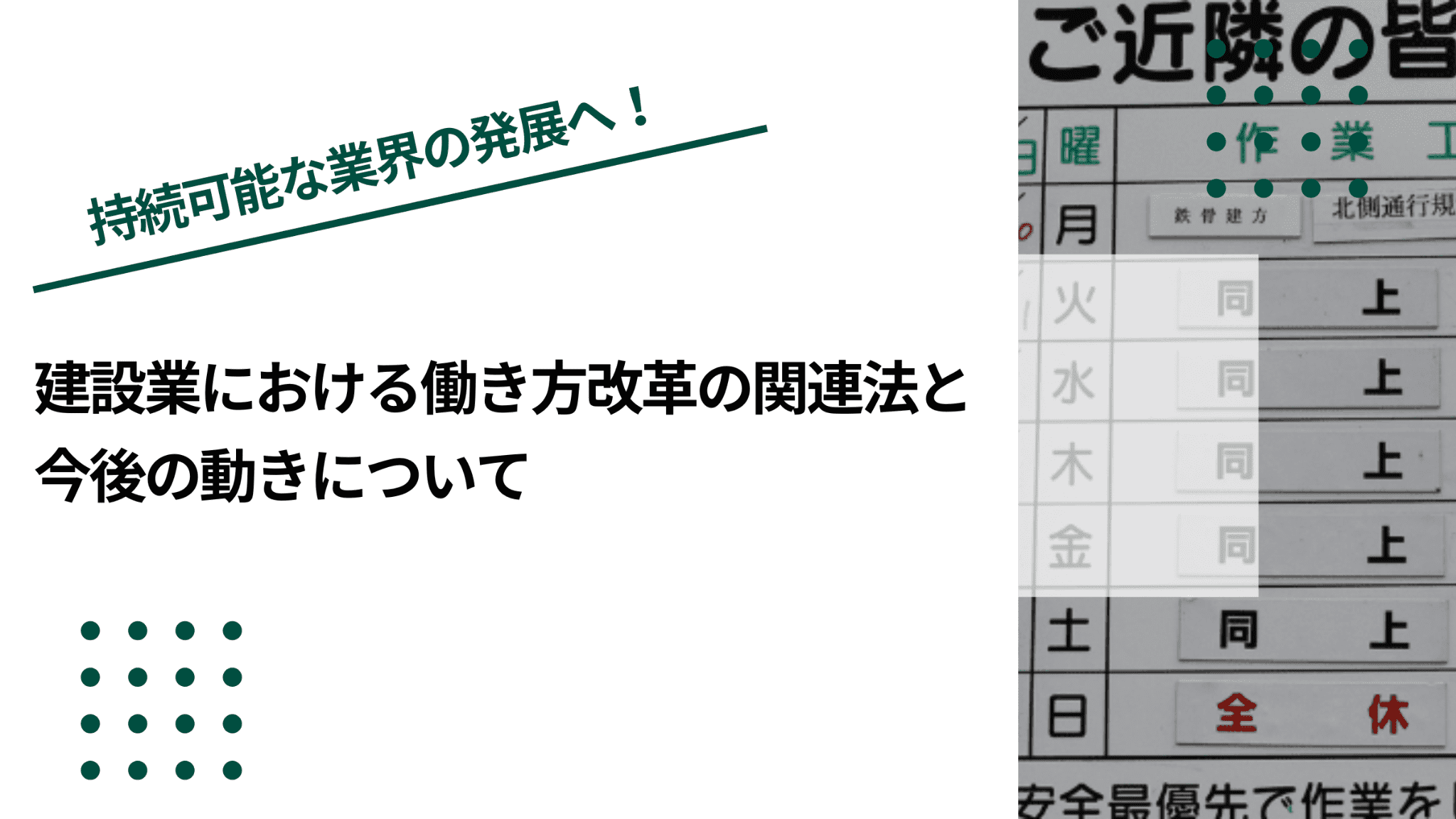
目次
建設業における働き方改革は、長時間労働の是正や週休二日制の推進を通じ、労働環境の改善と生産性向上を目指す取り組みです。
2024年4月からは時間外労働の上限規制が適用され、業界全体での対応が急務となっています。
加えて、少子高齢化による人手不足や若年層の離職率の高さも課題となっており、持続的な発展のためにはICTの活用や職場環境の整備が欠かせません。
本記事では、関連法の概要や今後の動向について詳しく解説します。
建設業の「働き方改革」とは

建設業における「働き方改革」とは、長時間労働の是正や週休二日制の導入、適切な賃金水準の確保などを通じて労働環境を改善し、生産性の向上を目指す取り組みです。
建設業界は他の業界と比べて長時間労働が常態化しており、人手不足・高齢化といった課題が深刻化していることから対策が急がれています。
2024年4月からは、時間外労働に対して罰則付きの上限規制が適用されることになり、これまで以上に労働環境の改善が求められるようになりました。
また、若い世代の人材を確保するためにも、より魅力的な職場環境を整えることが重要です。
改正労働基準法では、時間外労働の上限が原則として月45時間・年360時間と定められ、特別条項付き36協定を結んだ場合でも年720時間以内という制限が設けられています。
こうした規制を踏まえ、国土交通省は「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定し、週休二日制の推進や適正な工期設定、ICTを活用した生産性向上などを進めています。
建設業で働き方改革が重視される理由

建設業界は他の産業と比べて独自の労働環境を抱えており、改善が喫緊の課題です。
長時間労働の常態化や人手不足と高齢化の進行、厳しくなる法規制、そして若手の確保と職場環境の魅力向上など、解決すべき課題は多岐にわたります。
ここでは、建設業で働き方改革が重視される理由を掘り下げます。
労働時間の是正
建設業の労働時間は、他の産業と比較して依然として長く、是正が求められています。
建設業の年間実労働時間は全産業平均を大きく上回り、年間出勤日数も多い傾向が見られます。
労働時間が長いのは、建設業特有の多層請負構造や、短納期での工期設定が影響しているためです。
実際に、建設工事の約65%が4週4休以下の勤務形態であることが示されており、長時間労働が常態化している状況が浮き彫りになっています。
過酷な労働環境は労働者の健康維持を困難にし、ワークライフバランスの実現を妨げるだけでなく、生産性の低下にもつながります。
建設業における労働時間の是正は、労働者の福祉向上と業界の持続的な発展のために必要不可欠な課題です。
高齢化と深刻な人手不足
建設業では就業者の高齢化が進行しており、人手不足が深刻な問題となっています。
国土交通省のデータによると、55歳以上の就業者の割合が高い一方で、29歳以下の若年層の割合は低く、新たな人材の確保が困難な状況が続いています。
加えて、若年層の離職率が高いことも課題の一つです。
このままでは、熟練技能者の退職による技術継承の遅れや、業界全体の活力低下が懸念されます。
若年層の定着が進まない背景には、建設業の労働環境に対するネガティブなイメージや、他の産業と比べた際の労働条件の差があります。
人手不足の問題は既存の労働者の負担をさらに増やし、結果としてさらなる離職を招く悪循環を生み出すことになるでしょう。
建設業が持続的に発展するためには職場環境の改善を進め、若年層にとって魅力ある働き方を提供することが不可欠です。
参考:国土交通省|本格化する少子高齢化・人口減少における課題
時間外労働の上限規制
2024年4月から、建設業にも罰則付きの時間外労働上限規制が適用されます。
これまでは建設業のみ適用が猶予されていましたが、働き方改革関連法の改正により一般企業と同様の基準が求められるようになりました。
具体的には、月45時間・年360時間が原則とされ、特別条項付き36協定を締結しても年720時間が上限となります。
違反した場合には罰則が科されるため、業界全体での対応が急務です。
なお、災害復旧・復興事業に関しては一部例外規定がありますが、大半の建設業者はこの規制を遵守しなければなりません。
若手人材の確保と定着
若手人材を確保し、定着を促進するためには、建設業の職場環境を抜本的に見直す必要があります。
従来、建設業は「3K(きつい・汚い・危険)」というイメージが根強く、長時間労働や休日の少なさが若年層の敬遠につながっていました。
加えて、少子高齢化の影響もあり、労働市場全体で若年層の確保が難しくなっています。
近年の若年層は、ワークライフバランスやキャリアパスを重視する傾向にあり、魅力的な労働条件を提供できなければ人材流出を防ぐことは困難です。
そのため、企業は建設キャリアアップシステムを活用し、技能評価制度の導入を進めることが効果的な施策となります。
さらに、労働時間や休日の改善、待遇の向上を図ることで、より働きやすい環境を整備し、人材確保と業界の活性化を目指す必要があります。
建設業の働き方改革に関連する法律

建設業界における働き方改革は、労働環境の向上と持続可能な業界の発展に欠かせない取り組みです。
大きな変革を支えるためにさまざまな法律が制定・改正されており、業界に大きな影響を与えています。
特に、時間外労働の上限規制、割増賃金率の引き上げ、年次有給休暇の取得義務といった改正は、建設業に従事する人々の働き方を大きく変える要因となりました。
以下、建設業の働き方改革に関連する法律のポイントについて見ていきましょう。
時間外労働における罰則付きの上限規制
これまで建設業は時間外労働の上限規制の適用対象外とされていましたが、働き方改革関連法の改正によって、他業種と同様の規制が適用されることになりました。
一定の猶予期間を経た後、現在では原則として月45時間・年360時間が上限とされ、労使間で36協定を締結した場合でも、年720時間を超えることは認められません。
違反があった場合、罰則が科される可能性があります。
災害復旧・復興工事に関しては特例が設けられていますが、基本的には上限を守ることが求められます。
時間外労働の規制が導入されたことで、長時間労働が常態化しやすい建設業界においても、労働時間の管理強化が不可欠となりました。
割増賃金率の引き上げ
2023年4月から、建設業を含む中小企業に対しても、時間外労働の割増賃金率の引き上げが適用されました。
従来、中小企業には特例措置があり、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は25%に据え置かれていましたが、改正後は50%に引き上げられました。
また、企業はこの割増賃金の代わりに、代替休暇を付与することも可能です。
割増賃金率の上昇は長時間労働を抑制し、労働者の適切な休息を確保するための施策の一つとして位置づけられています。
企業にとっては人件費の増加という課題もありますが、労働環境の改善に向けた取り組みが求められます。
年次有給休暇取得の義務付け
労働基準法の改正により、事業者は労働者に対して最低5日間の年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。
有給休暇の取得率向上を促進し、労働者のワークライフバランスを改善することを目的とした改正です。
一定の条件を満たすすべての労働者に適用され、正社員のみならず非正規雇用者にも影響を与える可能性があります。
事業者は労働者の意向を考慮しながら、取得時期を指定するなどして、確実に有給休暇を取得できるよう配慮しなければなりません。
違反した場合には罰則が科されることもあります。
建設業における働き方改革の今後

建設業にも働き方改革関連法が適用され、時間外労働の上限規制などを通じて労働環境の見直しが進んでいます。
働き方改革の進展により、建設業では生産性向上と労働環境の改善がますます求められています。
2024年問題を皮切りに、2025年には団塊世代の高齢化が一段と進み、労働力の減少が避けられない状況です。
こうした課題を克服するためには、長時間労働に依存した従来の働き方から脱却し、業務の効率化を進めることが不可欠となります。
課題の克服に貢献するのが、国土交通省が推進する「i-Construction」をはじめとするICTやDXの活用です。
測量・設計・施工・管理といったあらゆる工程において自動化や省人化が進めば、作業の効率が飛躍的に向上すると期待されています。
また、若手の人材を確保するためには、週休2日制の普及や柔軟な働き方の導入が急務です。
さらに、経験やスキルに応じた公正な評価制度の確立も重要なポイントとなります。
建設業が持続可能な発展を遂げるためには、技術革新を積極的に取り入れ、多様な人材が安心して働ける環境を整えることが求められています。
まとめ
建設業の働き方改革は、労働時間の是正や人材確保、労働環境の改善を目的に進められています。
2024年の時間外労働の上限規制をはじめ、割増賃金率の引き上げや有給休暇取得の義務化など、法改正が業界に大きな影響を与えています。
今後はICTやDXを活用した業務効率化が重視され、若年層が定着しやすい環境整備が不可欠です。
持続可能な業界の発展に向け、働き方改革の実践が求められています。
