建設業の安全教育資料はどこからダウンロードする?概要とあわせて解説
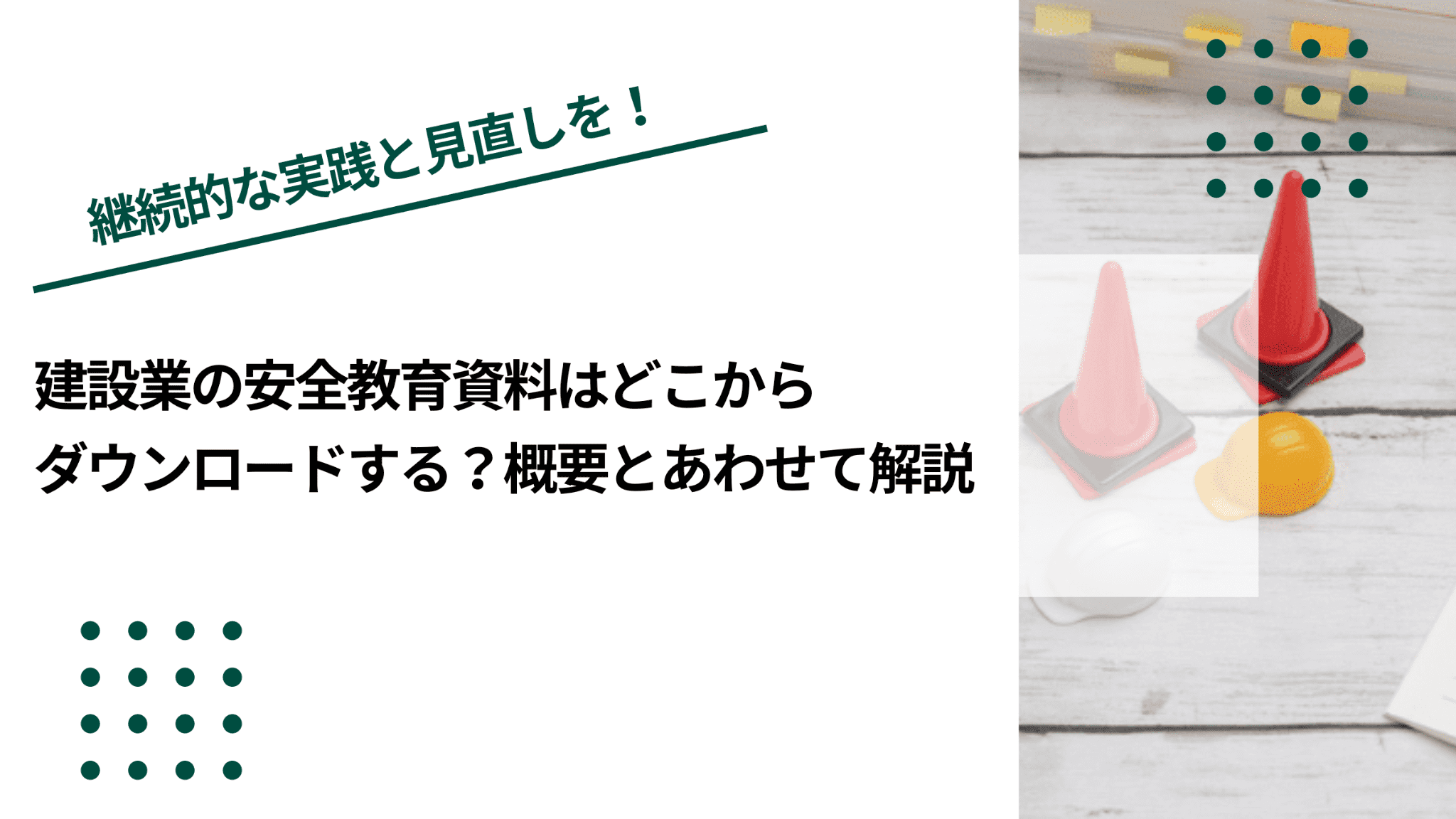
目次
建設現場における安全確保は、事故や災害を未然に防ぐために欠かせません。従って、建設業者には徹底した安全教育が不可欠です。
しかし「どこから適切な安全教育資料を入手できるのか?」という疑問を感じている建設業者も多いのではないでしょうか。本記事では、安全教育に関する基本情報をはじめ、以下のテーマを取り上げています。
- 安全教育の概要
- 安全教育が重視される理由
- 建設業の安全教育資料の種類
- 安全教育資料を活用する際の注意点
さらに、信頼性のある安全教育資料をダウンロードできるWebサイトも紹介しているので、ぜひ活用してください。
建設業における「安全教育」とは

建設業における「安全教育」は、労働災害を防ぐために不可欠な取り組みです。事業者は、作業現場での危険性、安全な作業手順、そして緊急時の対応方法を労働者に教育する責務を負っています。
ここでは、安全教育について、以下のポイントに焦点を当てて詳しく解説します。
- 安全教育の内容
- 安全教育が重視される理由
- 安全教育を実施すべきタイミング
- 安全教育にかかる期間
現時点で十分な安全教育が行われていない、または既存の方針を見直したいと考えている建設業者は、ぜひ参考にしてください。
安全教育の内容
建設業における安全教育は、労働安全衛生法に基づき、多岐にわたる要素をカバーしています。労働災害の防止を目的とした内容には、労働安全衛生関連の法律、安全施工サイクルなどの基本的な事項に加え、現場に特化した具体的な対策が含まれます。
例えば、安全管理体制の確立や安全点検の実施、有害物質に対する措置などが重要です。また、過去に起きた労働災害の事例を学び、原因と対策を理解することで、同様の事故を未然に防ぐことが目指されます。
安全教育は座学にとどまらず、保護具の着用方法や現場での合図、安全指示などの実践的な訓練も重視されています。労働者が現場で直面し得るリスクを具体的に想定し、迅速に対応できるようにすることが重要です。
安全教育が重視される理由
建設業で安全教育が特に重視される理由は、業界特有の高い労働災害発生率にあります。高所での作業や重機の操作など、危険を伴う作業が多く、全産業の中でも死亡事故が多発しているのが現状です。
令和3年度のデータによると、全産業で発生した死亡事故867件のうち、建設業に従事する労働者は288名が犠牲となっており、全体の約33.2%を占めています。
また、建設業は日本経済においても重要な位置を占めており、GDPの5.7%を占める基幹産業で、約499万人の労働者が働いています。
このため、労働災害による影響は非常に大きく、事故による直接的な損失だけでなく、工事の中断や遅延、さらには企業の指名停止といった大きな経済的リスクを伴うのです。
多くの労働災害は、規律違反や不安全行動といった人的要因に起因しています。そのため、作業員一人ひとりがリスクを認識し、危険を回避できるようになるために、安全教育が必要不可欠なのです。
安全教育を通じて、安全意識の向上と、リスク予知・回避の能力を身につけることが期待されており、企業が社会的責任を果たすためにも欠かせない取り組みといえるでしょう。
参考
安全教育を実施すべきタイミング
建設業における安全教育は、労働安全衛生法によって実施するタイミングが規定されています。特に重視されるのは、新たに労働者を雇い入れた際や、作業内容が変更された際です。
新規雇用時には、機械や材料に関する危険性、安全装置や保護具の使い方、作業手順といった基本的な安全知識の教育が求められます。作業内容の変更時には、変更に対応した新たな安全教育が必要です。
加えて、危険または有害な作業を行わせる場合や、職長や安全衛生責任者への法定教育も欠かせません。さらに、下請け業者が新しい工事を開始する際や、新規作業者が初めて現場に入る際には「新規入場者教育」を実施する義務があります。
安全教育は一度行えば終わりではなく、定期的に繰り返すことが重要です。結果、労働者の安全意識を持続的に高められ、かつ現場の安全性も向上します。
安全教育にかかる期間
建設業における安全教育の期間は、労働安全衛生法や関連するガイドラインに基づき、原則1日(6時間)とされています。建設現場での労働災害リスクの高さや、安全を確保するために求められる多様な知識と技能を十分に習得するための時間として設定されている期間です。
しかし、安全教育は一度実施すれば終わりというものではありません。事業者は、労働者の安全意識を常に維持・向上させるため、定期的に内容を見直し、継続的に実施することが求められます。
また、新規雇用時や作業内容が変更された際など、適切なタイミングでの追加教育も不可欠です。
建設業の安全教育資料にはどんなものがあるか

建設業における安全教育資料には、労働災害を防ぐために、法律に基づくものや業界団体が作成した資料など、幅広い種類があります。主に以下の2つに分類されます。
- 法定安全教育資料
- 任意安全教育資料
上記の資料は、座学用テキストや動画、実技訓練用の教材、さらにはチェックリストといった多様な形式で提供されており、ニーズに応じて活用することが可能です。
法定安全教育資料
法定安全教育は、労働安全衛生法に基づき、事業者が労働者に対して実施することが義務付けられているものです。新規雇用時や作業内容の変更時、危険有害業務従事者や職長、新規入場者に対するものが含まれ、それぞれに対応した資料が提供されています。
<新規雇用時教育>
新たに雇用された労働者全員に対して、機械や材料の危険性、安全装置や保護具の使用方法、作業手順など、基本的な安全知識を教育します。
<作業内容変更時教育>
作業内容が変わる際に、変更後の作業に合わせた安全教育を行います。内容は新規雇用時教育と同様です。
<危険有害業務従事者教育>
クレーン操作や高所作業など、危険性の高い業務に従事する労働者向けに、業務に応じた安全教育を実施します。
<職長教育>
職長を対象に、作業中の安全確保や労働者の指揮監督に必要な知識・スキルを習得させる教育です。
<新規入場者教育>
下請け業者が新たに工事を始める際や、現場に初めて入る労働者に対して、現場の安全ルールや注意事項を教育します。
任意安全教育資料
任意の安全教育は、法的な義務はないものの、労働災害を防ぐために積極的に実施することが推奨される取り組みです。労働災害の事例やその対策、5S活動やKY活動など、幅広いテーマにわたります。
法定の安全教育に比べ、より実践的で具体的な内容が多く、企業は自社の状況や教育目的に応じて最適な資料を選定する必要があります。
<日本建設業連合会(日建連)安全対策本部発行資料>
建設現場の交通安全、地下埋設物の事故防止、火薬類の安全管理、海洋工事の安全施工など、さまざまなテーマに対応した資料が提供されています。ポケット版リーフレットやマニュアル、事例集やDVDなど多様な形式で利用可能で、大半は無料でダウンロードできます。
<建設業労働災害防止協会>
建設工事の種類や作業内容、安全管理項目ごとに安全教育資料を提供しています。
<建設現場マガジン>
労働災害の事例やその対策、5S活動やKY活動に関する情報を提供し、現場で役立つ安全管理の知識を発信しています。
<KENTEM>
安全教育の具体的な内容、実施時間や講師の条件などを解説した資料や、安全教育に役立つ建設ツールを紹介しています。
安全教育資料を活用する際の注意点

安全教育資料を活用する際は、いくつかの重要な点に注意する必要があります。まず、使用する資料は、法令の改正や技術の進歩に対応した最新の情報を取り入れていることが求められます。
また、労働者の知識レベルや経験に応じて、分かりやすく作成されたものを選ぶことが大切です。さらに、現場で実際に役立つ知識やスキルを習得できるような、実践的な内容が含まれていることも重要です。
そして、安全教育は一度実施すれば終わりではなく、定期的に繰り返して行うことで、労働者の安全意識を維持し、向上させられます。
建設業の安全教育資料はどこからダウンロードできるのか

建設業の安全教育資料は、さまざまな機関から提供されており、多くは無料でダウンロードできます。主な入手先として挙げられるのは、以下2つです。
自社のニーズに合った資料を上記から適切に入手し、安全教育に活用しましょう。
厚生労働省「職場のあんぜんサイト」
建設業を含む幅広い業種に対応した安全衛生教育資料が提供されているサイトです。動画教材・テキスト・リーフレットといった多様な形式で用意されており、日本語だけでなく英語や中国語、ベトナム語など、多言語対応の資料もあります。
特に「各種教材・ツール」ページでは、業種別・業務別に分類された資料がダウンロード可能です。建設業に関しては、共通事項に加え、型枠施工・左官・コンクリート圧送など、より具体的な業務に特化した教材も提供されています。
一般社団法人「中小建設業特別教育協会」
中小建設業特別教育協会では安全衛生教材を無料で公開しており、社内研修などで活用することが可能です。以下に挙げる、豊富な資料が揃っています。
- 安全標語・標識
- 安全ポスター
- リスクアセスメント用の資料
- 中高年齢労働者向けの動画
- ヒューマンエラー防止の教材
- 熱中症予防
- 危険予知訓練(KY活動)
また、外国人労働者向けの教材や、多言語対応のフルハーネステキストもダウンロードできます。
まとめ
建設業における安全教育は、労働災害防止のために非常に重要です。適切な資料を活用することで、労働者の安全意識を高め、現場でのリスクを最小限に抑えられます。
厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」では、業種別・業務別に分類された多言語対応の資料が提供されており、特に建設業に特化した教材をダウンロードできます。また、一般社団法人「中小建設業特別教育協会」では、無料で多岐にわたる安全教育教材を公開しており、社内研修にも活用可能です。
本記事で紹介したダウンロード先を積極的に利用し、継続的な安全教育を行うことで、安全で効率的な現場運営が実現するでしょう。
