塗装工事の見積書とは|書き方やポイント、インボイスを業者向けに解説
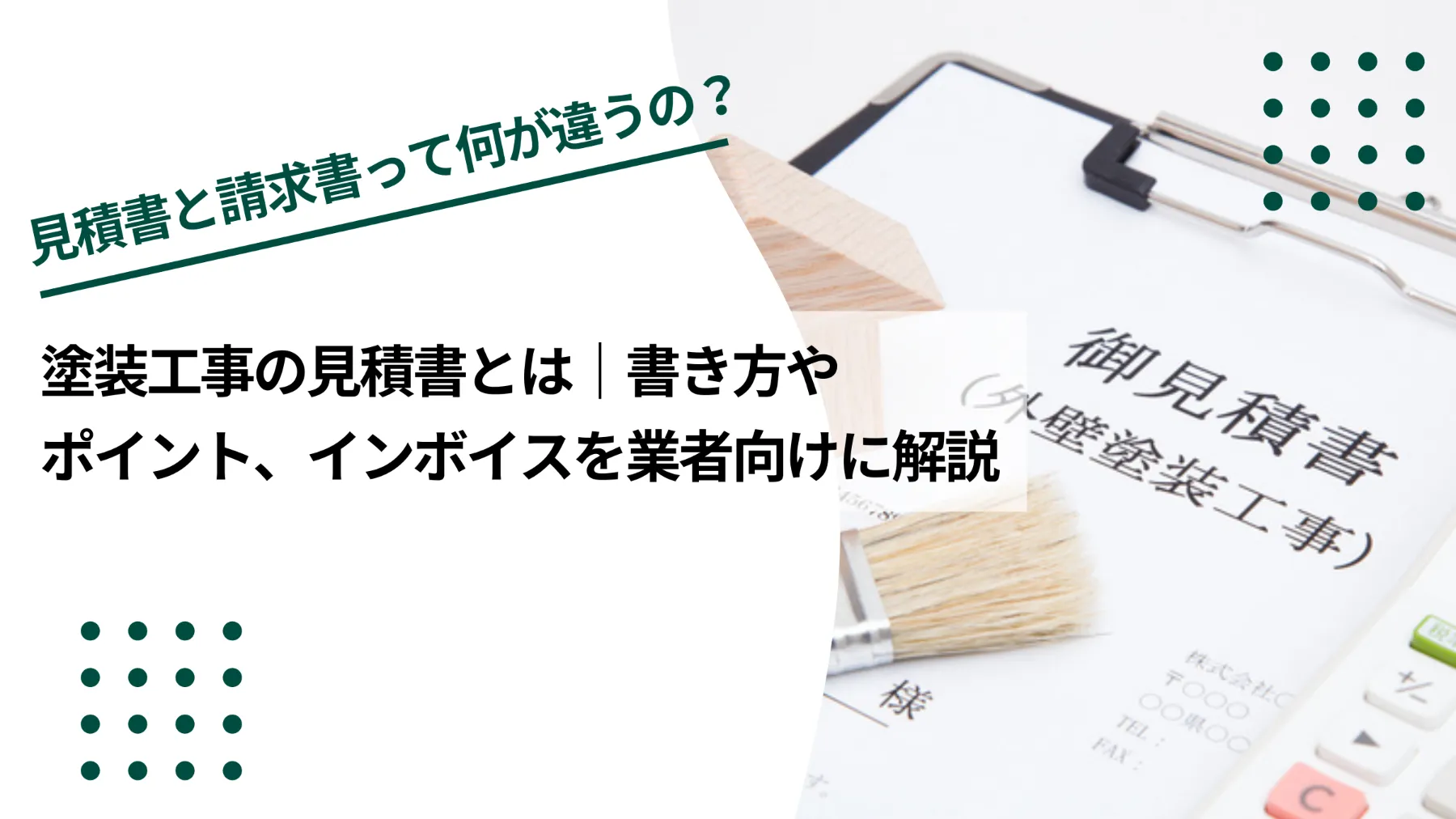
目次
- そもそも見積書とは
- 見積書と請求書の違い
- 塗装工事の見積書の書き方・記入例
- タイトル
- 宛名
- 見積番号
- 発行日
- 作成者名
- 見積金額
- 法定福利費
- 工事名・工事場所・工事概要
- 見積有効期限
- 受渡場所
- 取引条件
- 見積詳細
- 塗装工事における見積書の重要性
- 取引先とのトラブルを回避する
- 企業の信頼性が向上する
- 見積書はインボイス対応が必要なのか?
- 塗装工事における見積書作成のポイント
- 塗料は商品名まで記載する
- 工程ごとに詳細を記す
- 足場代を明記する
- 根拠を持って工事費用を算出する
- 有効期限を記載する
- 塗装の面積・数量を明らかにする
- 塗装工事の見積書の保管期間
- まとめ:塗装工事の見積書で取引先からの信頼を獲得しましょう
見積書とは、契約を締結する前段階で、発注者に対して工事内容の詳細を提示する書類です。
依頼主との認識のズレを防止し、自社の信頼性を高めるためには、見積書の作成が欠かせません。
この記事では、塗装工事における見積書の書き方やポイントを業者向けに紹介します。
インボイス制度と見積書の関係など、塗装業者が気になる点を解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも見積書とは

そもそも見積書とは、契約する前の段階で発注者に対して、工期や工事条件などの取引内容を提示するための書類です。
発注者は見積書の内容を確認し、場合によっては工事業者に変更・交渉を求め、双方が納得できた段階で契約を結びます。
なお、見積書の作成に法的な義務はありません。
しかし、取引内容が曖昧なまま工事が進んだ場合、「思っていた工事内容と違う」という認識のズレが生じるリスクがあります。
認識のズレによるトラブルを防ぐには、見積書を作成して取引の記録を残すことが重要です。
見積書と請求書の違い

見積書と請求書の違いを理解するために、まずは塗装工事の契約の流れを確認してみます。
- 見積もりを依頼する(発注者)
- 見積書を提出する(受注者)
- 発注書を提出する(発注者)
- 納品書を提出する(受注者)
- 受領書を提出する(発注者)
- 請求書を提出する(受注者)
- 工事費用を支払う(発注者)
- 領収書を発行する(受注者)
見積書の作成段階では契約は確定しておらず、「取引を進めるかどうか」を判断するために書類を作成します。
対して、取引の内容をあらためて確認し、代金の支払いを依頼する書類が「請求書」です。
それぞれの違いを、以下の表にまとめました。
見積書 | 請求書 | |
|---|---|---|
提出するタイミング | 工事契約を結ぶ前 | 工事終了後 |
作成する目的 | 工事内容を提示し、正式に取引を進めるかを発注者に検討してもらう | 工事内容を再度確認し、発注者に代金の支払いを依頼する |
見積書は発注先の要求によって修正・再提出する可能性がありますが、請求書に記載した内容が変わることはありません。
塗装工事の見積書の書き方・記入例

ここからは、塗装工事の見積書の書き方を解説します。
以下で詳しく見ていきましょう。
タイトル
見積書の一番上にはタイトルを記載します。
ひと目見て何の書類なのかが分かるように「御見積書」と大きく記します。
宛名
見積先の名称に関する項目です。
宛名の欄には会社名や屋号、氏名を書きます。
(株)や(有)のような略語は使用せず、正式名称を用いるのがマナーです。
敬称については
- 様……個人宛て
- 御中……企業や団体宛て
上記の基準で使い分けます。
ただし、担当者宛ての場合は「様」を使用します。
見積先に対して「宛て」は使わないので注意が必要です。
見積番号
塗装工事では見積書を何度も提出するので、見積番号の記載が欠かせません。
通し番号を振ることで、見積書の検索や再発行などの管理業務が容易になります。
発行日
見積書を作成または発行した年月日を書きます。
見積有効期限の起算日となる項目です。
作成者名
見積書の作成者について
- 会社名
- 住所
- 電話番号
- FAX番号
- 担当者名
これら5点を明記します。
上記に加え、必要に応じて社員や担当者印を捺印します。
依頼主が問い合わせる際に参考とする情報なので、間違いがないようによく見直しましょう。
見積金額
取引先に請求する見積金額は、見積書において特に大事な項目なので、内訳の上にわかりやすく記入します。
見積金額は内訳の下部にも「合計金額」として記載します。
法定福利費
法定福利費とは、法律によって事業者に支払いが義務付けられた福利厚生の費用です。
具体的に、健康保険料や厚生年金保険料などを指します。
国土交通省は「適正な法定福利費を含んだ見積書を作成すること」と「見積書にて法定福利費を内訳明示すること」を呼びかけています。
参考URL:標準見積書の活用等による法定福利費の確保の推進について
工事名・工事場所・工事概要
見積書には工事名・工事場所・工事概要を明記しましょう。
工事場所に関しては、住所または建物の名称を書きます。
工事概要では延床面積や建ぺい率、容積率などを記します。
見積有効期限
見積有効期限を明らかにするための項目です。
見積もりから工事までに期間があくと、見積もり時点から屋根・外壁の劣化状態が変わる可能性があります。
紫外線や天候の影響を受ければ、見積もり当初の材料費や施工期間で工事を進めることは難しいです。
加えて、有効期限を設けなかった場合、材料費が変動して不利益が生じることも。
ただし、短すぎる見積有効期限は「施工を焦らせているのでは?」と顧客に不信感を抱かせてしまいます。
塗装工事の見積有効期限は、1〜2ヶ月程度が一般的です。
受渡場所
塗装工事完了後に、依頼者に受け渡しを行う場所を書きます。
取引条件
見積先とのトラブルを避けるために、細かな取り決めは「取引条件」として見積書に記載しておきましょう。
取引条件の例としては
- 契約を解除した場合は注文者に対して違約金を請求できる
- 工事用の水道や電気は注文者のものを使用する
上記のような内容が挙げられます。
見積詳細
見積の詳細として記入する内容は、以下のとおりです。
- 項目の名称(商品名)
- 仕様・規格・寸法
- 数量
- 呼称
- 単価
- 金額
- 備考
- 小計
- 御値引
- 消費税
- 合計金額
塗装工事では、見積項目を細かく1つずつ書くのが難しい場合に「一式」という表記が使用されます。
内容をひとまとめにできて便利なのですが、一式表記を多用すると内訳が不明確になる恐れがあります。
塗装工事における見積書の重要性

塗装工事における見積書の重要性は、主に2つあります。
- 取引先とのトラブルを回避する
- 企業の信頼性が向上する
塗装工事に携わる方は、ぜひ参考にしてみてください。
取引先とのトラブルを回避する
塗装工事における見積書は、取引先とのトラブルを回避する役割を果たします。
見積書を作成せずに口約束で工事を進めると、取引内容に認識のズレが生じたり、言った・言わないによるトラブルが発生したりする恐れがあります。
取引内容を記録するために、見積書には項目名や数量、金額などを細かく記入しておきましょう。
企業の信頼性が向上する
見積書で「何に・いくらかかるのか」を示せれば、工事費用の根拠が明確になります。
書類作成や経理業務を正しく行える証明となり、自社の信頼性が向上するでしょう。
結果として、受注や再受注につなげやすいです。
さらに、見積書をベースに交渉を進められると、その後の取引がスムーズになります。
見積書はインボイス対応が必要なのか?

インボイス制度とは、消費税の仕入れ額控除額を正しく計算するための方式です。
適格請求書(インボイス)がなければ、仕入税額控除を受けられません。
塗装業者が適格請求書を発行する場合、インボイス制度に対応した方式で書類を作成する必要があります。
なお、基本的には見積書の作成においてインボイス対応は不要です。
インボイス制度で重要なのは「納付する消費税額」なので、フォーマットの変更が求められるのは請求書といえます。
インボイス対応で記載が求められる項目は、以下の6つです。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
適格請求書を発行するには、上記6点を記載した請求書を作成します。
「見積書と請求書を関連付けることで記載項目を網羅したい」と考えているならば、見積書を適格請求書として扱うことは可能です。
参考URL:適格請求書等保存方式の概要
参考URL:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
塗装工事における見積書作成のポイント

塗装工事における見積書作成のポイントを、6つピックアップしました。
- 塗料は商品名まで記載する
- 工程ごとに詳細を記す
- 足場代を明記する
- 根拠を持って工事費用を算出する
- 有効期限を記載する
- 塗装の面積・数量を明らかにする
1つずつ解説していきます。
塗料は商品名まで記載する
塗料の商品名まで記載することが見積書作成のポイントです。
使用する塗料によって、塗装工事の見積価格は大きく変動します。
たとえば、見積書で「塗料〇〇円」と金額のみ記載した場合、発注者は「塗料メーカーのホームページに掲載されている商品はもう少し安価だった」と不信感を抱かれる可能性があります。
商品名・仕様まで細かく記し「この箇所にはシリコン塗料を用いる必要があるため✕✕を見積もりに計上しています」と説明すれば、取引先からの納得を得られるでしょう。
工程ごとに詳細を記す
外壁塗装一式〇〇円と大雑把にまとめられた見積書は、工事の範囲・内容が不明確となり、依頼主は妥当性を判断できません。
「手抜き工事されるのでは」または「不当な価格設定なのでは」という疑問から、受注をためらわれる要因となります。
そのため、塗装工事の見積書では工程ごとに詳細を記入するのが理想的です。
共通工事としてどの作業を行うのか、外壁工事・屋根工事にはどの塗料を使うのか、などを詳しく明記します。
足場代を明記する
塗装工事を安全に進めるには足場の設置が求められます。
足場の設置には仕入れや運搬、設置、解体作業など……、多大な費用が発生するものです。
なかには「足場代無料」をうたい文句として、他の項目で採算を合わせる業者も存在します。
適正な見積価格で取引先からの信頼を得るには、足場代を考慮しなければいけません。
根拠を持って工事費用を算出する
塗装工事に詳しくない発注者の立場では、「3回も塗装は必要なのか?」「同じ塗装の面積でも費用が異なる理由は?」と多くの疑問が生じます。
発注者からの質問に対してスムーズに返答できるように、見積書を作成する際は明確な根拠を持って工事費用を算出しましょう。
有効期限を記載する
紫外線や天候の影響で、建物の劣化状況は日々変化しています。
見積もり時から期間があくと、劣化状態や材料費が変化する可能性があります。
そのため、塗装工事では見積有効期限を設けるのが一般的です。
塗装の面積・数量を明らかにする
塗装工事では塗装の面積・数量にもとづいて価格が決定します。
明確な見積もり根拠を提示するには「一式」としてまとめるのではなく、面積・数量を明らかにすることが大切です。
塗装工事の見積書の保管期間

塗装工事の見積書に関して作成義務はありませんが、契約に至った見積書には保管義務が課せられます。
法人か個人事業主かによって、見積書の保管期間は異なるので注意してください。
それぞれの保管期間は、次のとおりです。
保管期間 | |
|---|---|
法人(欠損金の繰越控除が適用されない) | 7年 |
法人(欠損金の繰越控除が適用される) | 10年 |
個人事業主(消費税課税事業者でない) | 5年 |
個人事業主(消費税課税事業者) | 7年 |
参考URL:No.5930 帳簿書類等の保存期間
参考URL:記帳や帳簿等保存・青色申告
参考URL:No.6621 帳簿の記載事項と保存
法人なら10年間、個人事業主なら7年間保管しておくと安心です。
まとめ:塗装工事の見積書で取引先からの信頼を獲得しましょう
今回の記事は、塗装工事における見積書の書き方やポイントを業者向けに紹介しました。
見積書の作成で意識すべきポイントは
- 塗料は商品名まで記載する
- 工程ごとに詳細を記す
- 足場代を明記する
- 根拠を持って工事費用を算出する
- 有効期限を記載する
- 塗装の面積・数量を明らかにする
上記6点です。
見積書の作成は面倒に感じるかもしれませんが、取引先からスムーズに工事を受注をするために重要な書類です。
今回ご紹介した書き方を参考にして、適切な見積書を作りましょう。
