時間外労働・休日労働に関する協定届とは?建設業における提出義務・記載例・例外の実態まで解説
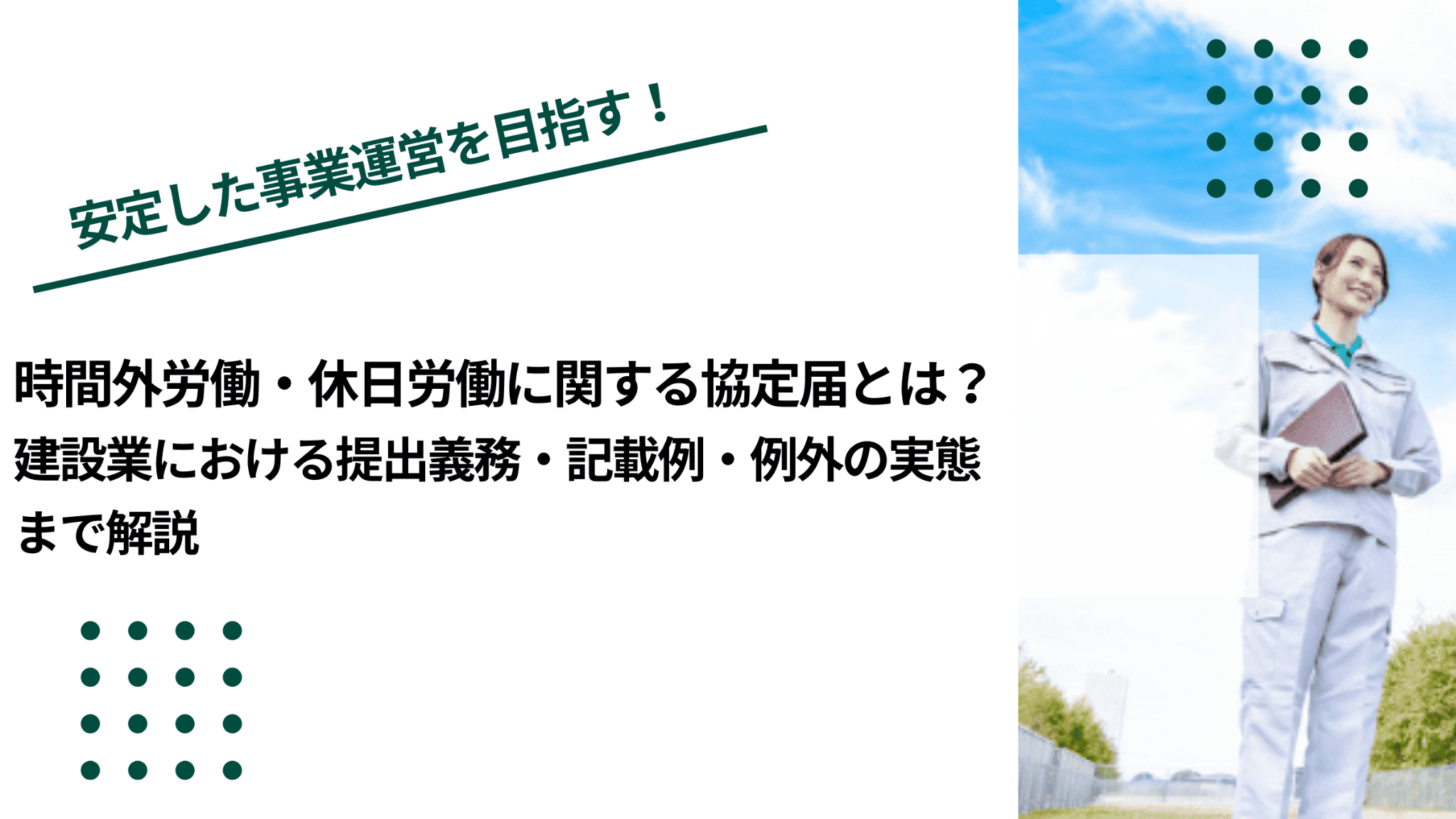
目次
- 時間外労働・休日労働に関する協定届とは
- 建設業への適用が始まった背景
- 建設業における協定届の提出単位と判断基準
- 協定届は基本的に現場ごとに届け出る必要がある理由
- 離れた場所にある現場をまとめて届け出できる場合とは
- 同一の場所でも別事業とみなされる特殊なケース
- どの単位で届け出るべきか判断に迷ったときの対応策
- 新様式による協定届の書き方|建設業特有の項目と特別条項の注意点
- 建設業向けの様式は「災害対応」への配慮が含まれている
- 特別条項を設ける際は「臨時性」の明確な説明が不可欠
- 新様式では時間数の上限記載にも細かな注意が必要となる
- 様式の選択ミスは届出無効のリスクにつながるため要注意
- 提出時の注意点|労基署対応・締結から届出までの流れ
- 協定の締結前には労働者の過半数代表の選出が必要になる
- 協定内容の説明は全従業員に対して十分に行うことが求められる
- 労基署への提出は所轄を間違えないよう事前に確認する
- 提出期限を逃さず年度ごとに見直す体制を整えるべき
- まとめ
2024年4月から建設業にも時間外労働・休日労働に関する協定届、いわゆる「36協定届」の提出が義務化されました。
従来は適用除外とされてきた建設業ですが、長時間労働の是正と職場環境の改善を目的に法制度が見直されています。
現場単位での届出が必要なケースや、様式の選び方、特別条項の注意点など、実務に沿った理解が不可欠です。
本記事では、建設業における協定届の基本から、例外的な運用、提出時の実務対応まで解説していきます。
時間外労働・休日労働に関する協定届とは
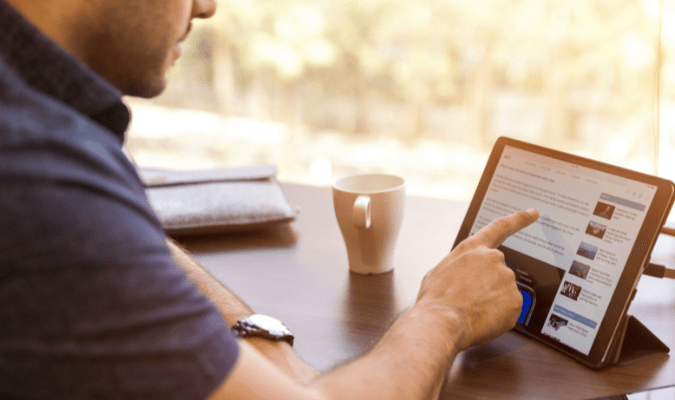
労働基準法では、原則として1日8時間・週40時間を超える労働や、法定休日の勤務を行わせることはできません。
しかし、例外的に労使間で書面による協定を結び、所轄の労働基準監督署へ届け出ることで、一定の範囲で時間外や休日の労働が可能となります。
これがいわゆる「36協定届」です。
特に建設業においては2024年4月より適用猶予が終了し、他業種と同様の上限規制が導入されました。
適切に届け出を行わない場合、企業には行政指導や罰則が科される恐れがあります。
自社の体制に合った届出内容を整備し、現場単位での管理体制も含めて、確実な対応が求められます。
建設業への適用が始まった背景

建設業にも36協定の上限規制が導入されたのは、長時間労働が常態化していた業界の労働環境を見直す必要があったためです。
労働力の確保が難しくなる中、働き手の健康を守る制度整備が求められていました。
特に、若年層の離職を防ぎ人材を呼び込むには、過酷な勤務体制からの脱却が不可欠です。
例えば、これまでは天候や工期の影響で長時間労働を強いられる現場も多く、是正の動きが後回しになっていました。
そのような実情を踏まえ、2024年4月から建設業にも他業種と同様の時間外労働の上限規制が適用されるようになったのです。
建設業における協定届の提出単位と判断基準
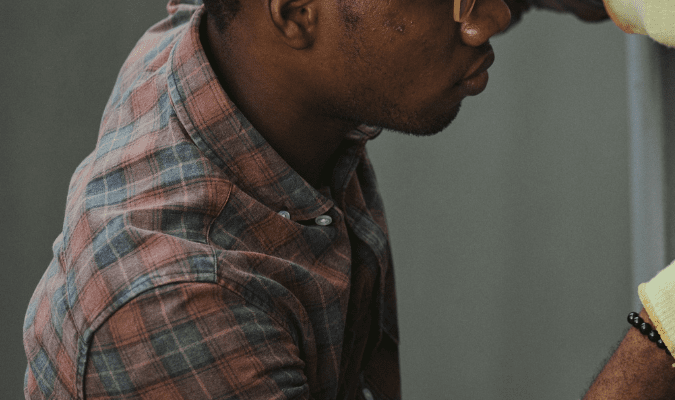
建設業で36協定届を提出する際は「どの単位で届け出を行うか」が重要なポイントになります。
以下で、判断基準や例外的な取り扱いについて詳しく解説します。
協定届は基本的に現場ごとに届け出る必要がある理由
建設業では協定届を会社全体で一括して提出するのではなく、原則として現場ごとに届け出るのが適切とされています。
現場ごとに労働条件や業務内容が大きく異なることが多く、実態に即した労務管理を行うためには、個別の届け出が望ましいとされているのです。
特に元請・下請の関係が複雑になりやすい現場では、各所の状況を正確に反映した届出が求められます。
離れた場所にある現場をまとめて届け出できる場合とは
原則として現場単位での届け出が基本となる一方で、一定の条件を満たす場合は複数の現場をひとつの単位として扱えるケースも存在します。
例えば、労務管理が一括で行われている現場や、現場の独立性が薄く同一の管理者が勤務状況を把握しているような場合は、ひとつの事業所としてまとめて扱うことが可能です。
同一の場所でも別事業とみなされる特殊なケース
ひとつの敷地内で異なる事業を展開している場合、たとえ所在地が同じでも協定届は別々に提出する必要が出てきます。
例えば、同一現場内で建設工事と設備メンテナンス業務が並行して行われており、それぞれの作業指揮系統や勤務体制が明確に分かれているようなケースが該当します。
このような場合は事実上別の事業所と判断されるため、個別の届出が求められるでしょう。
どの単位で届け出るべきか判断に迷ったときの対応策
どの単位で届け出るべきか判断がつかない場合には、自己判断で手続きを進めるのではなく、所轄の労働基準監督署へ事前に相談すると安心です。
実務上の解釈には地域差が生じやすいため、行政側の見解を確認しておくことで後から届出のやり直しや是正指導を受けるリスクを避けられます。
担当者にとっても、事前の確認はスムーズな運用を進めるうえで重要なプロセスになります。
新様式による協定届の書き方|建設業特有の項目と特別条項の注意点
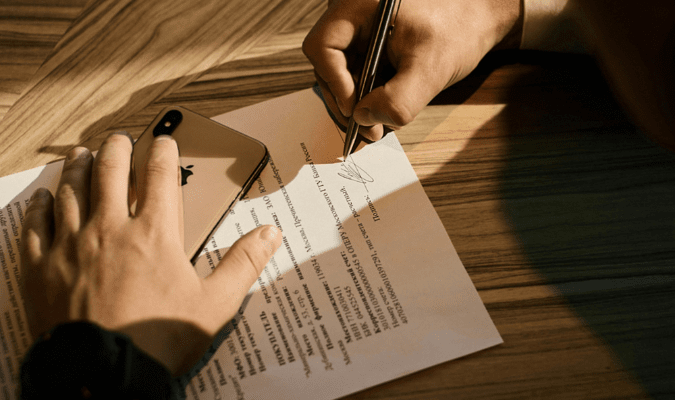
2024年4月からの法改正により、建設業でも新しい様式で36協定届を提出する必要があります。
ここでは、建設業ならではの記載項目や特別条項の留意点について解説します。
建設業向けの様式は「災害対応」への配慮が含まれている
建設業の協定届では、災害時の復旧・復興に関する業務が特別に考慮されており、様式第9号の3の2(一般条項)および3の3(特別条項)を使用する形となります。
災害対応の業務が突発的かつ緊急性を伴うため、他業種より柔軟な時間外労働の取り扱いが求められるためです。
対象業務に該当するかどうかの確認も重要であり、該当しない業務で使用するのは避けましょう。
特別条項を設ける際は「臨時性」の明確な説明が不可欠
特別条項を利用する場合には、単に「忙しい時期がある」といった理由だけでは認められません。
臨時的な事情であることを根拠を持って示す必要があり、内容は協定書に具体的に記載しなければなりません。
例えば「台風による納期変更」や「元請からの急な指示」など、業務上避けがたい要因であることが伝わる書き方を意識しましょう。
新様式では時間数の上限記載にも細かな注意が必要となる
記入欄には、月・年ごとの時間外労働の上限だけでなく、回数や連続日数の制限も求められるようになりました。
従来よりも詳細な内容を盛り込む形式となっているため、事前に勤務実態をよく把握しておく必要があります。
実際の働き方と乖離した上限設定は、のちの指摘や是正の対象になる可能性があるため慎重に記入しましょう。
様式の選択ミスは届出無効のリスクにつながるため要注意
様式の選定を誤ると、提出後に労働基準監督署から差し戻されるケースがあります。
例えば、建設業であるにもかかわらず一般業種向けの第9号を使用した場合、正しい法的効果を持たなくなる恐れもあるのです。
使用すべき様式が分からないときは、早めに管轄の労基署へ確認しておくのが安全です。
提出時の注意点|労基署対応・締結から届出までの流れ
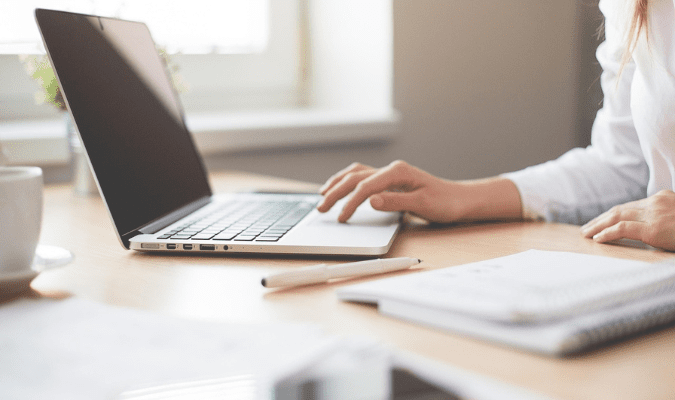
36協定届は単に記入して出すだけでなく、締結の過程や労基署への対応も含めた一連の流れを意識する必要があります。
以下では、各段階の注意点を紹介します。
協定の締結前には労働者の過半数代表の選出が必要になる
協定書を作成するには、まず労働者の過半数を代表する者と合意を得なければなりません。
代表者は会社側が一方的に指名するのではなく、労働者自身の投票や話し合いで適切に選出された人物でなければいけません。
代表者の選定手順に不備があると、協定そのものの効力が認められない恐れもあるので慎重に進めましょう。
協定内容の説明は全従業員に対して十分に行うことが求められる
協定を結ぶ際には、書面で手続きを済ませるだけでは不十分です。
対象となる従業員に向けて、内容の説明や就業条件への影響について丁寧に周知することが重要です。
特に特別条項付きの協定となる場合には、時間外労働の上限や適用場面について具体的に伝えることで、後々のトラブル防止につながります。
労基署への提出は所轄を間違えないよう事前に確認する
協定届を提出する際には、自社の拠点や現場が管轄する労働基準監督署へ正しく提出することが求められます。
事業所単位で届け出る建設業では現場ごとに所轄署が異なる場合もあるため、提出先の選定ミスには注意が必要です。
事前に労基署へ問い合わせておけば、無効扱いとなるリスクを避けられます。
提出期限を逃さず年度ごとに見直す体制を整えるべき
36協定届は一度出せば終わりではなく、基本的には1年ごとに締結と届出が必要です。
新しい年度の開始に合わせて更新するサイクルを社内に定着させておけば、届出漏れを防ぐだけでなく、働き方の変化に応じた協定内容の見直しもしやすくなります。
余裕を持ったスケジュールで準備を始めることが望ましい対応です。
まとめ
建設業における36協定届の対応は、書類を整えるだけでなく、現場ごとの運用実態や労働環境を正確に把握したうえで適切に反映させることが求められます。
様式の選定ミスや届出の遅れは、企業の信頼性を損なう要因にもなりかねません。
今回紹介した内容を参考に、法令に沿った労務管理体制を整備し、安定した事業運営を目指しましょう。
適切な協定の締結と届出は、働く人と企業の双方にとっての安心につながります。
