建設業の手当一覧|基本給との違いや課税・非課税となるケースを紹介
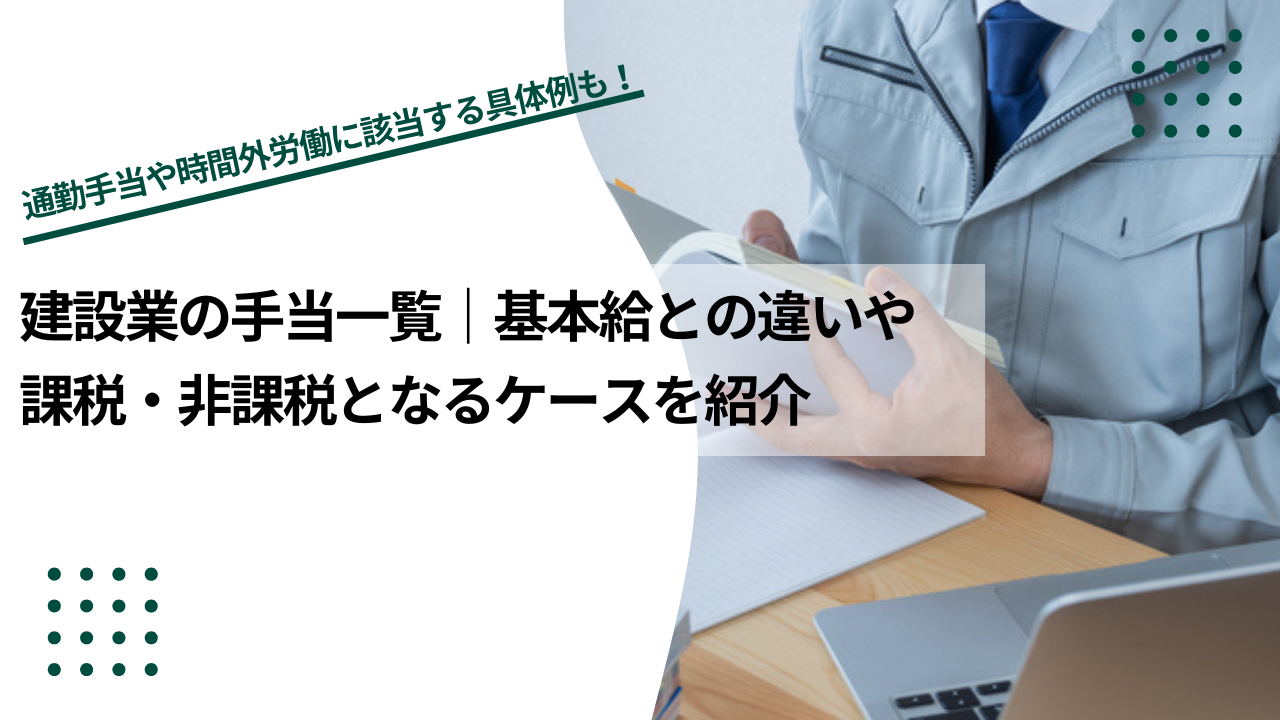
目次
建設業では職務手当・職能手当や現場手当、役職手当などを設けている会社が多いです。
手当は基本的に所得税の課税対象ですが、範囲によっては非課税となるケースもあります。
この記事では手当と基本給の違いや、建設業でよく使われる手当一覧を紹介します。
手当が課税・非課税となるケースも説明するので、ぜひ最後までご覧ください。
建設業の手当とは
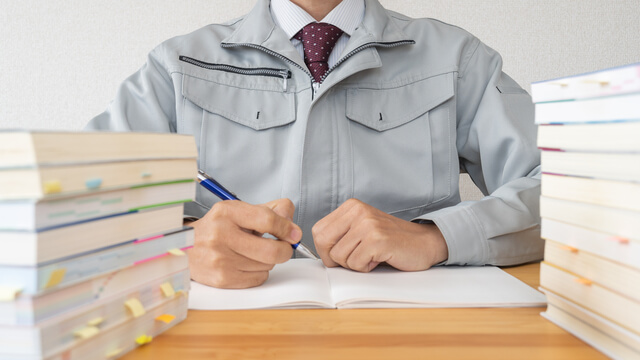
建設業の手当とは、会社が従業員に支給する基本給以外の賃金です。
時間外手当や深夜手当、休日手当の支給は法律で定められています。
対して、現場手当や職務手当など、企業が任意で支給する法定外の手当もあります。
建設業で手当を支給する目的は、次のとおりです。
- 従業員のモチベーションを高める
- 会社への愛着を高める
- 従業員の立場や能力を評価する
- 会社が必要経費を補償して従業員の負担を調整する
手当は給与に含まれるため、原則として所得税が課されます。
ただし、要件を満たす場合のみ、非課税となるケースもあるので注意しましょう。
源泉徴収額を算出するには、手当の課税・非課税を正確に把握することが重要です。
手当と基本給との違い
毎月固定で支払われ、従業員の仕事内容や勤続年数、能力、経験、業績により変動する賃金を「基本給」といいます。
内訳の中でもっとも多くの割合を占める、賃金の根幹となるものです。
一方、手当は経費を補填する存在であり、条件を満たす人にのみ支払われます。
同じ会社で働いていても、従業員によって手当が支給されるタイミング・金額には差が生じるのです。
手当と福利厚生との違い
手当は条件に当てはまる従業員にのみ支払われますが、福利厚生はすべての従業員に対して平等に支給されます。
そもそも福利厚生とは、会社が従業員に向けて提供するサービスです。
宿泊施設・レジャー施設の割引制度や人間ドックの費用負担、社員食堂、社員旅行など、種類はさまざまです。
手当は給与扱いとなり所得税の課税対象ですが、福利厚生として認められたものは非課税となります。
手当は就業規則に規定する義務がある

手当は就業規則に規定しなければいけません(労働基準法第89条)。
就業規則には
- 必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)
- 当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)
の2つがあります。
絶対的必要記載事項は、以下の3つです。
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに交替制の場合には就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
参考URL:就業規則を作成しましょう
手当は賃金と同様の扱いになるため、就業規則への記載義務が発生します。
記載漏れがあった場合、労働基準法違反となる可能性があります。
参考URL:労働基準法 | e-Gov法令検索
法律で定められている建設業の手当一覧

以下3つは労働基準法によって、支給と割増率が定められている手当です。
種類 | 支払う条件 | 割増率 |
|---|---|---|
時間外 | 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき | 25%以上 |
時間外労働が限度時間(1か月45時間、1年360時間等)を超えたとき | 25%以上 | |
時間外労働が1か月60時間を超えたとき | 50%以上 | |
休日 | 法定休日(週1日)に勤務させたとき | 35%以上 |
深夜 | 22時から5時までの間に勤務させたとき | 25%以上 |
参考URL:しっかりマスター 割増賃金編
従業員がこれらの手当に該当する場合、会社の就業規則に規定がなくても、会社には手当を支払う義務が発生します。
それでは、手当の内容を解説していきましょう。
時間外手当(残業手当)
建設業は、工期厳守や人手不足により、残業が発生しやすい業種です。
労働時間が就業規則で定められた所定労働時間を超える場合、超過した時間に対する時間外手当(残業手当)を支払わなければいけません。
時間外手当に該当する・しないを考えるために、厚生労働省が掲げる「労働時間の考え方」を見てみましょう。
【労働時間の考え方】
労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たること。
たとえば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当すること。
要約すると「作業員の自由がなく、業務遂行のために義務づけられた行動は時間外労働とみなされる」ということです。
着替えや作業準備、清掃は時間外労働に当たりますが、業務の指示を受けない状態での移動時間は時間外労働に当たりません。
なお、法定外労働時間が1か月に60時間を超過する際は
- 1時間あたりの給料に50%以上を上乗せする
- 有給休暇を与える
上記どちらかの対応が必要です。
以前は中小企業に関して猶予措置が設けられており、月60時間超の残業割増賃金率は「25%以上」でした。
しかし、2023年より猶予措置が廃止され、大企業・中小企業にかかわらず、月60時間を超える残業の割増率は「50%以上」と決められています。
参考URL:時間外労働の上限規制
参考URL:使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
参考URL:月60時間を超える法定時間外労働に対して
参考URL:月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
深夜手当
深夜手当とは、22時から翌朝5時までの労働に対する割増賃金のことです。
深夜手当では通常の給与に、25%以上の賃金を上乗せした金額を支払う義務があります。
例として、22時から翌朝5時の深夜手当に該当する時間に、時間外労働を行った場合は
- 深夜手当:割増率25%以上
- 時間外手当:割増率25%以上
これら2つの手当を考慮し、1時間あたりの賃金に50%以上を上乗せしなければいけません。
休日手当
会社が従業員に必ず与えなければいけない休日を、法定休日といいます。
労働基準法において、法定休日は1週間に1日与えるものと定められています。
【労働基準法第35条】
〇第1項
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。
〇第2項
前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
参考URL:労働基準法 | e-Gov法令検索
この法定休日に労働した場合、休日手当として通常賃金に35%以上の賃金を上乗せして支払う義務があるのです。
法律では「35%以上を上乗せ」と規定されていますが、金額が上回る分には問題ありません。
従業員の意欲向上を目的として、休日手当に1.5倍や2倍の金額を支給する会社も存在します。
参考URL:労働時間・休日
【課税対象】任意で支給する建設業の手当一覧
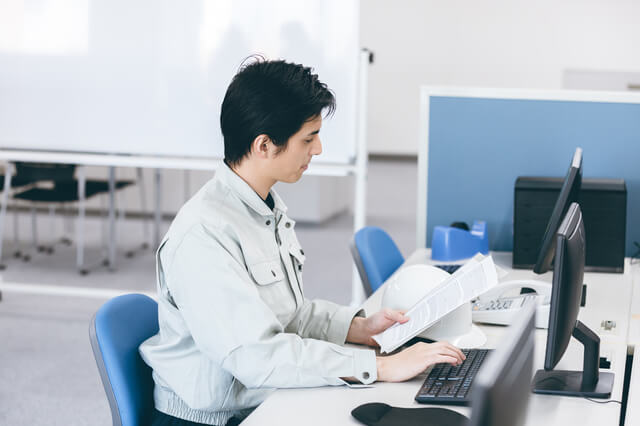
法律で定められている手当以外に、会社は任意に手当を設定できます。
ここからは、建設業が設けることの多い手当について紹介しましょう。
- 職務手当・職能手当
- 役職手当(管理職手当)
- 扶養手当・家族手当
- 住宅手当
- 地域手当
- 転勤手当・海外赴任手当
- 単身赴任手当
- 皆勤手当・精勤手当
- 現場手当
- 責任者手当
- インフレ手当
任意の手当のなかでも、まずは課税対象となるものについて説明していきます。
職務手当・職能手当
職務手当は、業務の内容や難易度、責任の度合いに応じて支給される手当です。
一方、職能手当は業務遂行の能力に対して支払われます。
業務遂行能力は評価が難しいため、勤続年数や年齢を評価基準とするケースも珍しくありません。
建設業で勤務する作業員は、特殊な技能や資格が求められたり、工事の管理といった責任の重い役割を担当したりします。
そのため、多くの建設業者では職務手当・職能手当が設けられています。
役職手当(管理職手当)
管理職や主任など、役職者に対して支払う手当を、役職手当(管理職手当)といいます。
役職者は部下の指導や工事全体の管理といった責任の重い業務を担当するため、その分多くの報酬が支払われる仕組みになっているのです。
なお、業務の管理監督者には、時間外手当を支払う義務が生じません。
管理監督者に時間外手当が出ない分、役職手当として報酬を支給する会社もあります。
ただし、管理職と管理監督者を混同しないように注意しましょう。
管理監督者とみなされるポイントは、次の3点です。
- 経営者と一体的な立場で仕事をしている
- 出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない
- その地位にふさわしい待遇がなされている
上記に当てはまらないときは管理監督者でないので、管理職であっても時間外手当を支払う必要があります。
参考URL:しっかりマスター 管理監督者編
扶養手当・家族手当
扶養手当・家族手当は配偶者や子どもなど、同居する家族がいる従業員に対して支給する手当です。
家族が多いほど経済的な負担は増えるので、従業員の負担を軽減するために支給されます。
家族手当は、従業員が扶養しているかどうかにかかわらず、家族の収入状況や年齢によって支払われるのが一般的です。
なお、扶養手当は従業員が扶養する家族への支給を目的とします。
会社で扶養手当を設ける際は、手当の支給条件として、自社における扶養家族の定義を明確にすることが大切です。
住宅手当
従業員の住居費用を補助する手当を、住宅手当といいます。
住宅手当の主な目的は
- 住宅費の負担を減らすため
- 寮や社宅に入居できない従業員に対して、不平等を調整するため
上記2点です。
「従業員が借りた物件について、上限付きで家賃の一部を補助する」または「会社が借り上げた物件に、従業員が費用を部分的に負担して入居する」などの形式があります。
従業員における住環境の整備は、生活の質の向上につながります。
従業員のストレスが軽減されて心身ともに健康になれば、工事の品質アップも見込めるでしょう。
地域手当
地域手当とは、物価が高い地域に勤務する従業員に支払う手当を指します。
都市部は地方と比較して、住宅や食料品などが高額になる傾向にあります。
このような地域を要因とした、出費の差額を埋めることが地域手当の目的です。
建設業は人事異動が頻繁に実施されるため、地域手当を設けることがあります。
転勤手当・海外赴任手当
さまざまな場所で工事が発生する建設業において、長期出張や転勤は少なくありません。
特に施工管理職は、プロジェクトごとに現場が変わるため転勤が頻繁に発生します。
引っ越しの手間や費用、生活リズムの変化によるストレスといった、転勤のデメリットを補うために支給されるのが転勤手当・海外赴任手当です。
加えて、転勤手当とは別として、会社が赴任旅費・引越し費用を負担するケースも見られます。
転勤手当・海外赴任手当は
- 異動の距離
- 期間
- 単身か家族帯同か
などを考慮したうえで金額が決まります。
単身赴任手当
単身赴任手当とは、転勤または長期出張により、単身赴任する従業員への手当です。
遠方の現場に赴くことの多い建設業では、単身赴任手当を支給する会社が多い傾向にあります。
単身赴任は、従業員のストレス度合いや家族関係に影響を及ぼす可能性があります。
そのため「単身赴任期間の上限を設ける」などの配慮を払うことが重要といえるでしょう。
皆勤手当・精勤手当
無断欠勤や遅刻がない従業員に支払うのが皆勤手当で、遅刻や欠勤が少ない従業員に支払うのが精勤手当です。
精勤手当に該当する条件は、賃金規程等で明記します。
注意点として、有給休暇を使用した休暇は欠勤とみなされません。
有給休暇と無断欠勤を区別した上で、皆勤手当・精勤手当の該当者を確認しましょう。
現場手当
建設業では屋外・高所作業や夜間工事など、オフィスワークよりも過酷な環境下にさらされます。
建設業特有の危険を伴う作業に対して支払われるのが現場手当です。
なお、現場手当を高所作業手当や夜間作業手当と呼ぶ会社もあります。
現場の規模や場所、作業の危険度に応じて、手当の額が決定します。
責任者手当
現場代理人や主任技術者、監理技術者など、現場で大きな責任を負う作業員に支払われるのが責任者手当です。
建設業における責任者は、現場の進捗管理や問題解決、発注者とのやり取りといった幅広い業務を担当します。
そのため、肉体的かつ精神的に多大なストレスを感じる方も珍しくありません。
金銭的な補償をすることで、作業員の負担軽減を図るのが責任者手当の意図です。
インフレ手当
物価高騰が進むと生活費がかさむため、給与額が増えない限り作業員の生活は厳しくなってしまいます。
インフレの影響を考慮し、作業員の生活を支援するために支払われるのがインフレ手当です。
インフレが進む現代において、インフレ手当を支給する企業が増えています。
【範囲によっては非課税】任意で支給する建設業の手当一覧

建設業が任意で支給する手当のなかで、範囲によっては非課税となるものを紹介します。
- 通勤手当
- 出張手当
- 資格手当・研修手当
それぞれ非課税となる条件を説明するので、ぜひ参考にしてみてください。
通勤手当
通勤手当とは、通勤にかかる費用を会社が負担する方式です。
時間外手当や休日手当とは異なり、通勤手当の支給は法律で義務付けられていません。
しかし、令和2年度の調査において、通勤手当を支給している会社は92.3%でした。
通勤手当の支給は義務ではありませんが、手当を用意するほうが人材獲得を有利に進められるでしょう。
さらに、作業員の自由がない状態での移動は「労働時間」とみなされます。
移動が労働時間と判断される場合、通勤手当に加えて時間外労働が発生する可能性があるので注意してください。
移動が労働時間に当たる例 | 移動が労働時間に当たらない例 |
|---|---|
|
|
参考URL:令和2年就労条件総合調査の概況
参考URL:そもそも「労働時間」とは? 「通勤時間」とは?
また、通勤手当が非課税となるには、支給額が一定以下であることが条件です。
通勤方法 | 1か月当たりの限度額 | |
|---|---|---|
電車・バス通勤者 | 15万円 | |
マイカー・自転車通勤者 | 片道の通勤距離が2km未満 | 全額課税 |
片道の通勤距離が2km以上10km未満 | 4,200円 | |
片道の通勤距離が10km以上15km未満 | 7,100円 | |
片道の通勤距離が15km以上片道の通勤距離が25km未満 | 1万2,900円 | |
片道の通勤距離が25km以上35km未満 | 1万8,700円 | |
片道の通勤距離が35km以上45km未満 | 2万4,400円 | |
片道の通勤距離が45km以上55km未満 | 2万8,000円 | |
片道の通勤距離が55km以上 | 3万1,600円 | |
参考URL:No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
参考URL:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
上記の限度額を超えた分は、所得税の課税対象となります。
出張手当
出張中は自炊が難しく、普段よりも食費や雑費がかさみます。
宿泊費や交通費はもちろん、出張により負担がかかった食費や諸雑費は、出張手当として会社が補填するのが一般的です。
出張手当が非課税と判断される基準は「業務に必要と認められるもので、金額が適正な範囲内か」です。
たとえば、日帰り可能な現場にもかかわらず宿泊した場合、交通費は非課税扱いですが宿泊費は課税対象となります。
出張が発生する度に妥当かどうかを判断するのは手間がかかるため、出張手当の内容は旅費規程として明記するとよいでしょう。
参考URL:〔傷病者の恩給等(第3号関係)〕
資格手当・研修手当
建設業で人材がスキルアップするには、資格取得や研修受講が欠かせません。
資格や研修を奨励するために、従業員に対して支給する手当を資格手当・研修手当といいます。
なお、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用であれば、課税の対象外です。
具体的には
- 免許や資格を取得するための研修会
- 講習会等の出席費用
- 大学等の聴講費用
などが挙げられます。
ただし「技術者が簿記を取得する」のように、業務と資格が直結しないときは課税対象です。
参考URL:No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
まとめ:建設業の手当は基本的に課税対象だが、非課税となるケースもある

今回の記事は、手当と基本給の違いや、建設業でよく使われる手当一覧を紹介しました。
時間外手当や深夜手当、休日手当は労働基準法により、支給が義務付けられています。
さらに、建設業で支給されることの多い手当は、次のとおりです。
- 職務手当・職能手当
- 役職手当(管理職手当)
- 扶養手当・家族手当
- 住宅手当
- 地域手当
- 転勤手当・海外赴任手当
- 単身赴任手当
- 皆勤手当・精勤手当
- 現場手当
- 責任者手当
- インフレ手当
- 通勤手当
- 出張手当
- 資格手当・研修手当
時間外手当を支給するには、作業員の労働時間を正確に把握する必要があります。
労働時間を計算するためにITツールを導入するならば、弊社クラフトバンクが提供するクラフトバンクオフィスがおすすめです。
ご興味のある方は、サービス資料をダウンロードしてみてください。
