【2024年最新版】造園業の年収における基礎知識まとめ
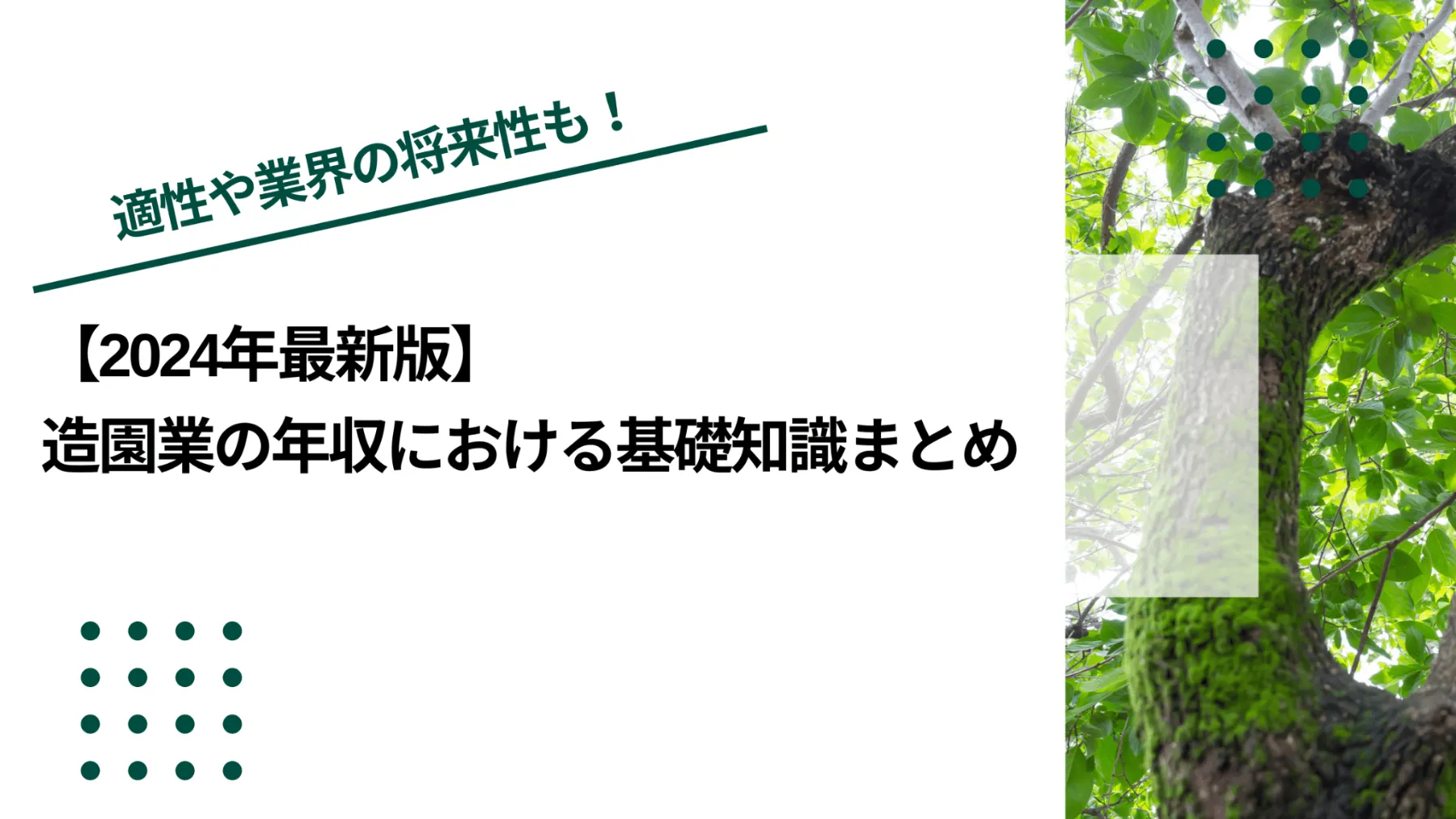
目次
公園や庭、緑地などを対象に工事をし、さまざまな場所を緑化する専門事業を行うのが造園業の特徴です。
建築物そのものを手がけるわけではないものの、豊かな緑を加えて建築物に命を吹き込むといった意味で魅力がある事業と言えます。
実際に造園業を営む、もしくは造園業を営む企業に在籍しようと考える際、気になるのは平均年収ではないでしょうか。
今回は、
- 造園業の平均年収
- 造園業で平均年収を上げる方法
- 造園業の適性
- 造園業の将来性
について解説します。
造園業の平均年収は?

厚生労働省の発表するデータによると、造園業の平均年収は360.7万円(令和4年度段階)でした。
もっと年収が低い年代は19歳から20代前半の200万円台で、もっとも高い世代は40代後半の458.86万円です。
国税庁の発表した「令和4年分民間給与実態統計調査」による全国の平均年収が458万円であることを考えると、造園業はある程度の年齢まで達さない場合の平均年収は高くないと考えられます。
【資格取得編】造園業で年収を上げる方法

造園業を生業とし、年収をより上げるために、資格を取得する方法が推奨されます。
ここでは、造園業で年収を上げるために取得しておきたい以下の資格について解説します。
造園業の仕事をより円滑に進めるためにも資格取得は重要になるため、ぜひ参考にしてください。
造園施工管理技士
造園施工管理技士は建築業法に基づいた国家資格です。取得すると、公園や緑化工事などの大規模な造園工事を計画し、現場での工程や品質、安全管理も行えます。
1級と2級があり、1級を取得すればさまざまな造園工事で監理技術者として活躍できるでしょう。
土木施工管理技士
土木施工管理技士とは、土木工事における施工計画作成や工程・安全の管理などを行える専門技術者です。
造園業でも、土木施工管理技士が在籍している事業所もあるため、取得しておくことで造園業者としての幅が広がると考えられるでしょう。
造園技能士
庭園の造園や庭木のお手入れ、公園・街路樹の管理など、造園工事に関する技術・知識を有していると証明できるのが造園技能士という資格です。
造園業を営むうえで必須の資格というわけではないものの、造園関連の技術と知識を一定量有している証明になるため、今後造園業の仕事を行ううえで取得が推奨される資格と言えます。
その他民間資格
造園業は上記3つの資格以外にも、以下に挙げる資格もあわせて取得するとより有利に活躍できると考えられます。
- 樹木医:樹木の状態を診察し、治療・保護ができる専門家
- エクステリアプランナー:塀や外庭などの設計・工事管理を実施できる専門家
- ビオトープ管理士:環境保全の専門知識を通じ、自然の保護・再生を行える技術者
いずれの資格も、造園業におけるさまざまな場面で役立つと想定されるため、メイン3つの資格とあわせて取得を検討してみましょう。
【独立開業編】造園業で年収を上げる方法

造園業で年収を上げる方法として、独立開業も考えられます。ここでは、造園業における独立開業と年収の関係性や、独立するための方法を紹介します。
造園業は独立すれば年収が上がる?
一人親方団体労災センター共済会によると、造園業で独立し、いわゆる「一人親方」になった場合の平均年収は、約700〜800万円とのことでした。
職種としての平均年齢が360.7万円(令和4年度段階)と考えると、独立した場合の平均年収は2倍近くになるとわかります。
ただし、造園業者として独立して年収を上げるのであれば、相応の技術や知識を身につけなければなりません。
顧客からの信頼性を得るために自身で営業活動を行ったり、より信頼されるために資格取得を検討したりと、独立して年収を上げるには努力を重ね、結果を出す必要があります。
また独立は、これまでチームで行ってきた業務を一人でこなさなければならないため、その分負担が増えてしまうことも認識しておきましょう。
造園業で独立するための方法
造園業で独立したい場合は、まずある程度の技術と知識を身につけるうえでも、親方のもとで修行を重ねましょう。
そのうえで、開業資金や作業場所などを用意し、個人事業主として登録します。開業届など、各種手続きもあわせて行うことで、独立自体は可能です。
「造園業は独立すれば年収が上がる?」の項目でも触れましたが、独立にあたっては自身での営業活動や資格取得が重要になることも覚えておきましょう。
造園業で年収を上げるには適性を理解することも大切

造園業の仕事を生業とし、かつ年収を上げるには自身の適性を理解することも重要です。
主に、以下の特徴に当てはまる人が造園業に向いていると言えます。
- 植物の育成に興味がある
- 繊細な作業が得意
- 忍耐強さに自信がある
- 体力がある
- 色彩感覚・デザイン感覚に優れている
- コミュニケーション能力がある
- ものづくりが好き
上記に加え、造園を通じて自身のセンスを具現化したいと考えてる人も、造園業に向いていると考えられます。
また、植物や剪定、造園に関する法律など、造園業につながる知識を業務スキルとして取得しておくことも大切です。
年収にも関係する造園業の将来性

造園業に限らず、業界の将来性は年収にも大きく関わってきます。ここでは造園業の将来性について、現状の課題や今後といった視点から解説します。
造園業の課題
造園業界は、人口減少・高齢化が原因の人手不足が課題とされています。人手不足に伴った、後継者不足も重大な課題に挙げられるでしょう。
造園業は炎天下での作業が多く、仕事そのものの「つらさ」が若年層を中心とした人材の獲得を遠ざけてしまう側面もあるでしょう。
また造園業は受注産業であるため、発注者の景況に左右されがちな点も課題です。大手元請け企業に案件が集約される構造が定番化されており、安定した案件獲得が難しい傾向にあります。
加えて、さまざまな業界で急務とされている「デジタル化」も、造園業における課題です。いかに早くIT技術を導入するかによって、造園業者としての今後が左右されるでしょう。業務時間の短縮や効率化などを、デジタル視点で改善することが重要になります。
造園業は今後どうなる?
課題こそ多いものの、造園業自体は将来性が期待される業界です。
その理由には、社会全体の環境保全に対する意識向上が挙げられます。
社会的に環境保全への意識が高まっているため、緑化政策に関する造園業の仕事が増加すると考えられるでしょう。
また、造園業では人材不足が懸念されており、資格を有した人材も不足しています。
そのため、資格や経験の有無を重視せず、人材を雇用する造園業者も増えると考えられます。
事業者によっては資格取得をサポートする支援制度を実装しているため、従事しながら技術・知識を身につけていくことも可能な業界と言えるでしょう。
まとめ
今回は、造園業の平均年収や、年収に関連する情報をまとめました。
造園業の年収自体は決して高いとは言えませんが、資格取得や独立開業を通じて上げることは可能です。
どんな資格を取得すべきか、どのようなビジョンをもって独立するか、熟考のうえ行動することが年収を上げる鍵になるでしょう。
加えて今回は、造園業を生業とするために覚えておきたい適性や、業界としての将来性についても解説しました。
造園業者として従事していきたい、造園業をメイン事業とする法人を立ち上げたいと考えている人にとって、本記事の内容が少しでも参考になれば幸いです。
