グリーンファイルとは? 作成義務やその種類について
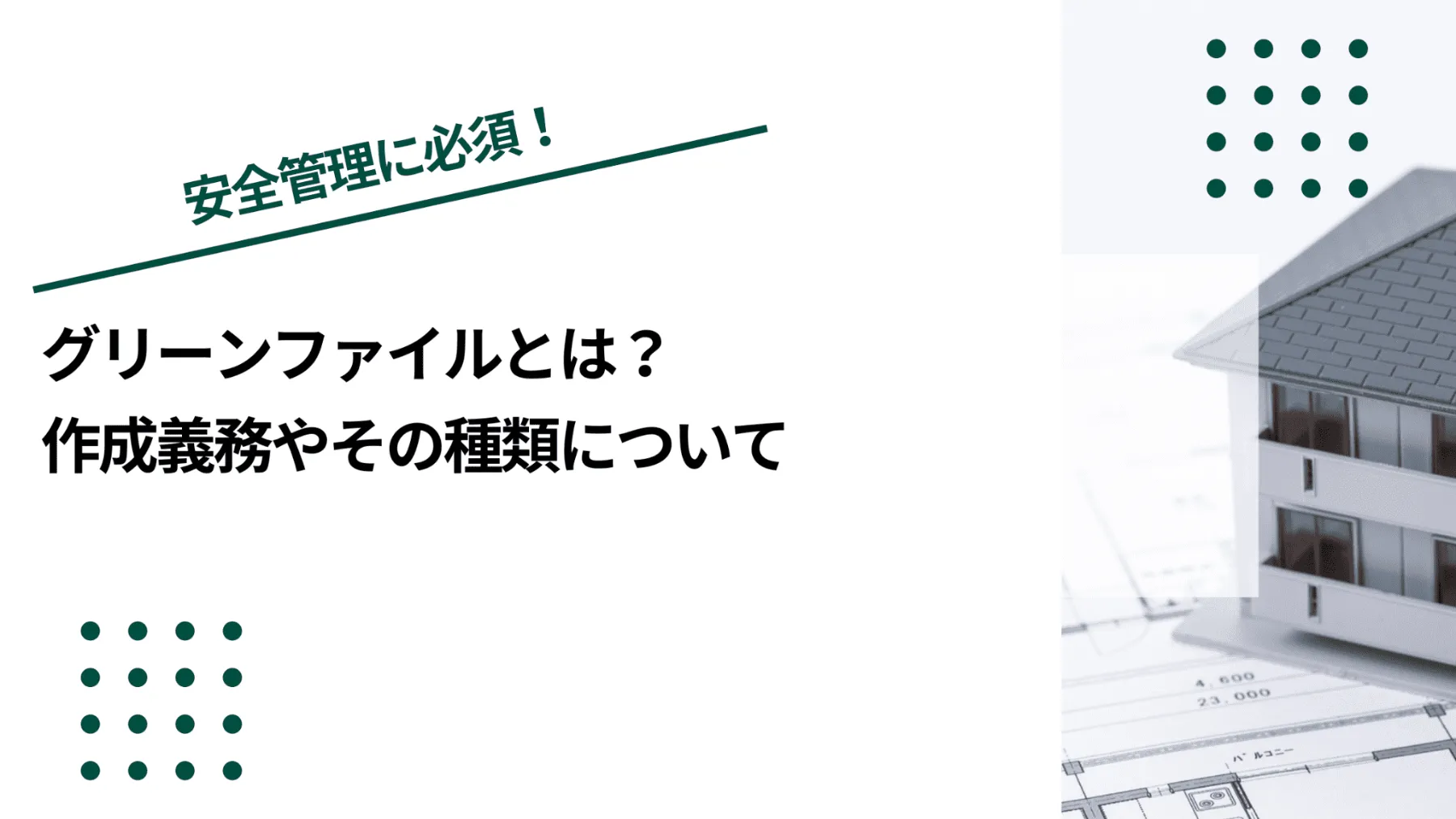
目次
建設現場における安全管理には「グリーンファイル」と呼ばれる安全書類が必要です。グリーンファイルという名称を聞いたことがない、聞いたことはあるが詳細はわからないという方のために、今回は、
- グリーンファイルの概要
- グリーンファイルの書式や作成義務
- グリーンファイル作成にあたっての課題
- グリーンサイトとの違い
- グリーンファイルの種類
これらについて解説します。
グリーンファイルとは

建設現場の安全確保と責任の所在を明確化するため、下請企業が元請企業に提出しなければならない労務安全書類の総称をグリーンファイルといいます。
グリーンファイルは建設現場の安全管理だけでなく、下請企業の工事内容や作業員体制の状況を元請企業が把握する目的で使用されるのも特徴です。また、安全管理体制を構築して事故防止に役立てることも、グリーンファイルの目的です。
ここでは、グリーンファイルの書式や作成義務、課題やグリーンサイトとの違いについても解説しています。
グリーンファイルの書式
グリーンファイルの書式は統一されておらず、事業者によって異なる場合が多いでしょう。なお、全国建設業協会によって定められた「全建統一様式」が一般的に利用されることもあります。
全建統一様式は、特に建築工事を担うゼネコンなどが、土木や建築施工関係の安全書類作成に際して用いる共通の書式であり、元請けから下請けまでの事務作業を軽減し、労務安全書類をより充実させることを目的としています。そのため、中小の建設事業者から大手ゼネコンまで、全国的に広く採用されているのが特徴です。
グリーンファイルの作成義務
建設業法に基づき、建設業者には建設現場の安全管理を目的としたグリーンファイルの作成および保管が義務づけられています。グリーンファイルは、工事着工前に準備のうえ、現場に関するさまざまな情報を記録します。
工事が進行中に内容に変更があった場合は、都度、更新された書類を作成し提出しなければなりません。また、グリーンファイルは原則として5年間の保管が求められており、これにより安全管理の徹底が図られています。
グリーンファイルの作成に関する課題
グリーンファイル作成において課題になるのが、項目数の多さによる誤入力の発生です。二重入力が必要な項目もあるため、誤入力が発生しやすいのです。
またグリーンファイルには統一のフォーマットがないため、内容・書き方にばらつきが出やすい傾向にあります。更新作業に手間がかかり、作成担当者の業務負荷が増えがちになるのも課題です。
加えて、過去の書類が管理できていなかったりするなど、効率化が図れていない場合もあるでしょう。
これらの課題を解決する対策には、入力用ツールの導入や関係者間での情報共有の強化、事業所内で使用するフォーマットの設定などが挙げられるでしょう。
グリーンファイルとグリーンサイトの違い
グリーンファイルと混在しやすい言葉に「グリーンサイト」があります。グリーンサイトとは、労務や安全衛生に関連するグリーンファイルを、作成・提出するシステムのことです。
紙ベースかつ手書きで作成することも多いグリーンファイルに対し、グリーンサイトは電子データでの作成となります。提出や情報共有なども電子データで完結できるので、作業効率化を図りやすいのもグリーンサイトの特徴です。
ただし、電子データでの作成となるため、システムの導入に費用や時間がかかることも覚えておきましょう。
【労務安全書類編】グリーンファイルの種類

ここでは、労務安全書類に該当する、以下のグリーンファイルについて解説します。
- 工事安全衛生計画書
- 持込機械等使用届
- 火気使用届
- 工事・通勤用車両届
- 安全ミーティング報告書
- 有機溶剤・特定化学物質等持込使用届
- 新規入場時等教育実施報告書
工事安全衛生計画書
危険を伴う工事現場にて、より安全に作業を進めるための書類を工事安全衛生計画書といいます。作成自体に法的な義務はないものの、元請会社から提出を求められる場合が多いでしょう。
工事安全衛生計画書に関する詳細は、当サイトで掲載している以下の記事を参考にしてください。
工事安全衛生計画書とは?項目ごとの記入例や作成義務について解説
持込機械等使用届
建設現場に機械を持ち込む際、作成しなければならない書類です。使用する機械が安全に使用できることを、宣言するために活用します。なお持込機械等使用届は、電気工具・電気溶接機などを持ち込む際に作成するものと、移動式クレーン・車両建設機械などを持ち込む際に作成するものの2種類があります。
火気使用届
建設現場で火器を使用する際は、火気使用届を提出しなければなりません。どのような火器を使用するか、火器をどう管理するのかを詳細に記載します。火器が原因の事故を防止するために重要な役割を果たすのです。
工事・通勤用車両届
建設現場に入る工事車両を管理するために、工事・通勤用車両届が必要です。トラックや生コン車など、建設現場を行き交う車両を対象に作成します。工事・通勤車両に関連する事故や渋滞を防ぐため、車両の搬出入時間を割り振る目的で作成されるのが工事・通勤用車両届の特徴です。
安全ミーティング報告書
建設現場で発生すると考えられる危険を洗い出したうえ、対策について記載した書類のことです。事故発生時はもちろん、事故を発生させないために、安全管理における不備がないか証明するために役立ちます。
有機溶剤・特定化学物質等持込使用届
有機溶剤・特定化学物質など、いわゆる「危険物」を持ち込む際に必要な書類です。危険物を使用する日程や材料名を記載し、元請け業者から許可を得るために使用します。
新規入場時等教育実施報告書
建設現場に、新たな人材が入る場合は新規入場時等教育実施報告書が必要です。新たに建設現場へ入る人材が、安全衛生教育を受けており、かつ現場のルールを理解しているか証明するための書類として使用されます。
【施工体制台帳編】グリーンファイルの種類

ここでは、施工体制台帳に該当する、以下のグリーンファイルについて解説しています。
- 下請負業者編成表
- 再下請負通知書
- 作業員名簿
- 外国人建設就労者現場入場届出書
- 年齢にまつわる就労報告書
- 施工体制台帳
下請負業者編成表
下請負業者編成表とは、工事に関わる企業名と工事の内容、現場の責任者名などが明記されている書類のことです。一次下請会社から二次下請会社だけでなく、さらにそれ以下の下請け会社まで、どのような流れで契約が進んでいくのかを記載します。
なお、下請負業者編成表を作成するのはあくまで一次下請会社であり、それ以下の企業が作成することはありません。
再下請負通知書
一次下請会社以下の下請契約に関する内容を、元請会社に報告するための書類を再下請負通知書といいます。
工事に関わるすべての下請け会社を、元請け会社が把握するために作成するのが再下請負通知書の目的です。
建設工事は下請け・孫請けと、下請けの範囲が拡大傾向にあります。そのため再下請負通知書がないと、元請け会社が工事の全容を把握しきれず、安全管理や進捗・品質管理にも問題が生じてしまうのです。
作業員名簿
作業員名簿とは、建設現場に関わる作業員の情報について記載された書類のことです。建設現場で、誰がどのような作業をしているのか把握するうえで役立ちます。また、社会保障の加入状況や健康診断の結果、資格・免許に関する情報が記載されているのも特徴です。
作業名簿に関しては、以下の記事でも解説しているのであわせて参考にしてください。
作業員名簿の書き方を無料のエクセルテンプレートをもとに解説!
外国人建設就労者現場入場届出書
外国人の就労者が建設現場に参加する場合は、外国人建設就労者現場入場届出書が必要です。建設現場に参加する外国人の情報や、外国人の就労者を受け入れる体制が整っているか確認するために活用されます。
年齢にまつわる就労報告書
建設現場に、60歳以上または65歳以上の人材が参加する場合は、自社責任での就労となる旨を報告する「高齢者就労報告書」の作成が必要です。
満18歳以下の人材が作業に参加する場合には、同じく自社責任で就労させることを報告するために「年少者就労報告書」を作成しなければなりません。
施工体制台帳
下請け・元請けを問わず、建設現場に関わるすべての企業の情報や関係性をまとめた書類です。各業者が担う施工範囲や技術者の名称、社旗保険の加入状況などを記載します。施工における安全確保や、建設業法の違反防止目的で作成される書類です。
なお、一次事業者に対して元請け業者が作成する「施工体制台帳作成通知書」という書類があることもあわせて覚えておきましょう。
まとめ
建設現場において、安全確保や責任の所在確認といった視点から、グリーンファイルの作成が必要とされています。グリーンファイルには労務安全書類と施工体制台帳に関する書類の2種類に大別され、それぞれ作成目的が異なることを覚えておきましょう。
また今回紹介したグリーンファイル以外にも、その他の安全書類が必要になることもあります。
労働基準監督署提出書類報告書 | 労務・安全衛生管理事項引受確約 | 安全帯使用に関する確約書 | 脚立の単独使用に関する確約書 | 職長教育修了証貼付台紙 | 有資格者一覧 |
労働基準監督署に対し、必要な書類対応が完了したことを報告する書類 | 元請け企業の指示に従い業務を遂行することを約束する書類 | 高所作業時に安全帯の使用を約束する書類 | 現場の人材に脚立の使い方を正しく指導したうえで使用することを約束する書類 | 職長教育の修了を証明するための書類 | 作業現場に入る人材の保有資格を工種別にまとめた書類 |
これらの安全書類に関する予備知識も踏まえ、グリーンファイルについての知識を身につけましょう。
