【2024年版】建設業の労災保険料率|計算方法や変更点も解説
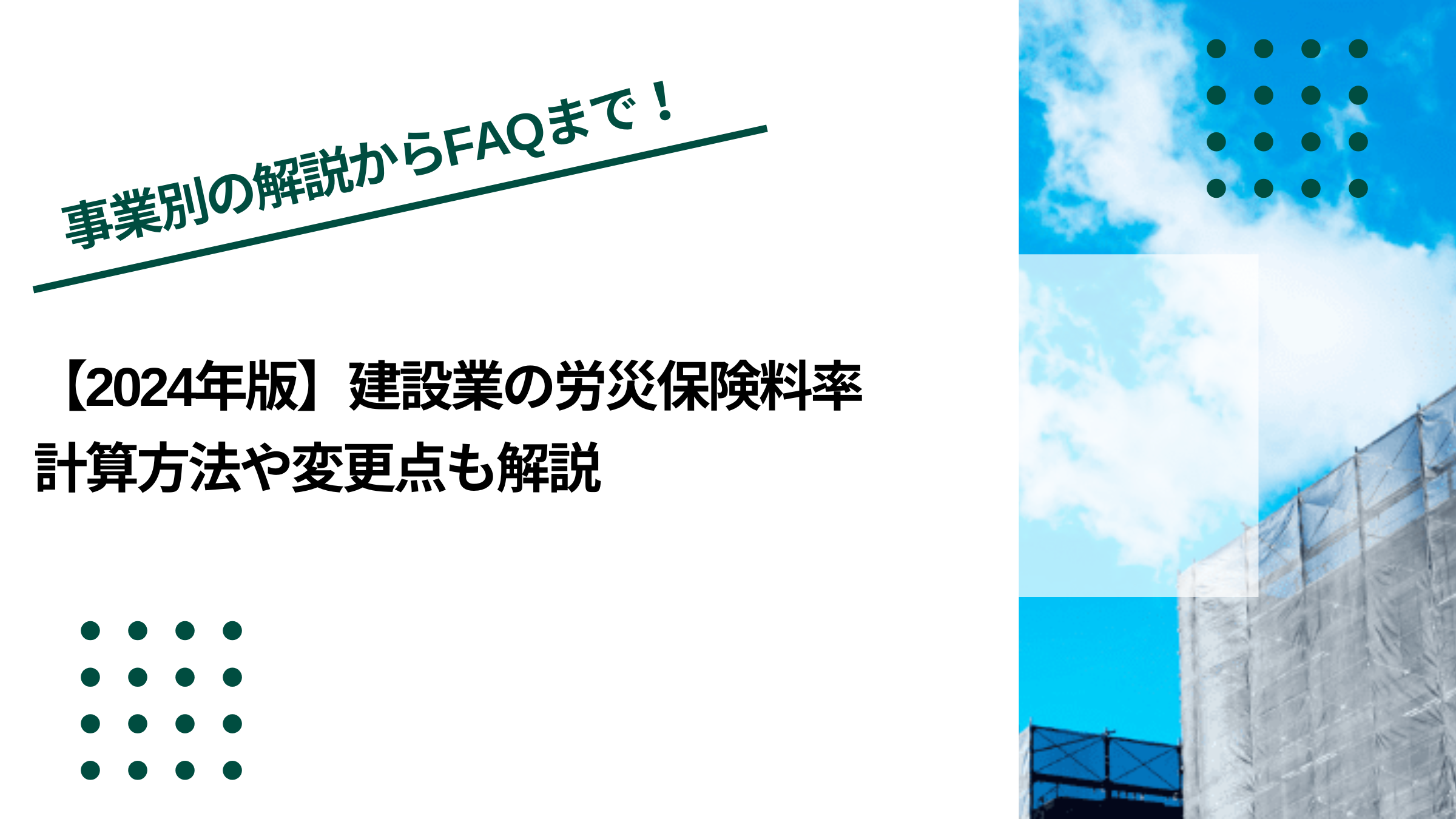
目次
建設業界は、労働災害のリスクが非常に高い業種として広く認知されています。事業運営者にとって、労災保険料率は経営における重要な指標のひとつであり、動向を正確に把握することが重視されるのです。本記事では建設業の労災保険料率について、以下の視点から解説します。
- 建設業の労災保険料率における概要や目的、算定方法
- 建設業における労災保険料率の分類
- 2024年度(令和6年度)からの労災保険料率の変更点
さらに、建設業の労災保険料率に関するよくある質問にも回答しているので、労災保険料率への理解を深め、適切な対応策を講じるための実用的な情報としてご活用ください。
建設業における労災保険料率とは

ここでは、建設業における労災保険料率について、以下の視点から解説します。
- 概要
- 目的
- 算定方法
建設業における労災保険料率は、労働者保護の観点から重要な要素となります。
労災保険料率の概要
労災保険料率とは、労働者の総賃金に一定の割合を掛けた金額であり、事業の種類に応じて異なる料率が設定されています。建設業は高い災害リスクを伴うため、他業種に比べて料率が高めに設定されています。なぜなら、災害発生時の補償や労働者の社会復帰を促進するため、保険制度が十分な資金を必要とするためです。
労災保険料率の目的
労災保険料率の目的は、万が一労働災害が発生した際に、労働者を保護するための費用を確保することです。具体的には、保険給付や社会復帰支援に必要な費用をまかなうための仕組みです。さらに、企業は労働基準法で定められた災害補償の義務を、保険給付の範囲内で免除されるというメリットもあります。
労災保険料率の算定方法
労災保険料は、労働者の賃金総額に料率を掛けて算出するのが一般的です。ただし、建設業においては、賃金総額の把握が難しいケースもあるため、特例として元請け金額に労務費率を掛けて計算する方法が用いられます。労務費率は業種ごとに異なり、17%から38%の範囲で設定されています。
建設業における労災保険料率の分類

建設業における労災保険料率は、事業の種類によって細かく分類されています。建設業の中でも、仕事内容や作業環境によって、労働災害のリスクが異なるためです。
ここでは、建設業における労災保険料率について、以下の事業別に解説します。
- 水力発電施設・ずい道等新設事業
- 道路新設事業
- 舗装工事業
- 鉄道または軌道新設事業
- 建築事業
- 既設建築物設備工事業
- 機械装置の組立てまたは据付けの事業
適切な料率を各事業に適用することで、労働者への補償を手厚くする一方、事業主の負担を公正に分配することが可能になります。
水力発電施設・ずい道等新設事業
水力発電施設やずい道の新設に関わる工事は、規模が大きく、かつ高所作業を伴うケースが多いため、特に高い労働災害のリスクが指摘されています。2024年度(令和6年度)は、労災保険料率が1,000分の34に設定されています。
道路新設事業
道路新設工事は、重機や車両が頻繁に往来するため、土砂崩れの危険性があり、労災リスクが高くなりがちです。2024年度の労災保険料率は1,000分の11で、前年度と同じ水準を維持しています。
舗装工事業
舗装工事は、道路新設事業と比べて作業範囲が限られており、重機の使用頻度も少ない傾向にあります。そのため労災リスクは比較的低く、2024年度の労災保険料率は1,000分の9に設定され、前年からの変更はありません。
鉄道または軌道新設事業
鉄道や軌道の新設工事では、線路の敷設や電気工事など、高度な専門知識を要する作業が含まれるため、労働災害リスクが重視されています。2024年度の労災保険料率は1,000分の9で、昨年度から変更はありませんでした。
建築事業
建築事業では、新築や増改築の作業を通じて高所作業や重量物の運搬が伴うため、複数のリスク要因が存在します。2024年度の労災保険料率は1,000分の9.5となり、前年度から据え置きとなっています。
既設建築物設備工事業
既存建物への設備工事は、建築事業と比べて作業範囲が限定され、リスクも比較的軽減されます。2024年度の労災保険料率は1,000分の12に据え置かれ、昨年度と同じ水準を保っています。
機械装置の組立てまたは据付けの事業
工場やプラントでの機械装置の設置作業は、重量物の扱いを伴うため一定のリスクがあります。2024年度の労災保険料率は1,000分の6.5に設定されており、前年度の1,000分の6からわずかに引き上げられています。
2024年度(令和6年度)からの労災保険料率の変更点
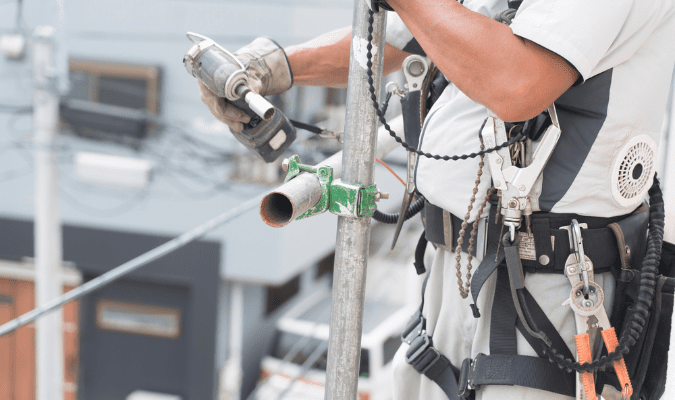
2024年度(令和6年度)の労災保険料率には、労働災害の発生状況や経済情勢の変化を踏まえた見直しが行われています。事業主にとって負担額へ直接的な影響があるため、改定内容を正確に把握することが求められるでしょう。
全体的な傾向
2024年度の労災保険料率改定では、全体として保険料率が引き下げられています。労働災害の件数が減少傾向にあることに加え、労災保険特別会計の財務状況も改善されていることが要因です。
建設業における変更点
建設業においても、いくつかの業種で労災保険料率が引き下げられています。いくつかの例をみてみましょう。
- 水力発電施設・ずい道等新設事業:1,000分の62から1,000分の34へ大幅に低下
- 採石業:1,000分の49から1,000分の37に引き下げ
一方、いくつかの分野では保険料率が上昇しています。
- 機械装置の組立・据付事業:1,000分の6から1,000分の6.5に引き上げ
- 鉄道および軌道新設事業:労務費率が19%から24%へ増加
- その他の建設事業:労務費率が23%から24%に上昇
第2種特別加入保険料率の変更点
特別加入制度を活用する事業主に対しても、改定された保険料率が適用されます。第2種特別加入保険料率は業種を問わず一律1,000分の8に設定され、前年の1,000分の8.5から引き下げられました。
年度更新時の注意点
2024年度の労災保険料率の変更に伴い、年度更新の際には改定後の料率で手続きを進める必要があります。毎年6月1日から7月10日の期間に行われる年度更新では、前年度の賃金総額に基づき概算で納付を行い、更新時に精算を実施する仕組みとなっています。事業主にとって、改定内容の確認と適切な手続きが求められる場面と言えるでしょう。
労災保険料率に関するよくある質問

ここでは、労災保険料率に関するよくある質問に回答します。
- 労災保険料は誰が負担する?
- 労災保険料率の変更はいつ?
- 労災保険料率に関する相談はどこでする?
上記の回答を踏まえて、建設業における労災保険料率の理解度を深めましょう。
労災保険料は誰が負担する?
労災保険料は、全額を事業主が負担します。労働者からの徴収はありません。労働者の安全と保障を目的とする、労災保険制度の基本方針に基づいています。業種ごとに異なる料率が定められており、賃金の総額にその料率を掛け合わせて保険料が算出されます。
労災保険料率の変更はいつ?
労災保険料率は原則として毎年見直され、必要に応じて調整が行われます。新しい料率は年度の開始に合わせて4月1日から適用されますが、実際の申告・納付は年度ごとの手続きに従って進められます。そのため、新料率の実施は、6月1日から7月10日までの年度更新手続きで正式に反映されることを覚えておきましょう。
労災保険料率に関する相談はどこでする?
労災保険に関する相談は、厚生労働省や各都道府県の労働局で対応しています。厚生労働省の公式サイトには、労災保険についての詳細な情報が掲載されています。また、労働局では電話や窓口での相談も可能なため、質問がある場合は直接問い合わせると安心です。
まとめ
本記事では、建設業における労災保険料率の概要と、今後の変更点について詳しく説明しました。
労災保険料率は事業の種類やリスクレベルに基づいて分類され、事業ごとに異なる料率が適用されます。2024年度には、全体的な料率の引き下げが予測されていますが、一部の業種や加入区分においては個別の変更点に留意しなければなりません。
保険料率の動向をしっかり把握し、適切な対策を講じることで、経営の安定性を高めることが可能になるでしょう。
