建設業の組合とはなにか?重要性や役割、育成・品質保証との関係性
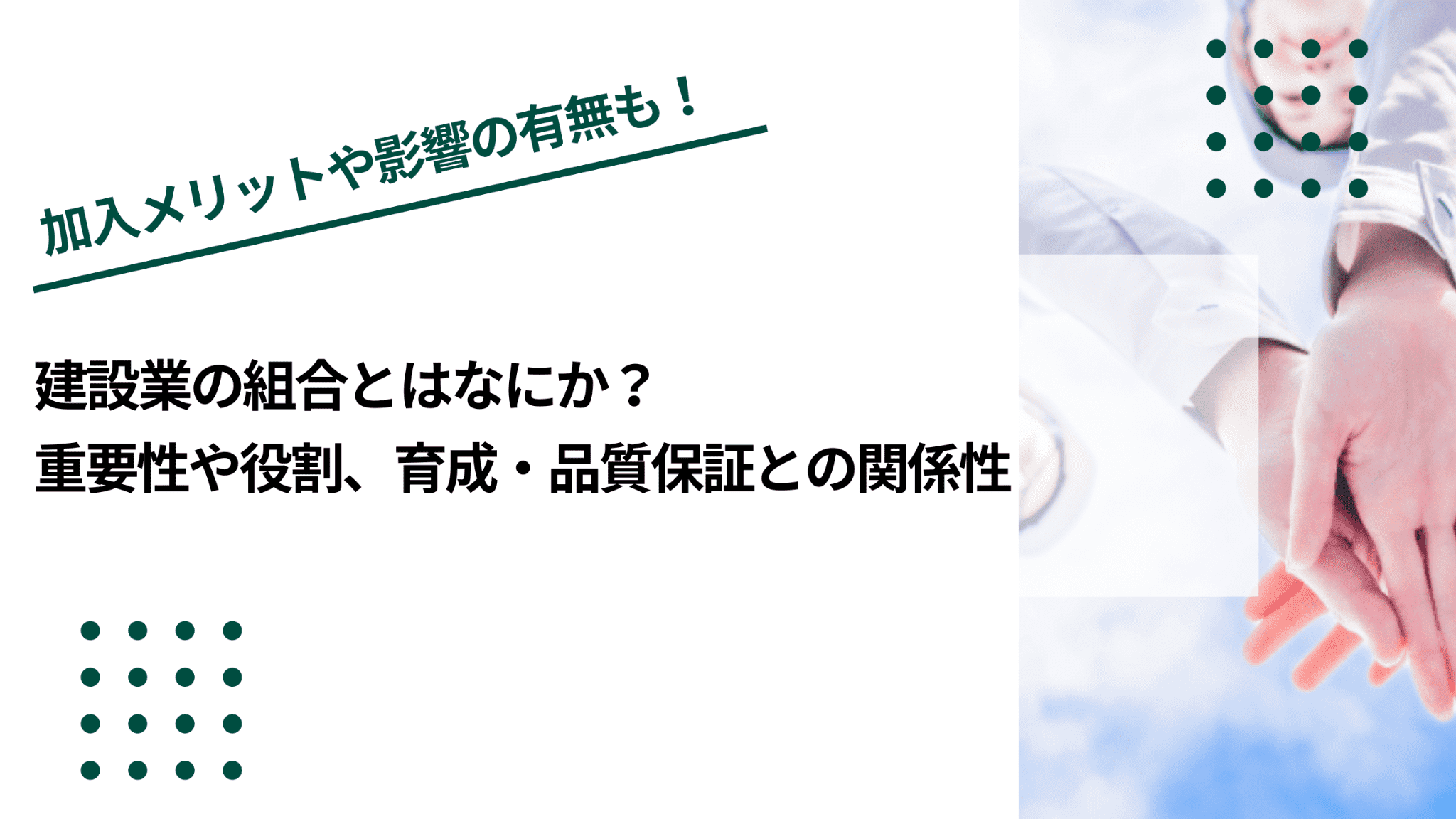
目次
昨今、建設業界は深刻な人手不足や技術の急速な進展に直面しており、経営の安定や事業の成長を図るうえで「組合」への参加が重要視されています。本記事では、建設業における組合について、以下の観点から詳しく解説します。
- 建設業の組合に加入するメリット
- 経常JVとの違い
- 建設業組合の種類
- 建設業における組合の重要性・役割
- 建設業の組合と関連する要素
組合への加入を検討している、もしくは組合についてさらに深く知りたい建設業者の方は、ぜひ参考にしてください。
建設業における「組合」とは?

建設業における「組合」とは、中小の建設業者業が抱える経営上の問題を共同で解決し、経済的地位の向上を図るための組織です。ここでは建設業の組合について、加入するメリットや経常JVとの違いといった視点から解説します。
建設業の組合に加入するメリット
建設業組合に加入すると、組合員はさまざまなメリットを享受できます。まず、組合は共同事業を通じて、経営の効率化や取引条件の改善をサポートします。
組合員が単独では難しい大規模なプロジェクトや、より有利な条件での取引を実現するチャンスを得られるでしょう。
また、社会保障や福利厚生の面でも「建設連合国民健康保険」や「一人親方労災保険」など、組合員専用の保険制度が整備されており、安心して業務に専念できる環境が整っています。
さらに、行政からの支援も充実しており、金融面では低金利の融資や信用保証制度を利用でき、税制面での優遇措置を受けられます。これらは、組合が中小企業の経営基盤強化に貢献しているという認識に基づく支援です。
加えて、国土交通省は公共工事の入札資格審査において、組合員に対して特例措置を設け、受注機会の拡大を後押ししています。
経常JVとの違い
経常JVと組合の主な違いは、行政庁の認可が必要かどうかです。組合は、設立や解散の際に行政庁の認可を受けなければなりません。しかし経常JVは、構成員同士の契約によって設立・解散が自由に行えます。
また、組合は事業協同組合の場合、共同受注に加え、組合員のためにさまざまな共同事業を展開します。さらに組合は結成後、解散決議がなければ存続し続けますが、経常JVは競争参加資格の有効期間が存続期間となるのが基本です。
経常JVは中小・中堅建設業者が持続的な協力関係を確立し、経営力や施工力を高めることを目指す共同企業体です。一方、組合は、中小企業者が直面する経営課題を共に解決し、経済的な地位を向上させることを目的とした組織である点にも違いがあります。
建設業組合の種類

建設業組合には、事業協同組合と協業組合の2種類があります。それぞれの特徴や組合資格、設立要件についてみていきましょう。
事業協同組合
事業協同組合は、中小企業等協同組合法に基づき、中小企業者が協力して事業を展開し、経営の効率化や取引条件の改善を目指す組織です。
組合資格は、組合の地区内に所在する小規模事業者で、組合の定款に記載された事業を営む者に限られます。建設業者だけでなく、以下に挙げる業種の事業者が組合員として参加できます。
- 商業
- 工業
- 鉱業
- 運送業
- サービス業など
設立要件としては、組合員候補となる者4名以上が発起人となり、設立総会を開催するなどの手続きを踏まなければなりません。さらに、定款に定められた組合員の行う事業について、所管する行政庁の認可を受ける必要があります。
協業組合
協業組合は、中小企業団体に関する法律に基づき協力し合い、企業規模の適正化や生産性の向上を効果的に推進し、共同利益の拡大を目的とした組織です。
組合に加入できるのは、中小企業者および定款で定められた中小企業者以外の者で、加入時に定款で規定された事業の全部または一部を営む者に限られます。ただし、中小企業者以外の者は、協業組合の総組合員の4分の1を超えてはなりません。
設立には、組合員候補となる4名以上の発起人が必要で、設立総会の開催など一定の手続きが必要です。また、協業組合が行う事業については、所管する行政庁の認可を取得しなければなりません。
事業協同組合と協業組合の違い
事業協同組合と協業組合は、どちらも中小企業が連携することで経営基盤を強化することを目的としていますが、目的や組織形態には違いがあります。
事業協同組合は「中小企業等協同組合法」に基づき、中小企業者が共同で事業を行い、経営の効率化や取引条件の改善を図ることを目指す組織です。組合員には建設業者だけでなく、多様な業種の事業者が参加できます。
一方、協業組合は「中小企業団体の組織に関する法律」に基づいており、組合員の事業活動を協力して行うことで、企業規模の適正化や生産性の向上を実現することを目指します。協業組合は、組合員が事業の全部または一部を共同で運営する点が大きな特徴です。
さらに、両者の違いとして、事業協同組合は組合と組合員が並立する関係ですが、協業組合はより密接な結びつきを持つ組織体となっています。
建設業における組合の重要性・役割

建設業において組合は、中小企業者が抱える経営課題を解決し、厳しい競争を勝ち抜くために欠かせない役割を果たしています。
特に事業協同組合は、共同事業を通じて経営の効率化や取引条件の改善を図り、組合員の事業活動を支援します。例えば、共同購買による資材調達コストの削減、共同受注による仕事の獲得機会の増加、共同保証を通じた信用力の強化が期待できるでしょう。
さらに、組合は社会保障や福利厚生の充実にも大きく寄与しているのです。建設連合国民健康保険や一人親方労災保険などを通じて、組合員が安心して働ける環境を提供し、生活の安定を支えています。
また、組合は行政からの支援も受けており、金融面では低金利融資や信用保証制度を活用でき、税制面でも優遇措置が適用されます。さらに、国土交通省は公共工事の入札資格審査において組合員に対して有利な特例措置を設けており、受注機会の拡大を後押ししているのも特徴です。
建設業の組合と関連するさまざまな要素
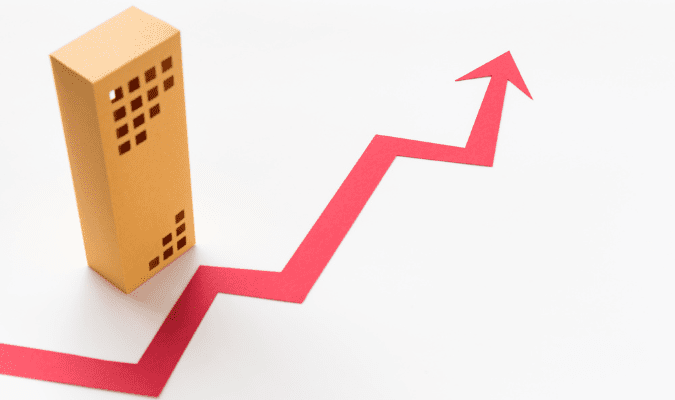
ここでは、建設業の組合と関連する以下の要素について解説します。
- 専門工事業の地位向上
- 人材育成
- 品質保証
- 情報化
- 改修工事の増加
上記要素と組合の関連性を、加入すべきか否か判断するうえでの参考情報としてください。
専門工事業の地位向上
建設工事は、多くの専門工事業者が連携して完成させます。しかし、重要な役割を担いながらも、発注者や元請け企業から十分な信頼を得られていない工事業種もあるのです。専門工事業の地位向上には、実務書や共通仕様書の整備、そして技能者の施工能力のバラつきをなくしていくことが求められます。
組合、特に事業協同組合や連合会は、こうした課題解決に貢献できます。組合を通じて実務書や技術に関する教科書を作成し、統一的な基準で技能者を育成することで、専門工事業の信頼性向上を図ることが可能です。
人材育成
建設業は機械化が進んでも人の手による作業が不可欠な業界です。そのため、高い技能と臨機応変な判断力を持つ人材の育成が重要となります。組合の存在は、研修会や講習会を通じて、組合員企業の人材育成を支援する要素です。
組合の財務力やノウハウを活用することで、個々の企業では難しい充実した研修プログラムを提供することが可能です。また、大学や研究機関との連携により、最新技術や情報を提供する組合もあります。
品質保証
建設業の組合は、品質保証の面でも重要な役割を果たします。建設生産物は多くの専門工事業者が関わるため、各部分の安全性や確実性を担保しなければなりません。組合は、品質管理の重要性を組合員に認識させ、啓発する効果的な組織として機能します。個々の中小企業では困難な品質管理体制の構築や、ユーザーへの説明方法の改善などを、組合を通じて実現できます。結果として、最終ユーザーの安心感を高めることにつながるでしょう。
情報化
建設業界においても、設計や製図のコンピュータ化、各種手続きの電子化など、情報化が急速に進んでいます。組合は、組合員企業の情報化を支援するため、OA機器の導入支援や操作講習会などを実施しているのです。
また、業界全体の情報共有を促進するために、独自の情報ネットワークを構築している組合も存在します。組合を通じて最新の情報技術や業界動向を共有することで、組合員企業の競争力強化を図ることが可能です。
改修工事の増加
近年、新築工事だけでなく、既存の建物を長持ちさせるための改修工事も増加しています。改修工事は、多様な専門工事業者が連携する必要があるため、組合の役割は重要です。
組合は、異業種間の連携を促進し、共同受注や技術交流を支援することで、組合員企業が改修工事市場で優位性を築けるようサポートします。また、改修工事に関する最新技術や法規制などの情報を提供することで、円滑な事業遂行も支援します。
まとめ
建設業界において、組合は業界全体の発展と個々の事業者の成長を支える重要な存在です。事業協同組合や協業組合など、さまざまな種類の組合があり、それぞれが独自の役割を担っています。
組合は専門工事業者の社会的地位の向上や人材育成、品質の向上や情報技術の導入など、多岐にわたる分野で建設業界に貢献しており、影響は大きいと判断できるでしょう。
組合に加入することは、建設事業者にとって多くのメリットをもたらすだけでなく、業界全体の発展にも寄与します。組合の役割と意義を理解し、積極的に活用することは、自社の成長はもちろん、業界全体の進歩につながるものです。
業界全体の底上げを目指すうえで、組合の存在は見逃せないでしょう。
