建設業の技能実習生とは?受け入れのメリット・デメリットや安全性確保の施策
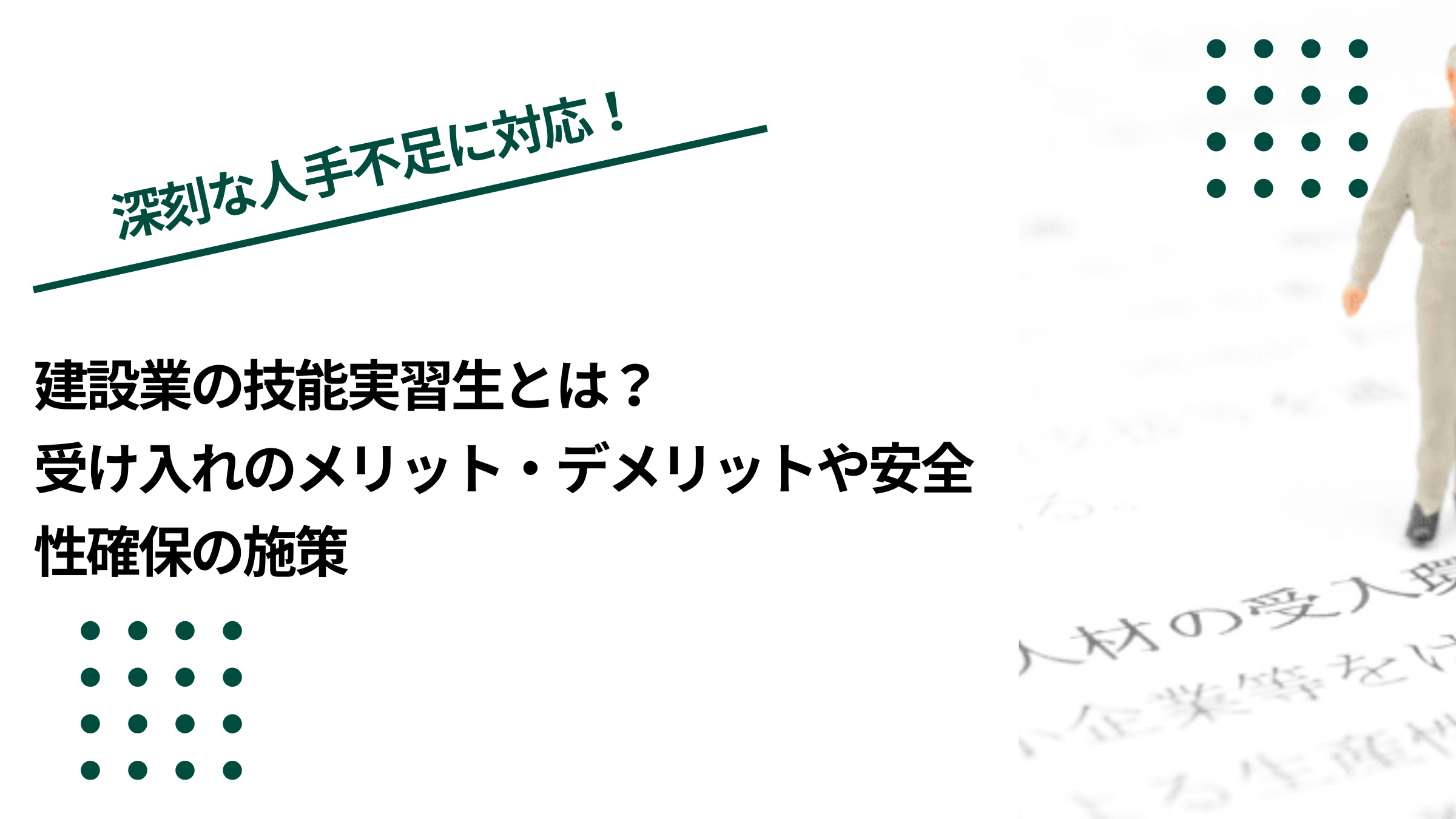
目次
建設業界は深刻な人手不足に直面しており、解決策として技能実習生の活用が注目されています。
本記事では、建設業における技能実習生について、以下のポイントから詳しく解説します。
- 建設業における技能実習生の概要
- 技能実習生と受け入れ側の要件
- 技能実習生を受け入れられる建設業の職種
- 建設業の技能実習制度について
- 建設業者が技能実習生を受け入れるメリット・デメリット
- 技能実習生の安全性を確保するための視点
技能実習生制度は外国人労働者に日本の技術や技能を学ぶ場を提供する一方で、人材不足に悩む建設業者にとっても重要な採用手段です。
しかし、人材の確保だけでなく、実習生の安全管理や教育、円滑なコミュニケーションなど、総合的な視点での取り組みも重視されているのです。
建設業における「技能実習生」とは

建設業界では人手不足が深刻化しており、技能実習生の受け入れを検討する企業が増えています。
しかし、技能実習生を受け入れるためには、実習生と企業の双方が満たすべき要件があることを覚えておきましょう。
技能実習生の要件
技能実習生になるためには、以下の要件をクリアする必要があります。
- 単純作業ではなく専門的な技能を習得することが目的である
- 年齢が18歳以上である
- 帰国後に日本で学んだ技能を活かした職業に就く予定がある
また、母国で習得が難しい技術であることや、送出国の公的機関から推薦を受けていることも重要です。
さらに、日本で実習予定の業務と同じような職歴があることが望まれます。団体監理型の場合は、技能実習に参加する特別な理由が必要となります。
受け入れ側の要件
企業が技能実習生を受け入れるための要件は、以下のとおりです。
- 技能実習法などの関連法令を遵守している
- 暴力団との関係がない
- 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を適切に配置する
また、実習生の住居を提供することも求められます。
住居については、一人当たり4.5㎡以上のプライベートスペースを確保しなければなりません。
さらに、日本人と同等以上の給与を支給し、社会保険に加入させること、帳簿を作成・保管することも義務付けられています。
団体監理型の場合は、適切な監理団体への加入も必須です。
加えて、建設業特有の要件として、建設キャリアアップシステムへの登録や月給制の導入など、技能実習生の失踪防止に関する基準も設けられています。
技能実習生を受け入れられる建設業の職種
建設業界では、22の職種と33の作業分野において、技能実習生の受け入れが可能です。
それぞれの職種ごとに、具体的な作業内容が明確に定められています。
実習生の業務は「必須業務」「関連業務」「周辺業務」の3つに分類され、年間の実習時間に対する各業務の割合が規定されています。
また、すべての業務において、総実習時間の10%以上を「安全衛生業務」に充てることが必要です。
建設業の技能実習制度について

建設業界では、深刻な人手不足に対応するため、技能実習制度の活用が進んでいます。
なぜ建設業で技能実習制度が必要とされているのか、背景にあるいくつかの要因についてみていきましょう。
制度導入の背景
建設業は工事ごとに勤務場所が変動するため、各現場での労務管理が求められます。
また、季節や受注状況により仕事量に波があり、報酬も変動しやすいという実情があります。
これらの状況から、技能実習生の適正な労働環境を確保することが課題となっていました。
さらに、2019年4月から改正入管法に基づく新たな在留資格「特定技能」の運用が開始されました。
新制度の導入により、技能実習制度でも新たな制度との整合性を保ちながら、適切な運用が求められるようになったのです。
さまざまな背景を踏まえ、実習生の適正な労働環境の確保と特定技能制度との調和を図ることを目的に技能実習制度が導入されました。
建設業者が技能実習生を受け入れるメリット

建設業者が技能実習生を受け入れることによるメリットについて詳しく探ってみましょう。
採用の計画性が向上する
技能実習生の受け入れは、計画的な採用を可能にするというメリットがあります。
受け入れ企業が監理団体に求人票を提出してから、実習生が入社するまでには約6~7ヶ月の期間が必要です。
一般的な求人活動では採用までの期間が不透明で、計画的な人員配置が難しい場合があります。
しかし、技能実習制度では入社までのスケジュールが明確であるため、長期的な人材育成計画を立てやすくなります。
特定技能へ移行しやすくなる
技能実習制度は、特定技能への移行を視野に入れた人材育成手段としても効果的です。
2019年から運用が開始された特定技能制度は、技能実習2号を修了した実習生がさらに高度な技能を習得し、日本で長期的に就労できる道を開くものです。
技能実習生を受け入れることで、特定技能への移行を希望する優秀な人材を確保し、長期的な雇用関係を築くことが可能になります。
さらに、特定技能2号への移行も可能で、在留期間の上限がなくなることによる永続的な雇用も視野に入れられるでしょう。
人材確保がスムーズになる
技能実習制度は、人材不足に悩む建設業界にとって、重要な人材確保の手段ともなり得ます。
技能実習生は転職をせず、3年間または5年間(技能実習3号の場合、一時帰国を含む)継続して雇用することが可能です。
近年、若者の建設業界への就労意欲の低下や離職率の増加が課題となっています。
しかし、技能実習制度を活用することで安定した労働力を確保し、人材不足の解消に大きく貢献できます。
建設業者が把握すべき技能実習生受け入れのデメリット

技能実習生の受け入れは、人材不足の解消に有効な手段ですが、同時にいくつかのデメリットも存在します。
実務未経験のことが多い
技能実習生は入国前に母国で一定の技能教育を受けていますが、実際の現場での実務経験が不足している場合が多いでしょう。
建設作業は経験によって習得される技術や知識が多く、未経験者にとっては習得に時間がかかることもあります。
そのため、実務未経験の技能実習生を受け入れる際には、日本人の新人と同等の実務未経験者として認識し、丁寧な指導や教育体制を整えることが重要です。
安全に作業を行えるよう、基本的な作業手順から細やかに教え、段階的なスキルアップをサポートしましょう。
日本語力に乏しい人材がいる
技能実習生は入国前に日本語の研修を受けていることが多いものの、日本語能力には個人差があります。
そのため、コミュニケーションに課題を感じるケースも少なくありません。
建設現場では安全確保のために正確な指示や報告が不可欠ですが、日本語でのコミュニケーションが円滑でない場合、作業効率の低下や安全上のリスクにつながる可能性があります。
受け入れ前に日本語能力を十分に評価し、必要に応じて日本語研修を実施するなど、円滑なコミュニケーションを図るための対策が重要です。
作業内容の制限がある
技能実習制度では、実習生が従事できる作業内容が職種ごとに明確に定められています。
建設業では多岐にわたる作業が発生しますが、技能実習生に任せられる作業は限定されるため、作業分担や人員配置に工夫が必要になるかもしれません。
また、実習計画に沿った作業内容でなければ法令違反となるリスクもあります。
受け入れ前に技能実習計画の内容をしっかりと確認し、実習生が適切な作業に従事できるよう計画を策定することが不可欠です。
技能実習生の安全性を確保するために

技能実習生は、日本の労働安全衛生法によって保護される労働者です。
しかし、文化や言語、生活習慣の違いから、安全管理には特別な注意が求められます。
実習生の安全を守るために、以下のポイントに留意しましょう。
参照:厚生労働省|技能実習生が建設作業を安全に行うための第一歩
言語の壁を乗り越えた安全教育の徹底
技能実習生にとって、日本語でのコミュニケーションがハードルとなることがあります。
安全教育や作業指示は、実習生が理解できる言語と方法で伝えましょう。
図解や実演を活用し、視覚的に理解を促す工夫が効果的です。
特に、危険を知らせる日本語や基本的な合図は確実に習得させましょう。
また、定期的に理解度をチェックし、疑問点があればすぐに解消できる体制を整えることが重要です。
実習生の健康状態を把握したうえでの労働環境構築
法定の健康診断の実施はもちろん、日常生活での健康状態や悩みにも気を配り、適切なサポートを提供しましょう。
特に、来日して間もない実習生は、日本の気候や生活習慣に慣れていない場合が多く、体調管理に注意が必要です。
熱中症対策やバランスの取れた食事、十分な睡眠時間の確保など、健康的な生活を送れるよう支援体制を整えることが大切です。
密なコミュニケーションによる孤立の防止
技能実習生が安心して働ける環境を作るために、職場でのコミュニケーションを重視し、孤立を防ぎましょう。
日本人スタッフとペアを組ませたり、定期的なミーティングや意見交換会を開催したりするなど、積極的に交流の機会を設けることが効果的です。
また、実習生の出身国や文化への理解を深め、お互いに尊重し合える職場環境を築くことも重要です。
まとめ
技能実習生の受け入れは、建設業界における重要な人材戦略です。
労働力の確保だけに目を向けるのではなく、技能実習生の安全と成長を支える環境づくりが不可欠となっています。
言語の壁を乗り越え、適切な安全教育や労働環境の整備、密接なコミュニケーションを通じて、実習生の定着と技能向上を支援することが求められます。
また、将来的には特定技能への移行を視野に入れ、長期的な人材育成の観点から技能実習生を位置づけることが、建設業の持続可能な発展につながるでしょう。
