【2024年版】建設業の利益率ランキング|推移や現状、向上につながる戦略
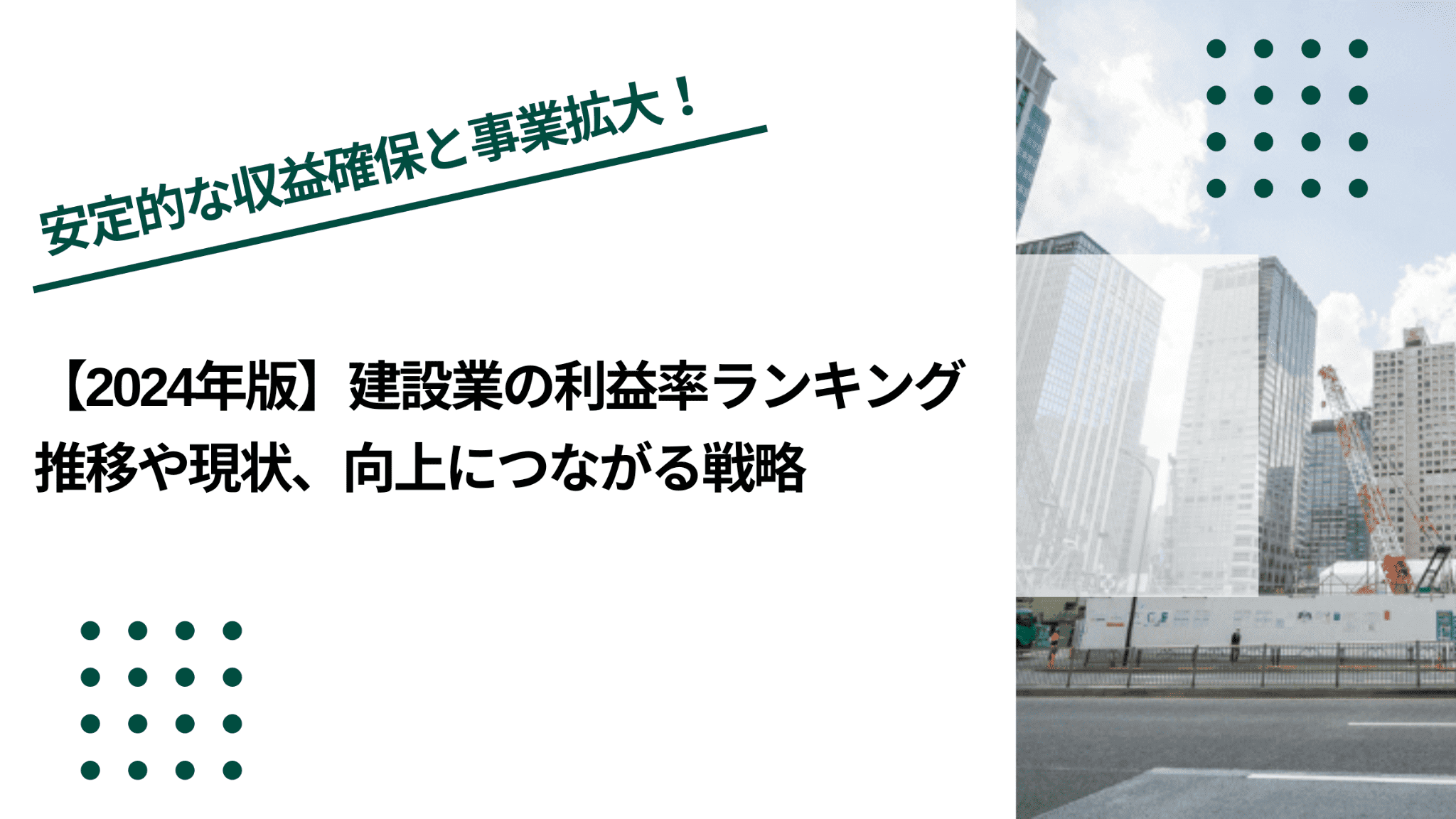
目次
建設業界では、利益率が企業の安定性や競争力を判断するうえで欠かせない指標として重視されています。しかし、近年は建設需要の変動、慢性的な人手不足、さらには資材価格の高騰といったさまざまな要因が利益率に影響を及ぼしている状況です。
本記事では、建設業の利益率に焦点を当て、最新ランキングを交えつつ、以下のテーマについて詳しく解説していきます。
- 建設業における利益率の概要や重要性
- 建設業で注目すべき利益率の種類
- 建設業における利益率の推移と現状
- 建設業の利益率向上のための戦略
本記事で解説する内容が、企業経営に役立つ実践的なヒントとなれば幸いです。
建設業における利益率とは
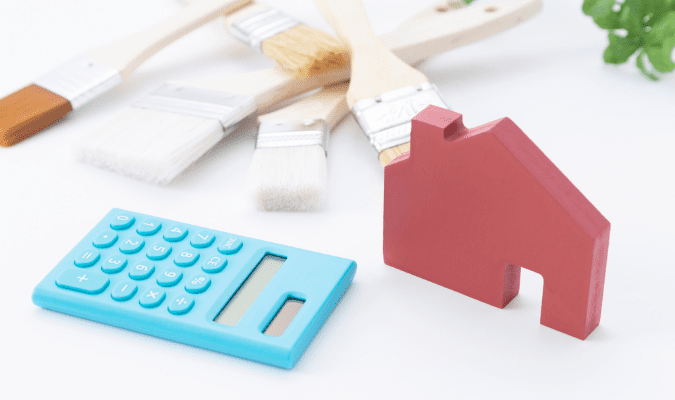
建設業における利益率とは、事業活動を通じて得た収益から費用を差し引いた割合を指し、企業の収益性や効率性を評価するための指標です。売上高に対する利益の割合を把握することで、企業がどれほど効率的に経営されているかを見極められます。
建設業は、道路や橋、建物など生活基盤を支えるインフラの建設を担い、社会において重要な役割を果たしています。近年、建設需要の増加や資材価格の上昇など、業界を取り巻く環境が急速に変化しています。
そのような状況下で企業が経営の安定を維持するためには、利益の確保が不可欠です。そのため、利益率は経営判断において欠かせない指標といえるでしょう。
利益率の意味と重要性
利益率は企業の経営状態を把握し、収益力や運営効率を判断するうえで不可欠な要素です。建設業では、材料費・労務費・外注費など多くのコストが発生するため、売上が高くても利益率が低い場合、経営が厳しい状態に陥る可能性があります。
利益率が高いことは、企業が効率的に事業を運営し、健全な収益を確保できていることを示します。一方で利益率が低い場合は、コスト管理の不備や競争の激化などの問題が考えられ、経営改善の必要性が生じるでしょう。
建設業界で企業が安定経営を続け、従業員の雇用を守り、社会貢献を果たしていくためには、適切な利益率の確保が不可欠です。そのためには、利益率の意義を深く理解し、自社の経営状況を的確に分析し、改善に向けた戦略を立てなければなりません。
建設業で注目すべき利益率の種類
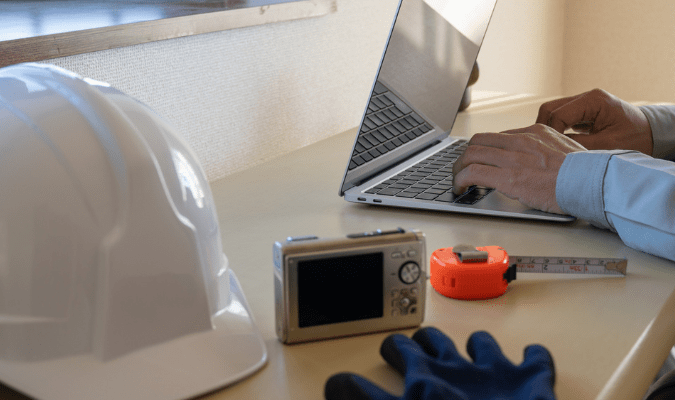
建設業で注目すべき利益率には、以下のような種類があります。
- 売上高総利益率(粗利益率)
- 売上高営業利益率
- 売上高経常利益率
- 自己資本経常利益率(ROE)
- 総資本経常利益率 (ROA)
それぞれの利益率が何を示し、どのように計算されるのかを理解することは、企業の経営状況を的確に分析するうえで不可欠です。
売上高総利益率(粗利益率)
売上高総利益率(粗利益率)は、収益性を測るための基本的な指標の一つです。売上高から売上原価を差し引いて得られる粗利益の割合で、建設業では工事価格から工事原価(材料費・労務費・外注費・経費など)を引いた金額が粗利益となります。
計算式:売上高総利益率 = 粗利益 ÷ 売上高 × 100% |
売上高営業利益率
売上高営業利益率は、企業における「本業」から生まれる利益を示します。売上高から売上原価と販管費を差し引いた営業利益の割合で、企業が主力事業を通じてどれだけの収益を上げられているかを評価する重要な指標です。
計算式:売上高営業利益率 = 営業利益 ÷ 売上高 × 100% |
売上高経常利益率
売上高経常利益率は、企業の経常的な収益力を測る指標です。売上原価・販管費・営業外費用を差し引いた、経常利益の売上高に対する割合を指します。売上高経常利益率は、主業務以外の収支も含めた、総合的な経営力を評価する指標とも言えるでしょう。
計算式:売上高経常利益率 = 経常利益 ÷ 売上高 × 100% |
自己資本経常利益率(ROE)
自己資本経常利益率(ROE)は、企業が株主から預かった資本をどれだけ有効に使い、利益を上げているかを示す指標です。経常利益を自己資本で割ることで算出され、企業の資本効率を表します。なお、ROEの数値が高いほど、資本を効率的に運用していると判断されます。
計算式:自己資本経常利益率(ROE) = 経常利益 ÷ 自己資本 × 100% |
総資本経常利益率 (ROA)
総資本経常利益率(ROA)は、企業が事業に投じた総資本をどの程度効率的に利益へと変えているかを示す指標です。ROAが高い場合、企業は資産を効果的に活用し、利益を生み出していると評価されます。
計算式:総資本経常利益率(ROA) = 経常利益 ÷ 総資本 × 100% |
建設業の利益率ランキング

ここでは、業界全体の動向や各企業の収益性を把握するために重要な、利益率ランキングを紹介します。ただし、ここで紹介するランキングはあくまで参考情報であり、各企業の利益率は事業内容や経営状況によって大きく異なる場合があることを前提としてください。
公的データに基づく建設業の利益率ランキング
国土交通省のデータによれば、2023年度の建設業全体の売上高営業利益率は約3.8%となっています。過去5年間の中でも高い水準であり、建設需要の増加や企業の生産性向上の取り組みが要因と考えられます。しかし、企業規模別に見ると、大企業の営業利益率は約4.2%であるのに対し、中小企業は約2.5%と、規模による格差が依然として存在しています。
スーパーゼネコンの利益率ランキング
スーパーゼネコンは、日本を代表する大手建設会社であり、高い技術力と豊富な経験を活かして国内外で数多くのプロジェクトを手がけているのが特徴です。最新の営業利益率ランキングは、以下のとおりです。
大手ということもあり、非常に高い利益率を上げているゼネコンが多い印象です。
準大手ゼネコンの利益率ランキング
準大手ゼネコンは、スーパーゼネコンに次ぐ規模の建設会社で、地域に密着した事業展開を行いながら全国的なプロジェクトにも積極的に参加しています。営業利益率ランキングについては、以下を参考にしてください。
- 長谷工コーポレーション: 7.8%
- 前田建設工業: 6.8%
- 安藤ハザマ: 4.7%
準大手ゼネコン全体の営業利益率が比較的高めになっているのは、高収益なマンション建設事業に強みを持つ企業が多いことが要因と考えられるでしょう。
中堅ゼネコンの利益率ランキング
中堅ゼネコンは規模こそ小さいものの、特定の地域や分野で高い専門性と技術力を持つ企業が多く存在します。営業利益率上位の企業は、以下のとおりです。
中堅ゼネコンは独自の技術やノウハウを活かし、ニッチな市場で高い収益性を実現している企業も多く見られます。
建設業における利益率の推移と現状

建設業の利益率について理解するために、利益率に影響を与える要因や企業規模ごとの特徴をもとに、推移と現状をみていきましょう。
建設業の利益率に影響を与える要因
建設業において、利益率は様々な要因の影響を受けます。企業の収益を左右する主要な要因として挙げられるのは、以下のとおりです。
<資材価格の高騰>
世界的な需要の増加や資源供給の不安定化によって、鉄鋼・木材・セメントなど主要資材の価格が上昇しています。資材コストの増加は、企業の収益に直接的な圧力をかける要因です。
<人手不足の影響>
高齢化と若年層の建設業離れによって、業界全体で人手不足が課題となっています。労働力の不足は、人件費の上昇や工期の遅延、品質の低下を招き、利益率の減少に結びついています。
<受注競争の激化>
公共工事の減少や民間投資の停滞により、業界内での受注競争が激しさを増しています。価格引き下げが不可避となる中、利益率の確保が困難な状況が続いているのです。
<労働時間の上限規制>
2024年4月の労働時間規制導入に伴い、長時間労働の是正が求められています。働き方の改善が進む一方で、企業には人件費増加や工期延長といった新たな課題が発生しました。
規模別に見る利益率の特徴
利益率の傾向は、企業規模ごとで異なります。
<スーパーゼネコン>
スーパーゼネコンは多くの大規模プロジェクトを手がけ、売上高の高さが特徴です。一方で、資材価格や人件費の上昇、受注競争の影響を強く受けるため、利益率は下がる傾向にあります。
<準大手ゼネコン>
準大手はマンション建設といった比較的利益率の高い事業に強みを持つケースが多く、利益率も安定して高い水準を維持しています。
<中堅ゼネコン>
地域や特定分野に特化した中堅ゼネコンの中には、収益性の高い事業展開を行う企業も見られます。しかし、規模が小さいため経営環境の変化に対する耐性が弱く、影響を受けやすいという一面もあります。
建設業の利益率向上のための戦略

建設業界では、資材価格の上昇や人手不足といった課題が重なり、経営状況が厳しさを増しています。収益を確保し、安定的な成長を続けるためには、以下のような戦略的な利益率向上施策が不可欠です。
- コスト削減
- 適切な価格設定
- 専門性の強化
- IT活用による業務効率化
建設業の利益率向上は、短期間で成し遂げられるものではありません。
しかし、提案した施策を確実に実行することで、経営における厳しい状況を打開し、長期的な成長を実現できるでしょう。
なお、建設業の利益率向上のための戦略として、クラフトバンクオフィスの導入もおすすめです。ここで紹介する方法とあわせて、クラフトバンクオフィスの導入も検討してみてはいかがでしょうか。
コスト削減
建設業において、収益を向上させるために最も初めに着手すべき施策として、コストの見直しが挙げられます。ただし、人件費や材料費を単純に削減するだけでは、品質の低下や納期遅延を引き起こし、社員のモチベーションを下げる可能性があります。
求められるのは、無駄な支出を徹底的に洗い出し、運用の効率化を図る戦略です。
<材料費削減の工夫>
- 大量購入や共同調達:業者との取引条件を見直し、スケールメリットを活かしたコストダウンを目指せる
- 規格統一による効率化:標準化された資材の導入が、調達コストを抑える手助けとなる。
- 廃材の再利用推進:余剰資材のリサイクルを奨励し、環境負荷軽減とコスト削減を同時に達成できる
<人件費の最適化>
- 人員配置の見直し:作業の効率を上げ、残業時間の抑制を目指せる
- 人材育成の促進:資格取得支援を行うことで従業員のスキルアップを図り、組織全体の生産性を高められる
<運搬費の削減策>
- 物流ルートの最適化:配送経路を見直すことで、運搬コストを削減できる
- 積載効率の向上:より効果的な積み込み計画を立て、輸送回数を減らす工夫が求められる
適切な価格設定
価格設定は、利益を確保するための不可欠な要素です。原価に利益率を上乗せするだけでなく、市場調査や競合の状況を把握し、顧客に納得される価格を導く必要があります。
<原価管理の徹底>
- 正確なコスト分析:原価を把握し、利益を圧迫する要因を早期に発見することが大切
<付加価値の見える化>
- 高品質施工や環境への配慮:短納期対応やエコロジーへの取り組みなど、顧客に対する付加価値を示し価格に反映させる
<交渉力の向上>
- 信頼関係の構築:顧客との信頼を深め、価格交渉を有利に進めるスキルが求められる
専門性の強化
収益性を高めるためには、以下の視点から特定分野での専門性を深め、競合に先んじた市場戦略を展開することが重要です。
<ニッチ市場への参入>
- 特化型技術の構築:需要が高まる分野に集中し、独自のノウハウを積み重ねることで、高収益を狙う
<技術力向上の取り組み>
- 最新技術の導入:従業員への教育と新しい工法の導入を通じて、質の高いサービスを提供する
<ブランド力の強化>
- 施工実績の積み上げ:実績と顧客満足度の向上に取り組み、ブランド価値を高め、受注の拡大を目指す
IT活用による業務効率化
以下に挙げるITツールの導入は、人手不足の解消やコスト削減、生産性向上に大きく寄与します。
<積算見積ソフト>
見積作業の効率化:作業の精度を向上させ、計算ミスを削減できる
<プロジェクト管理ツール>
情報共有の円滑化:工程管理を効率化し、コミュニケーションエラーの防止につなげられる
<BIM/CIM技術>
施工と設計の連携:情報の一元化により、施工の品質向上と業務効率化を実現できる
まとめ
建設業における利益率は、競争の激しさや採用する経営戦略に大きく影響を受けます。本記事で取り上げたランキングと分析を参考に、まずは自社の現状を的確に見極めましょう。
そのうえで、コストの見直しや価格戦略の最適化、専門性の強化、さらにはITを活用した効率化などの施策を取り入れることで、安定した収益の確保と事業拡大が可能になります。厳しい経営環境が続く中でも、利益率の改善を視野に入れた運営を行い、収益力強化を目指しましょう。
