建設業の時間外労働上限とは|2024年からの新ルールと対応策を総まとめ
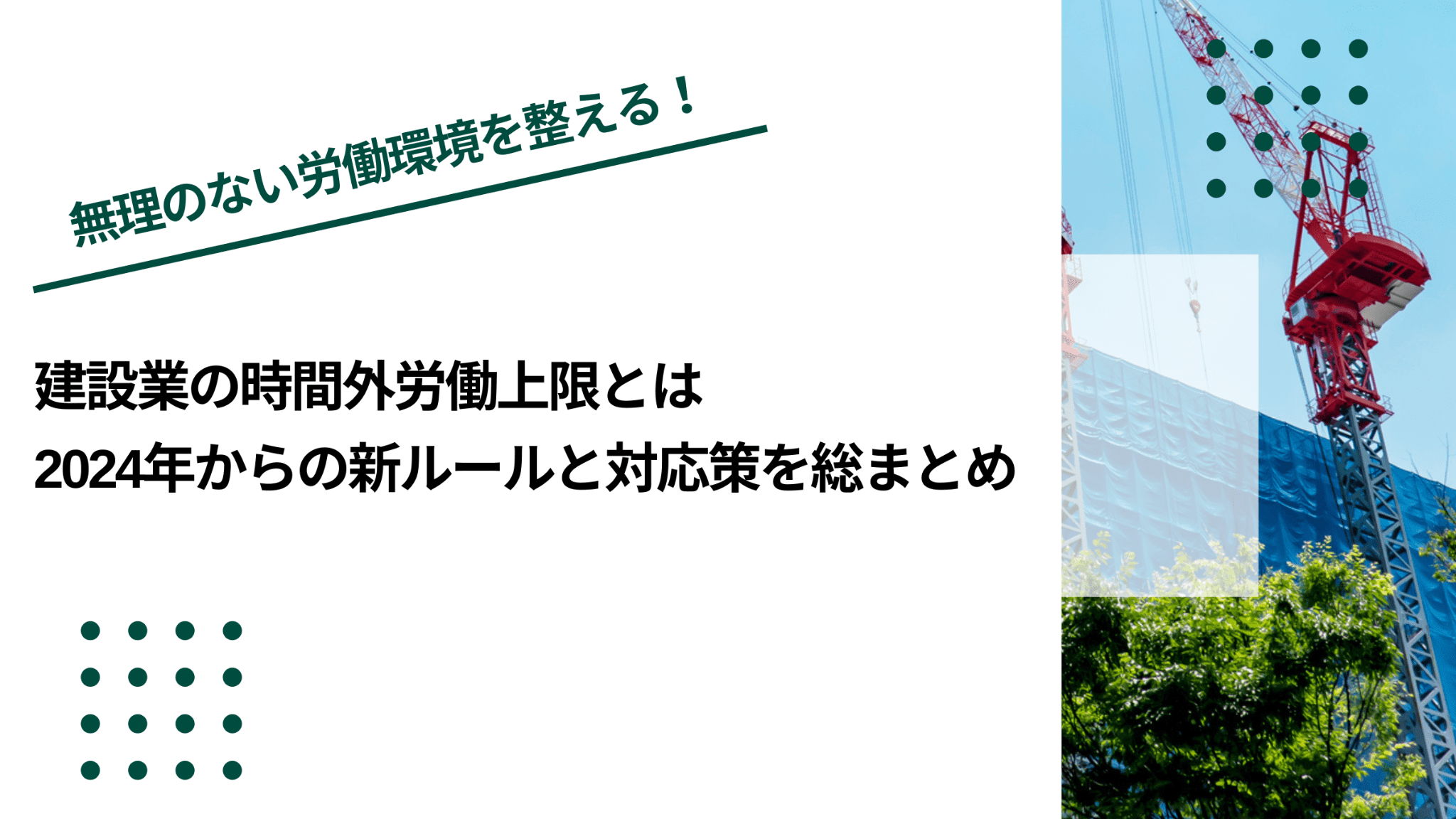
目次
- 建設業に時間外労働の上限が適用|2024年施行で何が変わったのか
- 上限規制の内容と罰則のポイント
- 現場作業も含めた労働時間の再確認
- 最低限やるべき対応
- 無理な工期が引き起こすリスクとは
- 勤怠管理の仕組みを見直す重要性
- 勘違いしやすい「労働時間」の定義と管理ミスを防ぐための視点
- 上限規制の具体的な数値と条件|特別条項があっても守るべき基準
- 原則となる上限は月45時間・年360時間が基本的なルール
- 特別条項付き協定を結んでも年間720時間を超える残業は不可
- 休日労働と合わせた制限も複数月平均80時間以内でなければならない
- 月100時間未満の制限も存在し短期集中の働き方にも制約がある
- 基準違反時の罰則は最大で懲役6か月・罰金30万円の対象になる
- 建設業界で進む勤怠管理の見直しと現場での対応策
- アナログ勤怠からの脱却が急がれる
- 現場ごとの働き方に応じたルールづくりが必要
- 36協定は実態に即した内容に見直す
- 元請けは下請けとの連携強化を図る
- 小さな改善から着手して対応を進める
- 若手離れと人手不足の打開策としての「時間外規制」
- まとめ
2024年4月、建設業界にも時間外労働の上限規制が本格的に適用されました。
長年猶予されていた規制が始まったことで、経営者や現場管理者は新たな対応を迫られています。
労働時間の見直しや勤怠管理の強化、36協定の再確認など、現場レベルで着手すべき課題は少なくありません。
本記事では、罰則やルールの具体的な内容を明らかにしながら、残業削減に向けた実践的な取り組みや小規模事業者でも取り組みやすい対応策をわかりやすく整理しています。
若手の定着や下請け管理にもつながる働き方改革の第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。
建設業に時間外労働の上限が適用|2024年施行で何が変わったのか

2024年4月から、建設業にも他産業と同じく時間外労働の上限規制が導入されました。
罰則の発生や現場への影響を理解し、必要な対応を進めましょう。以下では、見直すべきポイントや対応策を解説します。
上限規制の内容と罰則のポイント
これまで建設業では、36協定による上限規制の対象外とされてきましたが、猶予措置が終了したことで、月45時間・年360時間という基準がすべての事業者に適用されるようになりました。
さらに、特別条項付きの協定を締結した場合でも、以下の厳しい条件を満たす必要があります。
- 年間720時間
- 単月100時間未満
- 複数月平均80時間以下
違反した場合には罰金や懲役の対象となるため、管理体制の甘さが経営リスクに直結しかねません。
現場作業も含めた労働時間の再確認
朝礼や片付け、移動中の待機など、現場で「当たり前」とされていた作業の一部が、法的には労働時間に該当するケースがあります。
特に小規模な事業者では、日報やタイムカードに記録されない作業時間が無自覚な違反につながる恐れがあります。
従業員がどのタイミングから業務指示を受けているのかを見直し、曖昧になりがちな部分を明文化することが、今後のコンプライアンス対応に欠かせません。
最低限やるべき対応
大手企業と異なり、専任の労務担当者を持たない中小建設業者では、時間外労働の管理体制をすぐに整えるのが難しい場合もあります。
その場合はまず、36協定の見直しや締結状況の確認、そして就業規則との整合性を取ることから始めましょう。
労働基準監督署への届出を済ませ、過去の勤務実績をもとに違反リスクの高い部署や工程を洗い出す作業も欠かせません。
最小限の取り組みでも、実態を可視化するだけでリスクは大きく低減します。
無理な工期が引き起こすリスクとは
元請け・下請け関係を問わず、著しく短い工期が契約される現場では、上限規制の順守が困難になる場面もあります。
そのため、見積もり時点で無理のない工程を組むことが、労務リスクの回避だけでなく、信頼関係の構築にもつながります。
発注者側に対しては、「工期に関する基準」や行政資料を根拠とした説明を行い、必要に応じて工期変更の協議を行う姿勢が大切です。
勤怠管理の仕組みを見直す重要性
現場単位で時間外労働を抑えるには、従来の手書き管理から脱却し、打刻漏れや虚偽記録を防ぐための仕組みづくりが必要です。
近年ではスマートフォンやタブレットで打刻できる勤怠システムも登場しており、特に複数現場を抱える事業者にとっては有効な選択肢となります。
記録の整合性が取れる環境が整えば、労使間のトラブル防止にもつながります。
勘違いしやすい「労働時間」の定義と管理ミスを防ぐための視点

建設業の現場では、作業開始前の朝礼や片付け、資材の積み込みといった“準備作業”が習慣的に行われています。
しかし、これらの時間が「労働時間」に含まれるかどうかを誤解したまま管理してしまうと、意図せず法令違反となる可能性があります。
労働基準法では、使用者の指揮命令下にある時間はすべて労働時間とされており、明示的な指示だけでなく黙示的な命令であっても対象となります。
現場ごとに慣習が異なる場合も多いため、時間管理の基準を会社として統一し、曖昧な部分を洗い出してルール化することが重要です。
特に中小企業では、紙ベースの勤怠記録や口頭での報告が多く、把握漏れが起こりやすいため、まずは「何が労働時間なのか」を正しく理解することから始めましょう。
上限規制の具体的な数値と条件|特別条項があっても守るべき基準
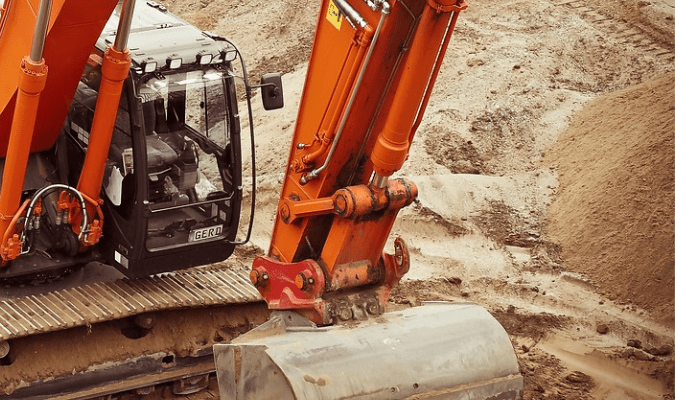
時間外労働の上限には明確な数値が定められており、特別な事情がある場合でも超えてはならない限界があります。
見落としやすい条件や例外の扱いについて、以下の項目で整理しましょう。
原則となる上限は月45時間・年360時間が基本的なルール
改正労働基準法のもとでは、建設業でも他業種と同様に、原則として月45時間、年間では360時間を超える時間外労働は認められません。
通常の36協定を結んでいる場合の基本的な枠組みであり、超過すれば法令違反となります。
現場の忙しさや繁忙期に関係なく基準となるため、日頃から業務量の平準化や効率化に向けた取り組みが欠かせません。
特別条項付き協定を結んでも年間720時間を超える残業は不可
臨時の業務増加など、やむを得ない状況が発生した際に備えて特別条項付きの36協定を締結するケースもあります。
ただし、無制限の残業が許されるわけではなく、年間の上限は720時間と明記されています。
あくまで一時的な対応手段であり、常態化させてはならない点に注意しましょう。
協定を活用する際には、その理由や期間を明確にしておくことが重要です。
休日労働と合わせた制限も複数月平均80時間以内でなければならない
特別条項がある場合でも、月単位だけでなく2〜6か月の複数月平均で時間外労働と休日労働を合計した場合に、月平均80時間を上回らないという制限があります。
休日出勤も含まれるため、休日の出動が続くとすぐに基準超過に近づいてしまいます。
日々の積み重ねが結果的に違反リスクとなることも多いため、定期的な集計と管理が求められるでしょう。
月100時間未満の制限も存在し短期集中の働き方にも制約がある
月ごとの時間外労働と休日出勤の合計は、単月で見ても100時間を下回る必要があります。
繁忙期などに短期間で集中的に作業を進めようとする場面では、思わぬ超過につながる恐れがあります。
月末に調整しようとすると帳尻が合わなくなるケースもあるため、週単位や日単位での計画的な働き方が求められるようになりました。
基準違反時の罰則は最大で懲役6か月・罰金30万円の対象になる
時間外労働の上限を超えた場合、労働基準法違反として刑事罰の対象になります。
違反内容によっては6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があり、法令順守への意識が問われます。
特に下請けを多く抱える元請企業の場合、連携ミスによって下請けの労働時間が見えづらくなるリスクがあるため、全体のスケジュール共有も不可欠です。
建設業界で進む勤怠管理の見直しと現場での対応策

時間外労働の上限規制に対応するには、現場の運用だけでなく勤怠管理のあり方も再構築が求められます。
以下では、管理体制を整えるための実践的な対応策を紹介します。
アナログ勤怠からの脱却が急がれる
紙のタイムカードや手書き日報では、出退勤の正確な記録が難しく、労働時間の過少申告や集計ミスが発生しやすくなります。
従来の方法では、上限規制を超えているかどうかの把握が遅れ、結果的に違反リスクを高めてしまうでしょう。
現場環境に合った打刻システムやモバイル対応の勤怠アプリを導入し、各作業員の実働時間をリアルタイムで把握できる体制を整えることが望まれます。
現場ごとの働き方に応じたルールづくりが必要
建設業の就業形態は、天候や工程に左右されやすく、すべての現場で一律のルールを適用するのは現実的ではありません。
例えば、遠方の現場では移動時間が長くなることも多く、直行直帰を採用していても業務指示の有無によって労働時間に含まれるかどうかが変わります。
現場単位での労働時間の解釈や、ルールの明文化がトラブルを防ぐ土台となります。
36協定は実態に即した内容に見直す
36協定は締結すればそれで完了ではなく、日々の労働実態と合っていなければ意味を成しません。
特別条項付きの協定を運用する際には、年720時間や月100時間未満といった法定上限を超えないよう、月次や四半期単位で勤怠データをチェックする仕組みが必要です。
見直しの際には、現場の声を取り入れたうえで、管理部門と施工部門の連携を強めましょう。
元請けは下請けとの連携強化を図る
元請企業が法令を順守していても、下請け業者が時間外労働の基準を超えている場合には、全体として行政からの指導対象になるケースがあります。
そのため、施工計画の段階で無理のない工期を設定し、協力会社との定期的な情報共有や勤怠の実態確認を行うことが重要です。
小さな改善から着手して対応を進める
勤怠管理システムの導入が難しい場合でも、まずはExcelなどを活用した工数集計や、毎日の業務終了時に残業申告を義務化するなど、シンプルな取り組みからスタートできます。
重要なのは、現状の把握と意識の共有を優先し、段階的にルールと仕組みを整えていくことです。
若手離れと人手不足の打開策としての「時間外規制」

建設業界では若年層の入職者が減少し、55歳以上の従事者が3割を超えるなど高齢化が進んでいます。
背景として、長時間労働の常態化が若手の定着を妨げてきたことが挙げられます。
2024年4月から建設業にも時間外労働の上限が導入されたことで、働く環境の改善が制度面からも強く求められるようになりました。
規制は単なる制限ではなく、人材を呼び戻すための転機とも捉えられます。
無理な工期や過度な残業を見直し、週休2日制の推進や現場ごとの労働時間の見える化を進めることが、人手不足解消への第一歩となるでしょう。
まとめ
建設業への時間外労働上限の適用は、現場の働き方を見直す大きな転換点となります。
月45時間・年360時間を基本とし、特別条項があっても年720時間を超えれば違法となる厳格な基準のもと、従来の慣習や業務運用を見直す必要が出てきました。
対応を後回しにすれば、違反リスクや行政指導につながるだけでなく、人材確保の面でも不利になります。
勤怠管理の仕組みづくりや協力会社との連携強化を通じて、無理のない労働環境を整えていきましょう。
