建設業はお盆休みを取れない?傾向や働き方改革との関係性について
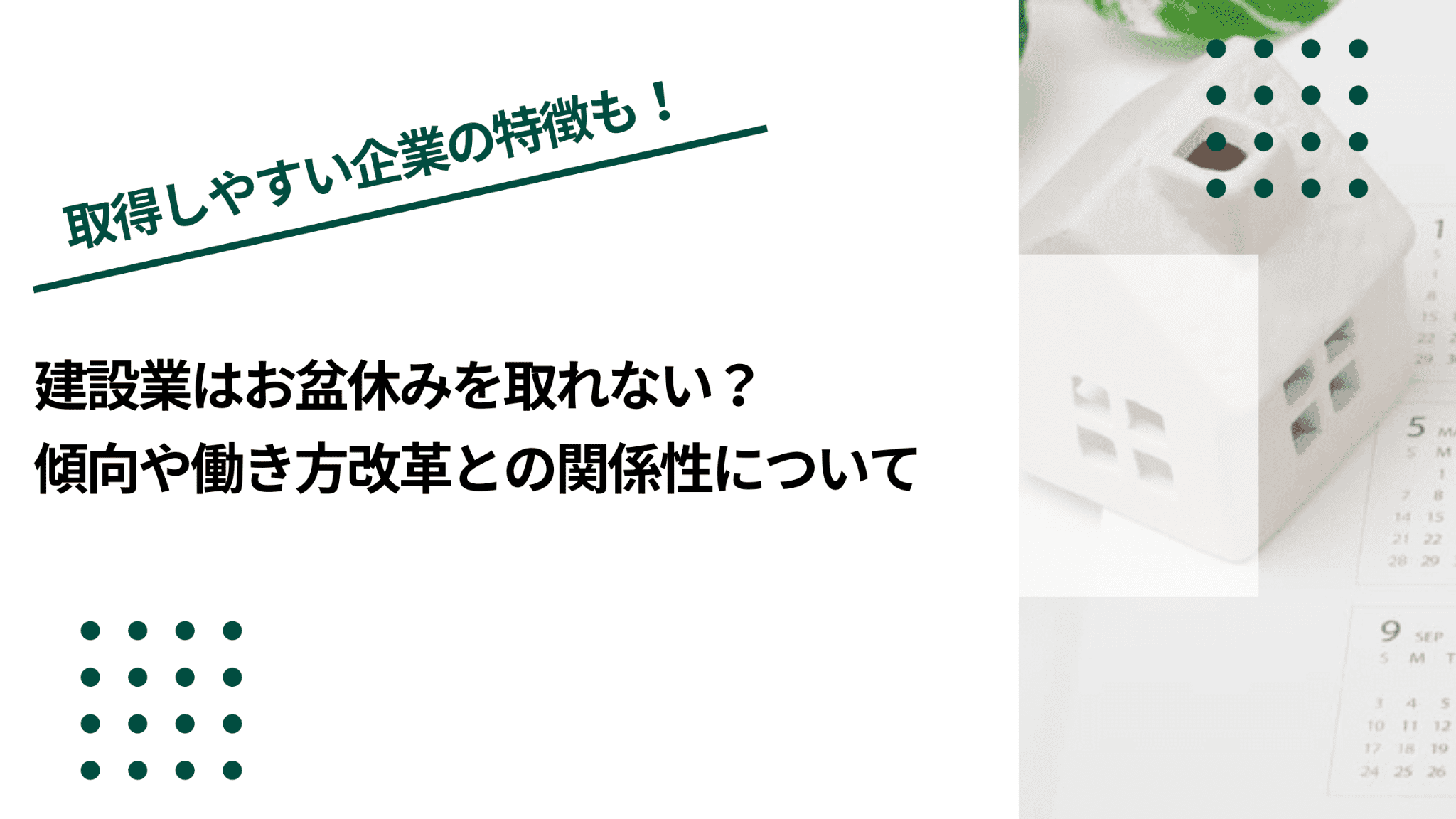
目次
建設業界において、お盆休みの確保は従業員の働きやすさに大きく影響を与える重要なポイントです。一般的に、建設業は他の業種と比べてお盆休みが取りにくいという印象が根強くありますが、近年の働き方改革の影響で、変化が見られています。
本記事では、建設業におけるお盆休みについて、次の観点から詳しく解説します。
- 建設業におけるお盆休みの傾向
- 建設業のお盆休みが少ないとされる理由
- 建設業と一般企業のお盆休みの違い
- 建設業のお盆休みと働き方改革の関係性
また、お盆休みを取りやすい建設業の特徴も紹介しているので、休日の取りやすさをアピールして人材確保を強化したい建設業者の方は、ぜひ参考にしてください。
建設業におけるお盆休みの傾向

建設業のお盆休みは、一般企業のようにカレンダー通りに休暇を取得できるとは限りません。企業や職種、現場状況によって休日日数が異なる傾向にあります。
例えば「小林建設工業株式会社」は2024年の夏季休暇を8月11日から18日までの9連休と設定し、企業全体が休業となりました。一方「大成建設」は、2024年8月10日から18日までの期間、Webサイトでのお問い合わせ対応を休止すると発表しています。
建設業のお盆休みは少ないのか
建設業のお盆休みは、建設業特有の事情が背景にあることから、一般企業と比較して少ないと言えるでしょう。
建設業では週休2日制の普及率が低く、4週4休以下で稼働している現場の多さがお盆休みが少ない理由として挙げられます。また、公共事業など納期が厳守される工事の場合、工期に間に合わせるために休日返上で作業を行うケースも少なくありません。
さらに、日給月給制の労働者にとっては、休みが増えることで収入が減ってしまう懸念もあります。
加えて、建設業は他の業界と比べて利益率が低い傾向にあります。そのため、休みを増やすことで人件費などのコスト増加が経営を圧迫する可能性も理由として挙げられるでしょう。
建設業と一般企業のお盆休みの違い
建設業と一般企業のお盆休みの大きな違いは、休日日数のばらつきです。一般企業では、カレンダー通りの祝日に加えて夏季休暇としてお盆期間を含む数日間の休みを設定するのが一般的です。
一方、建設業では企業全体で休みを取得する場合でも、現場によっては稼働しているケースがあります。特に、オフィスビルなどのテナント工事は、テナントが休暇中の期間中に行われることが多く、お盆期間中も工事が行われる傾向にあります。
とはいえ、職人の中には、お盆期間中も工期が迫っている現場で働く人もいれば、新築住宅の現場のようにお盆期間中に帰省するために休みを取る人もいるため、あくまで状況によって異なると認識しておきましょう。
建設業のお盆休みと働き方改革の関係性

建設業のお盆休みは、働き方改革の影響を受けて変化しつつあります。従来、建設業では週休2日制の導入が進んでおらず、休日日数が少ないことが課題でした。お盆休みについても、企業全体としては休みであっても、現場によっては稼働しているケースも見られていました。結果、休日日数は企業や職種、現場の状況によって大きく異なっていたのです。
しかし、働き方改革関連法の施行により、時間外労働の上限規制が設けられ、2024年4月からは建設業にも適用されることになりました。時間外労働の上限規制には休日出勤も含まれるため、建設業でもお盆休みを含む休日取得の促進が期待されています。
国土交通省は、働き方改革を推進するために「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定し、週休2日制の導入推進などを進めています。
同プログラムには、週休2日の確保に加え、適正な工期設定や賃金、社会保険に関する取り組み、生産性向上などが推進項目に含まれています。
建設業でもお盆休みを取りやすい企業の特徴

建設業では一般的にお盆休みを含めた休日が少ないイメージを持たれていますが、企業によっては、お盆休みを取得しやすい場合があります。例えば、以下の特徴に当てはまる建設関係の企業は、お盆休みを取得しやすいでしょう。
- 発注者支援業務をメインとしている
- ICT技術の活用や業務効率化を進めている
- 働き方改革に積極的に取り組んでいる
ここでは、建設業でもお盆休みを取りやすい企業の特徴について詳しく解説します。
本記事内で解説している「建設業におけるお盆休みの傾向」や「建設業のお盆休みと働き方改革の関係性」に通ずる視点でもあるため、各内容を再度把握するうえでもぜひ一読ください。
発注者支援業務をメインとしている
官公庁の業務を代行する発注者支援業務をメインとする建設業は、官公庁に準じた勤務体系となります。そのため、土日祝日休みやカレンダー通りの休暇を取得しやすいでしょう。
発注者支援業務をメインに行っている企業は、週休2日を導入していることもあるようです。また、官公庁自体が暦にあわせて休業するため、お盆休みがより自然に取得できると考えられます。
ICT技術の活用や業務効率化を進めている
ICT技術を積極的に導入し、業務効率化を進めている建設業も、お盆休みを取得しやすいでしょう。施工管理システムや電子契約サービスなどのデジタルツールを活用している建設業者であれば、既存の業務プロセスを大幅に効率化できていることが理由です。
先端技術を取り入れることで時間がかかっていた作業が短縮され、業務の生産性が向上します。結果、仕事の負荷が軽減され、休暇を取得する余裕が生まれやすくなるのです。
働き方改革に積極的に取り組んでいる
働き方改革に積極的に取り組んでいる建設企業は、お盆休みを取得しやすい環境が整っていると判断できます。週休2日制の導入や有給休暇の取得促進、休暇を取得しやすい職場風土の醸成に力を入れている企業が該当するでしょう。
また、厚生労働省や国土交通省が提供する建設業向けの働き方改革支援制度を積極的に活用している企業も、休暇取得を含めた働きやすさを確立できていると考えられます。
まとめ
建設業界では、他業種と比較してお盆休みが短い傾向にありますが、働き方改革が進む中で、休暇取得に関する改善も見られています。特に、発注者支援業務を中心に行う企業やICT技術を導入している企業では、業務の効率化が進んでおり、より休暇を取りやすい環境が整っています。人員数の確保を通じて事業運営を強化するためにも、働き方改革を推進し、しっかりとしたお盆休みの制度を整えることが重要です。
