建設業で儲かる業種は?仕事内容や業界の現状も含めた詳細について
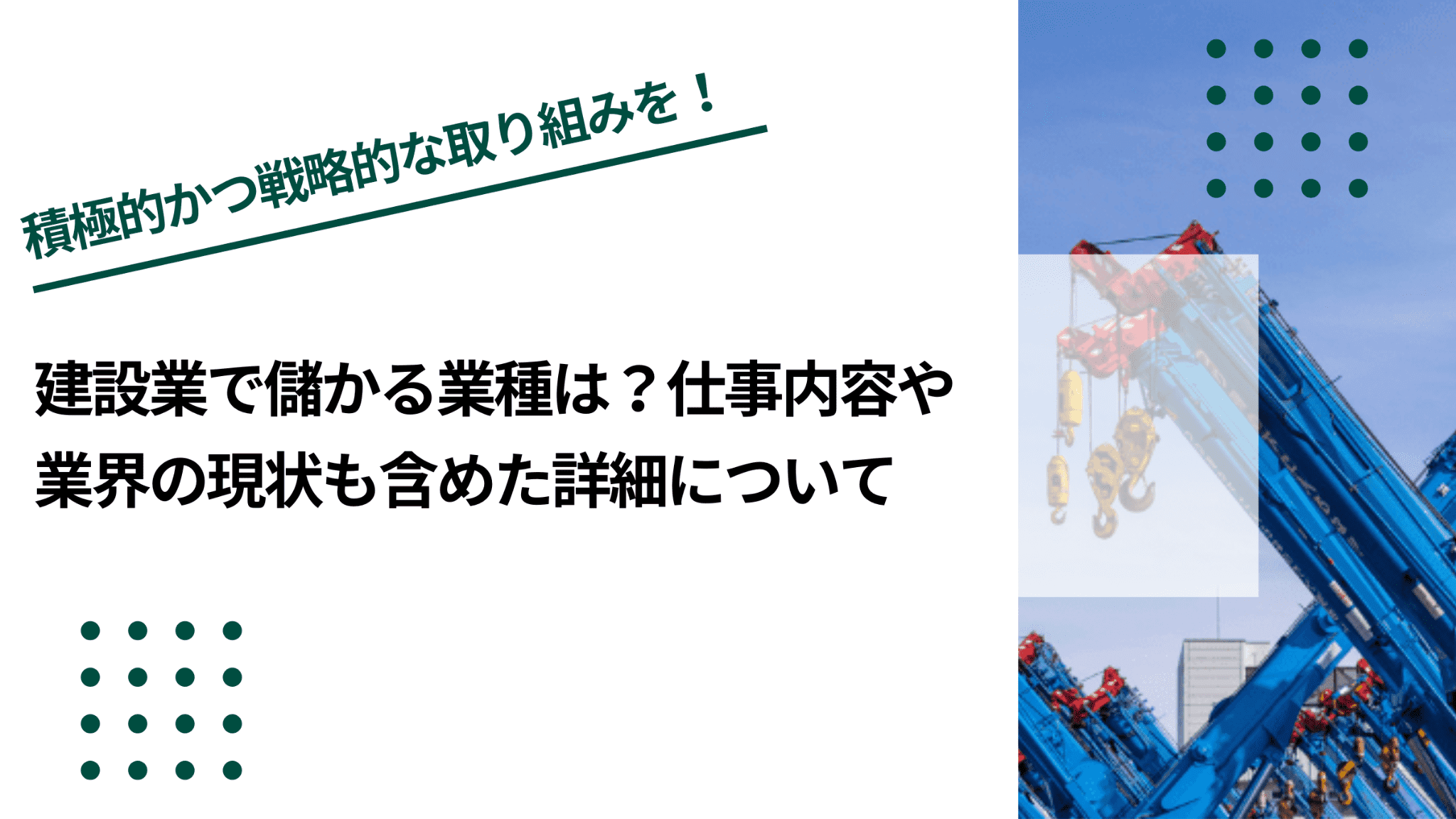
目次
本記事では建設業に関して、以下の内容を取り上げます。
- 建設業は儲かる業種なのか
- 建設業の収益に関する現状
- 建設業で「儲かる」業種
- 建設業における「儲からない」側面
- 儲かる建設業者になる方法・視点
建設業界は、景気の動向に大きく影響されやすい傾向にあり、下請け構造が生む利益率の低下などの現実に直面することも多いでしょう。
ただし、時代のニーズを的確に捉え、計画的なビジネス戦略を実行することで、高い収益を実現する可能性もある業界です。
そもそも建設業は儲かる業種なのか
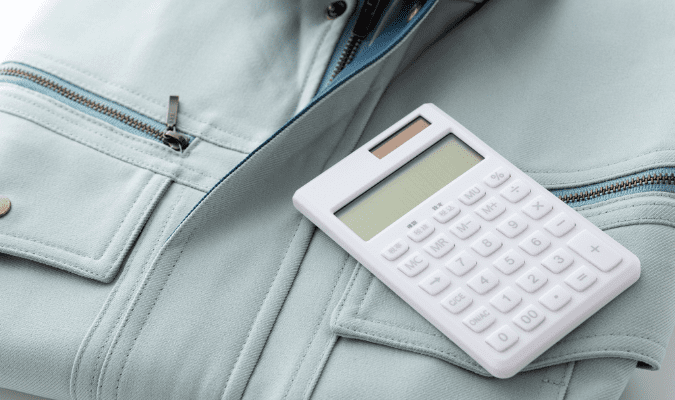
建設業界で成功を収めるには、まず業界全体の収益構造をしっかりと把握することが欠かせません。
どの業種が儲かるのか、建設業界の現状について詳しく見ていきましょう。
建設業の収益に関する現状
建設業は、公共事業から民間の工事まで多岐にわたる需要を抱えているため、安定した業界とされています。
しかし、業種ごとに収益の状況は大きく異なり、必ずしもすべての業種が高収益を生むわけではありません。
たとえば収益が期待できる業種として、塗装業や足場・とび職、高単価の案件が多い外構工事が挙げられます。
専門的な技術や知識を必要とし、独立を目指す人にとっても高収入の可能性を秘めている業種です。
高収益を狙う建設業者になるためには、需要の高い業種を選ぶだけでなく、元請けに近い案件を獲得したり、自社で集客力を高めたりする努力が必要です。
建設業で「儲かる」業種

建設業界には数多くの業種が存在し、それぞれの収益性には大きな違いがあります。
ここでは、建設業でも特に高収益が期待できる業種を詳しく紹介します。
塗装業
建物の美観や耐久性を保つために必要不可欠な塗装業は、リフォームの需要が高かる昨今において安定している分野と言えるでしょう。
戸建て住宅から商業施設まで幅広い建物が対象となり、独立しやすい業種としても人気があります。
一人親方として働くケースも多く、独立後は自社サイトを活用した集客を強化することで、元請けとして高収益を狙うことが可能です。
参照:住宅リフォーム市場に関する調査を実施 ~2021年第4四半期及び2021年計~
足場・とび職
足場・とび職は、高所作業に必要な足場の設置や解体を専門とする分野です。
新築工事やリフォーム、解体工事など多岐にわたる現場で需要があり、安定した仕事量を確保できるのが魅力です。
リスクを伴う作業であることから、他の職種より収入が高い傾向にあり、経験を積んで独立することでさらに高収入を得ることも可能です。
また、超高層ビルを中心とした大型案件の需要が高まっていることを考えると、足場・とび職は儲かりやすい業種と考えられるでしょう。
参照:建築需要をけん引する大型案件、2023年が着工のピークに
解体業
解体業は、建物の老朽化や建て替えによる需要が高まっています。
日本では空き家問題が深刻化していることから、今後も解体工事のニーズが高まると予想できるでしょう。
初期投資として許可申請や専用車両の導入が必要ですが、事業が軌道に乗れば大きな利益を得られる可能性があります。
建築士
建築士も、建設業で効率的に儲けるための選択肢に挙げられます。
一級建築士の場合、企業規模にもよりますが高収入を得ることが可能です。
また、令和2年から建築士資格の受験資格が緩和されたことから、業種としての需要が高く、かつ就業に関するハードルも下がったと考えられるでしょう。
したがって、建築士の資格取得を目指すことが「儲かる」ための施策になると言えます。
参照
政府統計の総合窓口 |賃金構造基本統計 調査令和元年以前 職種DB第1表
国土交通省|令和2年から建築士試験の受験要件が変わり、新しい建築士制度がスタートします!
建設業でも「儲からない」側面がある
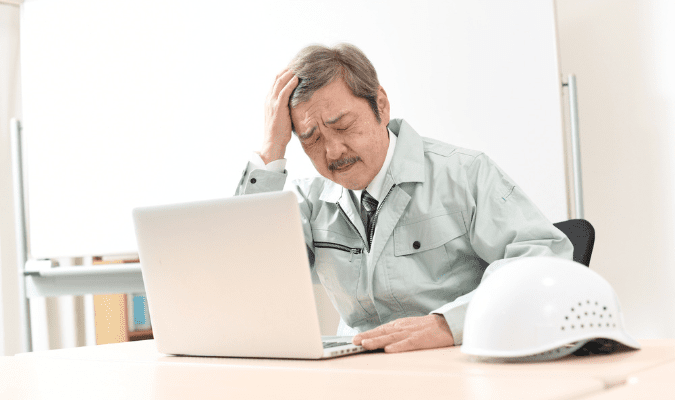
建設業は安定したイメージを持たれがちで、高収入を期待する人も多いでしょう。
しかし実際には、収益面で課題を抱えるケースも少なくありません。
ここでは、収益性が低い建設業者に見られる共通点を、いくつかの観点から考察します。
利益率を圧迫する多重下請け構造
建設業界では、以下のような多重下請け構造が一般的です。
- 元請け
- 下請け
- 孫請け
元請けが大きな利益を得る一方で、下請けや孫請けに進むほど利益率が低下するのが現実です。
また、業界の長年の慣習や付き合い重視の文化により、不利な条件での受注を余儀なくされる場合もあります。
元請け依存から脱却し、直接受注できる仕組みを整えることで多重下請け構造による利益率の低下を防止できるでしょう。
旧態依然とした経営戦略
建設業界は現場重視の文化が根強く、営業やマーケティングといった戦略的な経営が後回しにされがちです。
「今のままで十分だ」という現状維持の考え方は、時代の変化が速い現代において衰退を招く要因になります。
持続的な成長を目指すには、時代や経済の変化を敏感に捉え、新しいビジネスモデルを積極的に導入する姿勢が求められます。
社員の自主性・創造性の欠如
新しい挑戦を避ける風潮や「手間がかかる」「忙しいから後回し」という姿勢は、企業全体の成長を阻害します。
社員一人ひとりが当事者意識を持ち、創造性を発揮できる組織づくりを進めることで、収益性の向上につながるでしょう。
トップダウン型の経営から脱却し、社員が主体的に動ける環境を整えることが重要です。
儲かる建設業者になるには

建設業界で収益を上げ、安定した成功を収めるためには、戦略的な取り組みと柔軟な対応力が不可欠です。
ここでは、儲かる建設業者になるため実施すべき収益性を高める方法を紹介します。
顧客ターゲットを絞り込む
マーケティングの観点を取り入れ、自社の強みを最大限に活かせる顧客層を絞り込むことが重要です。
すべての顧客にサービスを提供するのではなく、リフォーム工事であれば内装や外構、水回りなど特定の分野に特化し、高い評価につながる顧客にアプローチしましょう。
顧客のニーズを深く掘り下げ、的確に応える施工メニューを整備することで、他社との差別化を通じた収益の向上が期待できます。
元請けとの関係を見直して直接受注を増やす
下請けに留まらず、元請けとの取引を見直し、直接受注を増やす努力も求められます。
過去の取引データを分析し、利益率の低い元請けとの契約を再検討することも一つの手です。
また、新規顧客の獲得を目指したマーケティング戦略を活用することで、元請け依存から脱却し、安定した利益を生み出す基盤を築けます。
新しいビジネスモデルに挑戦する
時代や経済の変化に対応するためには、これまでの慣習にとらわれない新たなビジネスモデルを導入する積極性が求められます。
不測の事態にも対応できるよう、内部留保を強化し、堅実な経営を心掛けましょう。
特に、事業の後継者にとっては、伝統に縛られずに革新的なアイデアを活用し、事業を発展させる好機と言えます。
経営者のビジョンを明確化して組織を活性化する
高収益を得られる建設業者になるには、経営者が明確なビジョンを掲げ、全社員を巻き込んだ行動計画を策定することが重要です。
事業計画を単なる数値の目標としてではなく、社員一人ひとりの意欲や創造性を引き出すための指針として活用しましょう。
共通の目標に向かって全社員が協力し、実行可能な具体的な計画を持つことで、収益の向上を実現できます。
原価削減をする
建設業で利益を確保するには、工事原価の削減が重要です。
原価は材料費・労務費・外注費・経費から構成され、直接材料購入や作業員配置の最適化、実行予算の活用が求められます。
また、固定費削減や外注活用も有効ですが、品質を損なわない工夫が必要です。
なお、建設業における原価削減には、クラフトバンクオフィスの導入もおすすめです。原価削減の一環として導入を検討ください。
まとめ
建設業は、収益を上げる可能性を十分に秘めた業界です。
塗装や足場・とび職、外構工事や解体業、設備組み立て、大工といった高い需要を持つ業種が多く存在します。
しかし、建設業者として成功を収めるには、顧客層の明確化や元請けとの関係の再構築、新しいビジネスモデルへの挑戦など、積極的かつ戦略的な取り組みが求められます。
さらに、経営者が明確なビジョンを掲げて組織を活性化させることで、建設業としての成長が実現するでしょう。
