建設業における「免許」の基礎知識|必要性や関連資格など
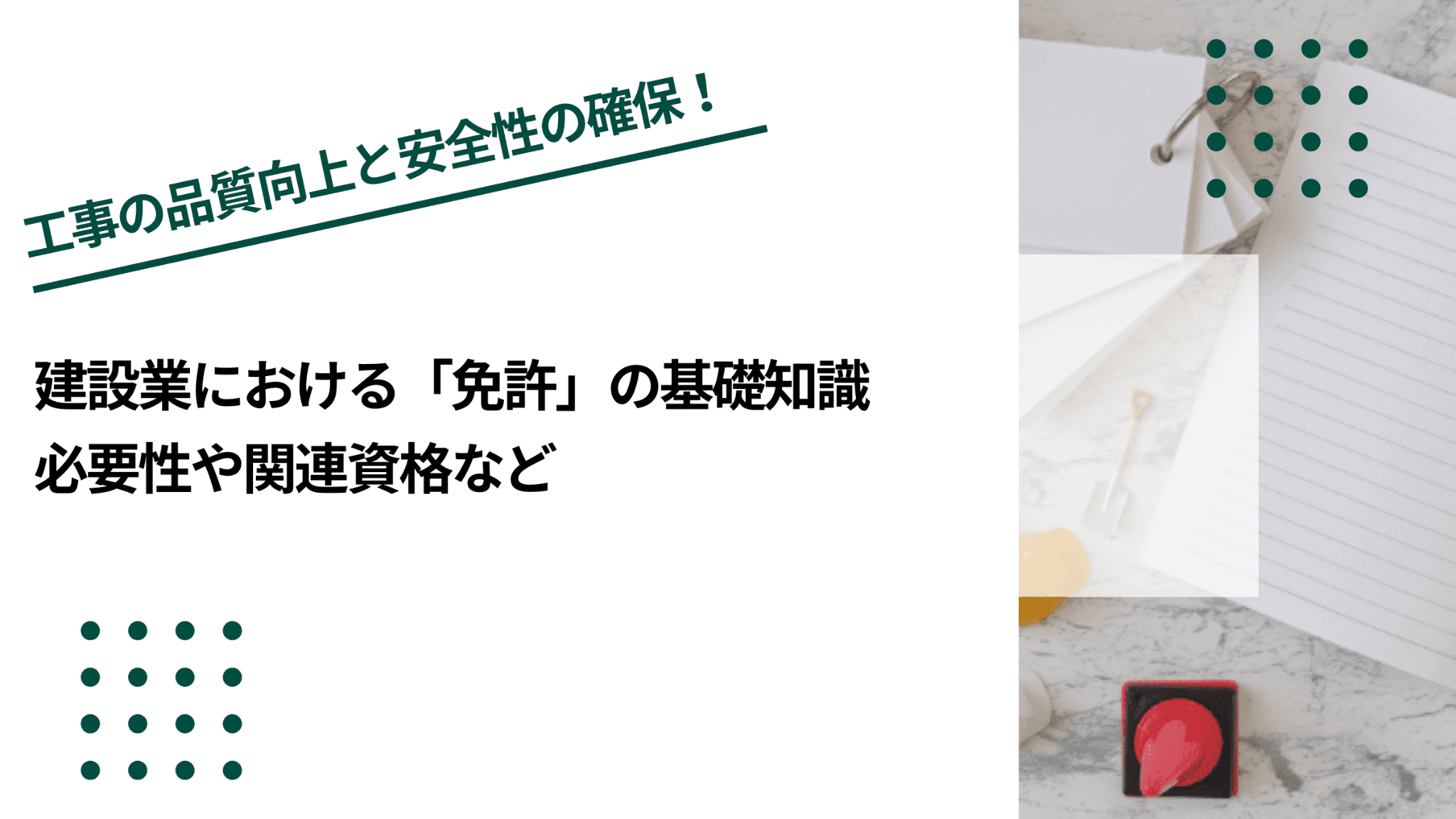
目次
建設業を営むうえで、免許の取得は欠かせないステップです。ただ、なぜ免許が必要なのか、どのような種類が存在するのか、そして取得にはどんな資格が求められるのか、疑問が浮かぶでしょう。
本記事では、建設業における免許について、以下の視点から解説します。
- 建設業に免許が必要な理由
- 建設業における免許の種類
- 建設業の免許取得につながる資格一覧
- 一般建設業許可と特定建設業許可で必要な資格の違い
- 建設業の免許申請において必要な基礎知識
本記事を通じて建設業の免許に対する理解を深め、事業運営に役立てていただければ幸いです。
なぜ建設業に免許が必要なのか?

建設業に免許が必要な理由は、社会資本の形成と国民の安全確保にあります。建設工事は、国民の生活や経済活動の基盤となる重要な役割を担っています。そのため、適切な施工が不可欠です。
建設業法に基づく免許制度は、事業者の技術力や経営状況を審査する一助となります。一定の基準を満たした事業者のみが工事を請け負えるようになるため、建設工事の品質向上と安全性の確保につながるでしょう。
また、免許制度には建設業界の健全な発展を促す狙いもあります。技術力や経営基盤の向上を目指す事業者が増えることで、業界全体のレベルアップが期待できます。
無許可で建設業を営むリスク
無許可で建設業を営むことは法律違反であり、大きなリスクを伴います。まず、法的制裁として3年以下の懲役や300万円以下の罰金が科される可能性があるでしょう。法人の場合は、最大1億円の罰金が課されることもあります。
無許可営業は、事業機会の損失にもつながるでしょう。公共工事の入札参加には建設業許可が必須条件となっているため、大規模な工事を請け負う機会を逃してしまいます。また、多くの元請業者が下請業者にも許可取得を求めているため、下請工事への参加も制限されます。
加えて、社会的信用の低下も深刻な問題です。建設業許可は、事業者の技術力や経営基盤の証明となります。そのため、無許可での営業は取引先からの信頼を損ない、新規顧客の獲得も困難になるでしょう。
さらに、請負可能な工事にも制限がかかります。許可がない場合、500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満)の軽微な工事しか請け負えません。軽微な工事のみ請け負う状態では、事業の成長や収益の拡大を阻害してしまいます。
建設業における免許の種類
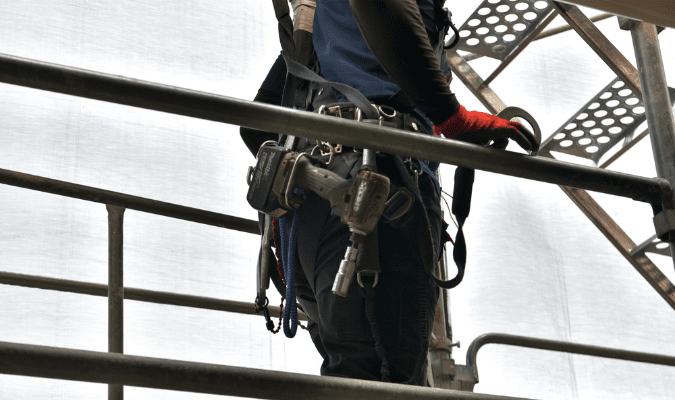
建設業の免許は、事業内容や規模に応じていくつかの種類に分類されます。自社に最適な許可を取得するためには、それぞれの違いを理解することが重要です。主な区分として、許可行政庁による区分、建設工事の種類による区分、請負金額による区分があります。
区分について正しく理解することで、適切な許可申請が可能になるでしょう。また、事業拡大や新規事業展開の際にも、必要な許可の種類を迅速に判断できます。以下では、各区分について詳しく説明していきます。
許可行政庁による区分
建設業の免許は、許可を出す行政庁によって「大臣許可」と「知事許可」の2種類に分けられます。
大臣許可は、複数の都道府県に営業所を持つ場合に国土交通大臣から許可を受けるものです。知事許可は、1つの都道府県内に営業所がある場合、都道府県の知事から許可を受けることになります。
営業所の所在地によって許可の種類が決まりますが、実際の工事は全国どこでも行えます。区分を理解すれば、適切な申請先を選べるでしょう。
建設工事の種類による区分
建設業の許可は、建設工事の種類ごとに細かく区分されているのも特徴です。
<一式工事(2種類)>
|
<専門工事(27種類)>
|
参考:国土交通省|「建設業許可事務ガイドラインについて」の一部改訂について
申請の際には、自社が実施する具体的な工事内容に応じて、該当する業種のすべてに対して許可を得る必要があります。たとえば、建築一式工事の許可だけでは足りず、左官工事や電気工事を行う場合には、それぞれに対応した別個の許可を取得しなければなりません。
請負金額による区分
建設業許可は、請負金額によって「一般建設業」と「特定建設業」に分けられます。
特定建設業の許可が必要なのは、1件の工事につき4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の工事を下請会社に依頼する場合です。それ以外の場合、つまり下請発注金額がこの基準未満であれば、一般建設業の許可で営業が可能となります。
注意すべき点は「元請会社であること」と「下請会社に依頼すること」の2つの条件が揃った場合にのみ、特定建設業の許可が必要になるということです。大規模な工事であっても、すべて自社で施工する場合は特定建設業には該当しません。
建設業の免許取得につながる資格一覧

建設業の免許を取得するためには、専任技術者の配置が必要です。専任技術者になるには、一定の実務経験や関連する資格の取得が求められます。資格を取得すれば、専任技術者の要件を効率的に満たせるでしょう。
ここでは、建設業の免許取得に直結する資格について詳しく解説します。
専任技術者になるための資格
専任技術者の要件を満たすには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 対応する国家資格を保有していること
- 一定の実務経験を有すること
- 資格と実務経験の両方を有すること
まず、対応する国家資格を保有していることが大切です。1級建築士や1級電気工事施工管理技士など、建設業界での専門性を証明できる資格が例に挙げられます。
次に、一定の実務経験を有していることも要件の一つです。建設業に関連する実務経験が一定期間以上あれば、専任技術者として認められる場合があるでしょう。
さらに、資格と実務経験の両方を有することも条件として認められます。資格の種類によっては、必要な実務経験の年数が異なることがあるため注意してください。
なお、特定建設業許可の専任技術者になれる資格は、一般建設業許可の専任技術者としても認められます。そのため、より高度な資格を取得することで、幅広い建設業許可に対応できるようになるでしょう。
業種別の資格一覧
建設業許可は29の業種に分類されており、業種ごとに必要な資格が異なります。以下は、主な業種と、専任技術者になるために必要な代表的な資格の例です。
業種 | 資格例 |
土木一式工事 | 1級土木施工管理技士、技術士(建設部門) |
建築一式工事 | 1級建築士、1級建築施工管理技士 |
電気工事業 | 1級電気工事施工管理技士、電気主任技術者 |
管工事業 | 1級管工事施工管理技士 |
鋼構造物工事業 | 1級土木施工管理技士、1級建築士 |
とび・土工工事業 | 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木・薬液注入)、1級建設機械施工技士 |
解体工事業 | 1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築・躯体)、(必要に応じて登録解体工事講習の受講) |
その他の専門工事 | 各業種に対応する施工管理技士、建築士、その他の専門資格 |
上記の資格以外にも、建設業許可の取得に役立つ資格は多数存在します。また、資格を取得していなくても、長年の実務経験があれば専任技術者になれる場合があります。
しかし、資格を保有することで、よりスムーズに専任技術者の要件を満たせるため、建設業許可の取得を目指すのであれば、関連資格の取得を検討しましょう。
資格取得と実務経験の関係性
建設業の資格取得には、実務経験が重要な役割を果たします。多くの国家資格では、一定期間の実務経験が受験資格として設定されているためです。
例えば1級建築施工管理技士の場合、学歴に応じて3〜10年の実務経験が必要です。大学で指定学科を卒業した場合は3年、高校で指定学科を卒業した場合は5年の実務経験が求められます。
また、2級建築施工管理技士では、実務経験のみで受験資格を得られる場合もあります。具体的には、11年以上の実務経験があれば受験が可能です。
実務経験を積むことは、より高度な資格の取得を可能にし、かつ建設業界でのキャリアアップにもつながります。
一般建設業許可と特定建設業許可で必要な資格の違い

建設業を営むうえで欠かせない許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があることを覚えておきましょう。一般建設業許可と特定建設業許可では、専任技術者に求められる資格要件が大きく異なります。
一般建設業許可の場合、10年以上の実務経験や、指定学科を卒業後に一定の実務経験を積めば、専任技術者として認められることがあります。
一方、特定建設業許可では、一級建築士や一級施工管理技士などの国家資格の保有が必須条件です。大規模な工事を元請として請け負う特定建設業には、高度な専門知識と技術力が必要とされるためです。
そのため、特定建設業許可を目指す際は、国家資格の取得が重視されます。
建設業の免許申請において必要な基礎知識

建設業免許の申請においては、以下に関する基礎知識を押さえておくことが大切です。
ここでは、建設業免許の申請に必要な基礎知識について、以下の視点から解説します。
- 許可要件の確認
- 申請書類の準備
- 申請書の提出先
- 審査期間
- 手数料
- 電子申請
ここでは、建設業免許の申請に必要な基礎知識について解説します。
許可要件の確認
建設業の免許を取得するためには、以下に関する要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者
- 建設工事に関する知識・経験を持つ専任技術者
- 誠実性
- 財産的基礎または金銭的信用
- 欠格事由
まず、5年以上の実務経験を有する経営業務の管理責任者を置くことが求められます。さらに、専門知識と実務経験を有した専任技術者を、営業所ごとに配置しなければなりません。
不正行為の可能性がないことも条件であり、過去に法律違反がある場合は許可が下りません。また、請負契約を履行するための財産的な基盤や金銭的な信用に加え、破産者や暴力団員が在籍していないことも重視されます。
以上の要件を満たすかどうか、事前に確認しておきましょう。
申請書類の準備
建設業許可の申請には、必要書類の準備も欠かせません。主な申請書類は以下のとおりです。
- 建設業許可申請書
- 登記事項証明書
- 財務諸表
- 経営業務の管理責任者および専任技術者の経歴書・誓約書
申請書類は正確に記入し、漏れなく添付することが重要です。不備があると申請が却下される可能性があるため、細心の注意を払いましょう。必要に応じて、行政書士などの専門家に相談することも検討してください。
申請書の提出先
申請書の提出先は、営業所の所在地に応じて異なります。
営業所が複数の都道府県に存在する場合は、国土交通大臣へ申請し、本店所在地を管轄する地方整備局長が担当します。一方、1つの都道府県にのみ営業所がある場合は、都道府県知事に提出してください。
事前に、許可行政庁のWebサイトで受付時間や必要な手続きについて確認しておきましょう。
審査期間
建設業許可の審査期間は、通常1ヶ月から3ヶ月程度です。ただし、許可行政庁や申請内容によって変動する可能性があります。審査では、提出された申請書類を基に、許可要件の充足性が厳格にチェックされます。
手数料
建設業許可の申請には、手数料が発生します。金額は、許可行政庁や許可の種類によって異なります。新規申請・更新申請・変更申請などで、手数料が変わる点に注意しましょう。
電子申請
建設業許可は、電子申請システムを利用した申請も可能です。電子申請であれば書類作成の手間が省け、申請書類の提出や手数料の納付もオンラインで完結できます。時間や場所の制約が少なく、効率的な申請が可能になるでしょう。
まとめ
本記事では、建設業の免許に関する基本的な情報を幅広く解説しました。
建設業における免許は、健全な業界の発展と事業運営の適正化を図るうえで、非常に重要な要素となります。免許の取得手続きは複雑で時間がかかることが多いものの、事前にしっかりと準備し、必要な知識を把握しておけば、スムーズに進めることが可能です。
