建設業の休みは他の業種と異なる?現状や業界における週休2日制との関連
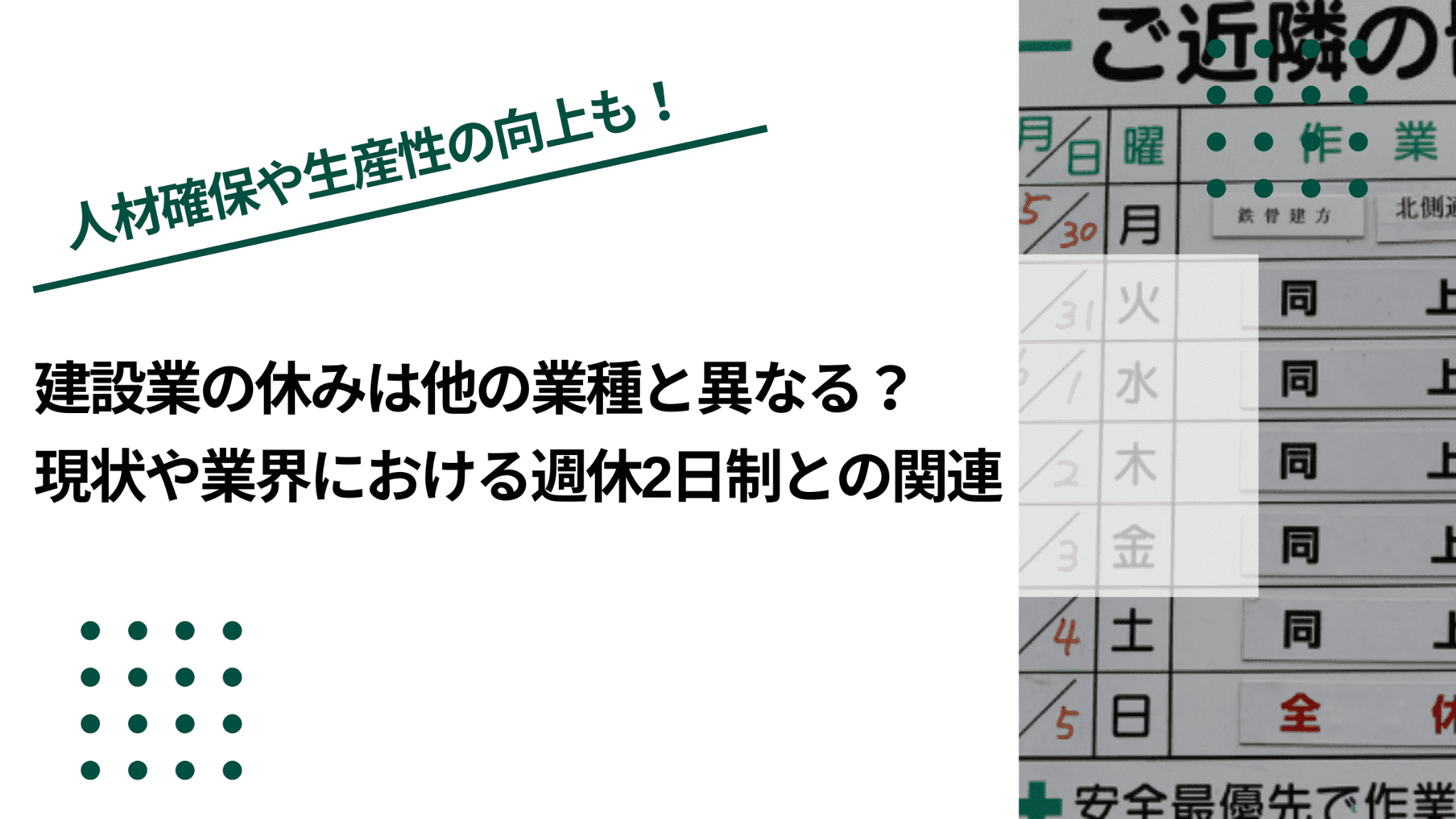
目次
建設業界は一般的なオフィスワークとは異なり、休日に対する独自の考え方が存在する業界です。
現場の進捗状況や工期、顧客からの要望といった多様な要因が絡み合い、休日の取得が左右されることから、労働環境の改善が大きな課題となっています。
本記事では建設業における「休み」の実態を、以下のポイントに分けて解説します。
- 建設業における所定の「休み」とは
- 建設業の休みが少ない理由
- 建設業と「週休2日制」の関係性
建設業に従事する方にとって、休日や休暇を正しく理解することは労働条件の改善や生活の質の向上に直結します。
建設業における所定の「休み」とは

働き方改革の流れを受け、建設業界でも労働時間や休暇に関する法律を正しく理解することが重要になっています。
特に、週休2日制の導入や従来の慣習の見直しが求められる場面が増えています。
ここでは、建設業における「休み」の定義について見ていきましょう。
休日と休暇の違い
建設業界では「休日」と「休暇」という言葉が頻繁に使われます。
しかし、それぞれの違いを正確に把握できていない方もいるでしょう。
法律上の「休日」とは、労働義務のない日を指します。
対して「休暇」は、労働義務があるものの、労働者の請求によって労働が免除される日とされています。
たとえば、お盆や年末年始を休日とするか休暇とするかで賃金計算に影響が出るため、注意が必要です。
所定休日と法定休日の違い
「所定休日」は事業主が独自に定めた休日を指し「法定休日」は労働基準法で定められた最低限の休日を指します。
建設業では、日曜日を法定休日とするケースが多いものの、法律上では特定の曜日を法定休日と規定しているわけではありません。
重要なのは、所定休日が法定休日を必ず含む必要があるという点です。
振替休日と代休
休日出勤が生じた際は「振替休日」または「代休」の制度を利用できます。
振替休日は休日出勤の前に別の日を休日として設定するもので、代休は休日出勤の後に代わりの休日を与える制度です。
どちらを利用するかによって割増賃金の計算が変わるため、適切な運用が求められます。
建設業における一般的な休日設定
建設業界では、多くの企業が日曜日を休日としています。
労働基準法においては週に1日の法定休日が定められていますが、土曜日も休日とする企業はまだ少ないのが現状です。
加えて、年末年始やお盆休みも一般的に休日として設定されています。
建設業の休みが少ない理由

他の業界と比べて建設業の休みが少ない背景には、業界特有の事情や構造的な課題が存在します。
以下で、建設業の休みが少ない理由を詳しく掘り下げましょう。
工期の短さ
建設業では、契約や依頼主の要望に応じて、厳しい工期を守ることが求められます。
中には非常にタイトなスケジュールが組まれる場合もあり、休日を削って作業を進めざるを得ないこともあるでしょう。
また、建設工事は、天候に大きく左右される仕事です。
雨や雪などの悪天候が工事スケジュールを遅延させることも多く、遅れを取り戻すために休日出勤が必要となる場合があります。
人手不足
建設業界は、慢性的な人手不足に悩まされている業界です。
高齢化による労働力の減少や若年層の入職者数の低迷で1人あたりの業務量が増加し、結果として休日を取りづらくなる状況が生まれています。
根強い文化
「長時間労働は当たり前」といった価値観が未だに業界内に根強く残っているのも、建設業で休みが少なくなる理由です。
特にベテラン社員の中には、休日を取ることに対して抵抗感を持つ人も多く、休みの少なさにつながっています。
さらに、企業文化も休暇を取りづらい空気を作り出している要因の一つです。
建設業界には体育会系の雰囲気を持つ企業が多く「休みを減らして働くことが美徳」とされる風潮があります。
請負構造
建設業では、元請け企業から下請け企業へと工事が分配される構造が一般的です。
このため、下請け企業の従業員が自分の担当現場が休みの日でも、他の現場で作業をすることがあり、休日の確保が難しくなりがちです。
工期と比例する経費
休日を増やせば工期が延び、比例して人件費や材料費などの経費が増大します。
コスト増を避けるために工期短縮を優先し、結果的に休日が減るケースがあるのです。
給料が減りがちな日当制による不安
建設作業員の中には日当制で働いている人も多く、休日が増える分収入が減るという懸念があります。
そのため、休日出勤を望む傾向が強くなりがちです。
建設業と「週休2日制」の関係性
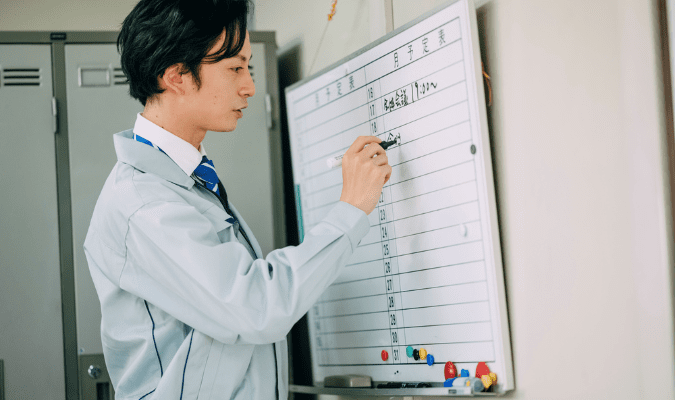
近年、建設業界では週休2日制の導入が大きな課題となっています。
従来の働き方を見直し、労働環境の改善に向けた取り組みが進んでいるのです。
ここでは、建設業における週休2日制の現状と課題について詳しく解説します。
なお、建設業における週休2日制の詳細は、以下の記事でも触れているのでぜひ参考にしてください。
建設業の週休2日はいつから義務化されるのか?週休2日に向けてやるべき5つのこと
従来の建設業で取り入れられていた週休2日制
従来、建設業界で週休2日制を採用している企業は一部に限られていました。
多くの企業では、日曜日のみが休日となる週休1日制が一般的でした。
なぜなら、工期を厳守する必要があるため、休日を増やすことが難しかったのです。
また、日給制で働く作業員が多く、休日が増えることで収入が減少するという問題も影響していました。
建設業で週休2日制が注目された背景
建設業界で週休2日制が注目されるようになった大きな要因の一つに「2024年問題」が挙げられます。
2024年問題は、2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用されることが焦点となっています。
規制により年間360時間(特別条項付きの場合720時間)を超える時間外労働が禁止され、違反には罰則が科されます。
そのため、労働時間を削減するために週休2日制の導入が急務となっているのです。
加えて、建設業界は人材不足と高齢化が進行しており、若い世代の入職を増やすには労働環境の改善が不可欠です。
週休2日制を導入することで、ワークライフバランスの向上や業界のイメージ改善が図られ、人材確保につながると期待されています。
建設業における週休2日制の義務化について
2024年現在、建設業界における週休2日制は法的に義務付けられていません。
しかし、国土交通省は週休2日制の推進に力を入れており、公共工事では週休2日制を導入した企業に労務単価の補正といった優遇措置を実施しています。
結果、公共工事では週休2日制の普及が進んでいますが、民間工事においては導入が遅れているのです。
建設業界全体で週休2日制を定着させるには、企業の取り組みに加え、政府の支援策や社会の理解と協力が不可欠です。
今後もこの課題に向き合い、持続可能な労働環境を整備していくことが重要となるでしょう。
まとめ
建設業界は、工期の厳しさや人手不足といった要因が複雑に絡み合い、他の業種に比べて休日が少ない傾向にあります。
働き方改革や人材確保の観点から、週休2日制の導入は避けて通れない課題となっているのです。
週休2日制を導入することでワークライフバランスが向上するだけでなく、人材確保や生産性の向上といった効果も期待できます。
さらに、業界全体で労働環境の改善に取り組むことで、若手技術者の定着率向上や業務効率化が見込まれます。
今後の建設業においては、従来の慣習に縛られず、柔軟な休日設定を実現するための取り組みが求められるでしょう。
