電気工事業と建設業許可の関係|取得要件や業種としての将来性
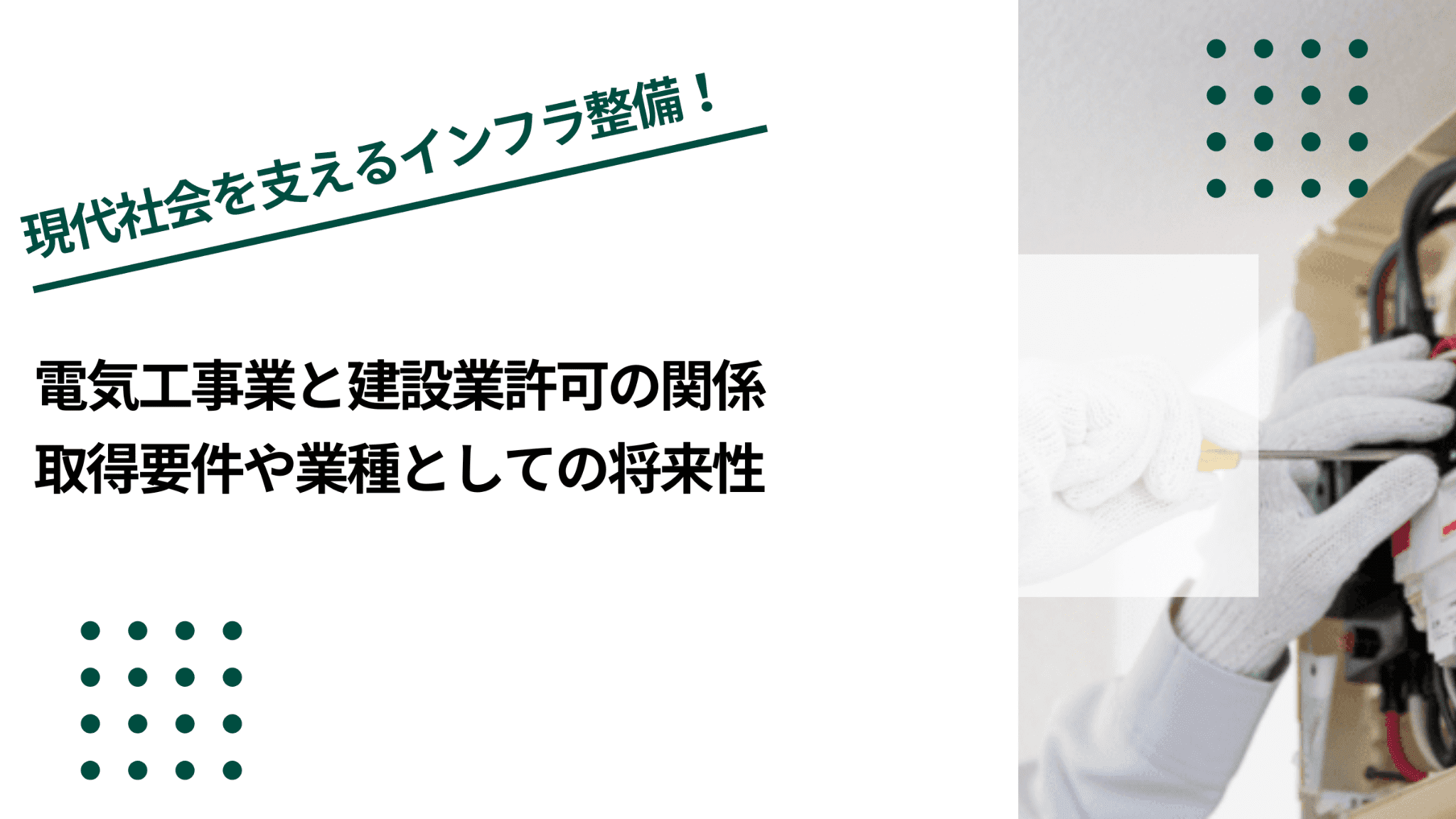
目次
電気工事業は、社会インフラを支える重要な役割を担う建設業の一分野として高い注目を集めています。
しかし、建設業許可の中での電気工事業の扱いや、別途必要とされる電気工事業登録制度など、把握すべき制度が複数あります。
そのため、それぞれの関係性に混乱を感じる方も多いでしょう。
本記事では、電気工事業の基本的な位置づけを確認しつつ、以下の観点について詳しく解説していきます。
- 建設業許可と電気工事業登録の違い
- 電気工事業における建設業許可の取得要件
- 電気工事業登録が必要な場面
- 電気工事業の将来性
なお当サイトでは、電気工事における単価についての詳細も解説しているので、本記事とあわせて参照ください。
電気工事で1人工の単価はどう決める?積算の方法や注意点を解説!
建設業における電気工事業とは

電気工事業は、発電所や変電所、送配電設備といった電気設備の設置を専門に担う分野です。
また、電気工事業には以下の設置も含まれています。
- 照明設備
- 電車線
- 信号設備
- ネオン装置
- 太陽光発電設備
上記から、電気工事業は現代社会に欠かせない電気エネルギーの供給を支えるインフラ整備を行っていることがわかります。
そのため電気工事業は、建設業の中でも特に重要な役割を果たす分野と言えるでしょう。
電気通信工事業・機械器具設置工事業との違い
電気工事業の大きな特徴は「強い電気」を扱う工事である点です。
一方で、電気通信工事業は以下のような情報通信設備にまつわる「弱い電気」を取り扱う工事が中心となります。
- 電話
- インターネット
- テレビ
また、機械器具設置工事業は、多種多様な機械器具の設置工事を包括的に扱う分野です。
機械器具設置工事業では、扱う機械器具によって電気工事や管工事、電気通信工事などと重複する場合があります。
ただし、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事に分類される一方で、太陽光発電設備の設置工事は電気工事に該当するように、該当する専門工事業ごとに区分されるのが一般的です。
建設業許可と電気工事業登録の違い
建設業許可は建設業法に基づき、建設工事を請け負う際に必要な許可です。
特に、500万円以上の電気工事を請け負う場合に取得が求められます。
一方で、電気工事業登録は電気工事業法に基づく制度で、工事金額にかかわらず電気工事を行う際に必要です。
建設業許可を取得している場合は「みなし登録電気工事業者」として認められ、電気工事業登録の手続きが簡略化されます。
つまり、500万円を超える電気工事を請け負う際には建設業許可と電気工事業登録がどちらも求められますが、建設業許可を取得済みであれば電気工事業登録が効率的に進む仕組みになっているのです。
電気工事業における建設業許可の取得要件

電気工事業で建設業許可を取得するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
以下では、特に重視すべき要点について整理します。
経営業務管理責任者の要件
建設業許可を取得する際には、経営業務管理責任者を選任する必要があります。
該当する責任者には、電気工事業に関する十分な知識と経験が求められます。
- 電気工事業を営む会社で5年以上役員として従事
- 電気工事業を個人事業主として5年以上継続
- 電気工事業以外の建設業を営む会社で5年以上役員経験
- 電気工事業以外の建設業を個人事業主として5年以上継続
経営業務管理責任者の要件については、上記を参考にしてください。
専任技術者の要件
電気工事業の建設業許可を取得する際には、営業所ごとに専任技術者を常勤で配置しなければなりません。
専任技術者には電気工事分野における高度な知識や技能が求められ、一般建設業と特定建設業では基準が異なります。
一般建設業の場合、一級電気工事施工管理技士や二級電気工事施工管理技士といった国家資格を有する者、もしくは一定の実務経験を持つ者が該当します。
特定建設業の場合は、一級電気工事施工管理技士をはじめとする高度な国家資格を有する者、あるいは国土交通大臣が同等以上と認める能力保持者が条件です。
なお、電気工事における施工管理の詳細は、以下の記事を参考にしてください。
電気工事の施工管理とは?関連資格「電気工事施工管理技士」の内容や将来性について
財産要件
建設業許可を取得するには、事業を安定して継続可能な財産状況を示す必要があります。
財産要件は、一般建設業と特定建設業で異なることを覚えておきましょう。
一般建設業の場合、直近の決算で自己資本が500万円以上、または500万円以上の預金残高が求められます。
特定建設業の場合は、自己資本4000万円以上が必要とされ、より厳しい基準が設定されています。
実務経験の証明方法
専任技術者の要件を満たすために実務経験を証明する場合は、申請先の行政機関が指定する書類を準備しなければなりません。
たとえば、東京都では工事請負契約書や請求書に加え、入金確認資料が求められる場合があります。
神奈川県では原則として確定申告書で証明しますが、確定申告書で立証できない場合は、工事請負契約書や請求書を含む資料と入金確認資料の提示が求められます。
電気工事業登録が必要な場面

電気工事業登録には「登録電気工事業者」「みなし登録電気工事業者」「通知電気工事業者」「みなし通知電気工事業者」の4種類があり、対応する工事の種類や規模によって求められる登録が異なります。
以下で、それぞれの登録が必須となる具体的な状況を見ていきましょう。
500万円未満の電気工事を施工する場合
材料費込み・税抜きで500万円未満の電気工事を行う場合、基本的には「電気工事業登録」さえ行っていれば問題ありません。
一方、500万円以上の工事に取り組む際は、これに加えて「建設業許可」の取得も必要となる点に注意してください。
一般用電気工事および自家用電気工事を行う場合
「登録電気工事業者」としての登録は、一般用電気工事および自家用電気工事を担当する際に求められます。
- 一般用電気工事:600V以下で受電する電気工作物を扱う工事
- 自家用電気工事:500kW未満の需要設備を対象とする自家用電気工作物の工事
なお、自家用電気工事は第一種電気工事士でなければ施工が許されない点も押さえておきましょう。
自社で電気工事を施工する場合
建設業許可を持つ業者が自社で電気工事を手がける場合には「みなし登録電気工事業者」となります。
注目すべきは、取得している許可が電気工事業以外の建設業許可であっても、みなし登録電気工事業者として扱われることです。
施工できる工事の範囲は、登録電気工事業者の場合と同様です。
自家用電気工事のみを施工する場合
自家用電気工事のみを行う場合は「通知電気工事業者」の登録が必要です。
自家用電気工事のみを施工し、なおかつ建設業許可を取得している場合は、「みなし通知電気工事業者」としての登録が求められます。
電気工事業の将来性について

現代社会において電力の需要は増え続けており、かつ今後も続くことが予想されます。
そのため、電気工事業は将来的にも有望な分野といえるでしょう。
以下では、電気工事業の将来性について解説します。
IoT・次世代通信関連工事の需要増加
近年、IoT(モノのインターネット)や5Gといった最先端のテクノロジーが急速に浸透し始めています。
技術の進化に対応した電気設備の設置やメンテナンス業務の需要は、一段と高まる見込みです。
具体的には、5G基地局の新規設置やスマートビルディングにおける高度なセンサー・制御システムの導入など、多くの電気工事案件が生まれると期待されます。
都市再開発・老朽化対策による安定需要
都市部の再開発や、老朽化した建築物の設備更新にともなう電気工事の需要も、業界を支える大きな柱です。
建物よりも短いサイクルで更新が求められる電気設備は、定期的なメンテナンスや交換が必要となります。
さらに、省エネ対策やEV充電インフラの整備といった新たな需要も加わり、電気工事業界への期待は着実に高まっていると考えられます。
災害復旧・復興工事における重要性
自然災害が多い日本では、災害発生後の復旧・復興工事において電気工事業者が不可欠な存在です。
被災地の電力供給を素早く再開することは、人々の生活再建において最優先課題の一つです。
また、今後はより災害に強い電気設備の構築が求められるため、災害復旧・復興工事の分野でも電気工事業者のスキルが活かされるでしょう。
まとめ
電気工事業は、建設業界の中でも今後の成長が見込まれる分野です。
IoTや次世代通信技術の進展、都市再開発の進行や災害復興における役割など、幅広い市場ニーズに応えるためには高い専門性が欠かせません。
電気工事業における持続的な発展を実現するためには、必要な許可の取得や資格者の育成に加え、技術力の向上が重要なポイントとなります。
本記事を通じて電気工事業への理解を深め、自社もしくは協業先とのプロジェクトを円滑に進行させましょう。
