【2024年版】建設業の平均年収を職種・年齢・企業規模別に解説
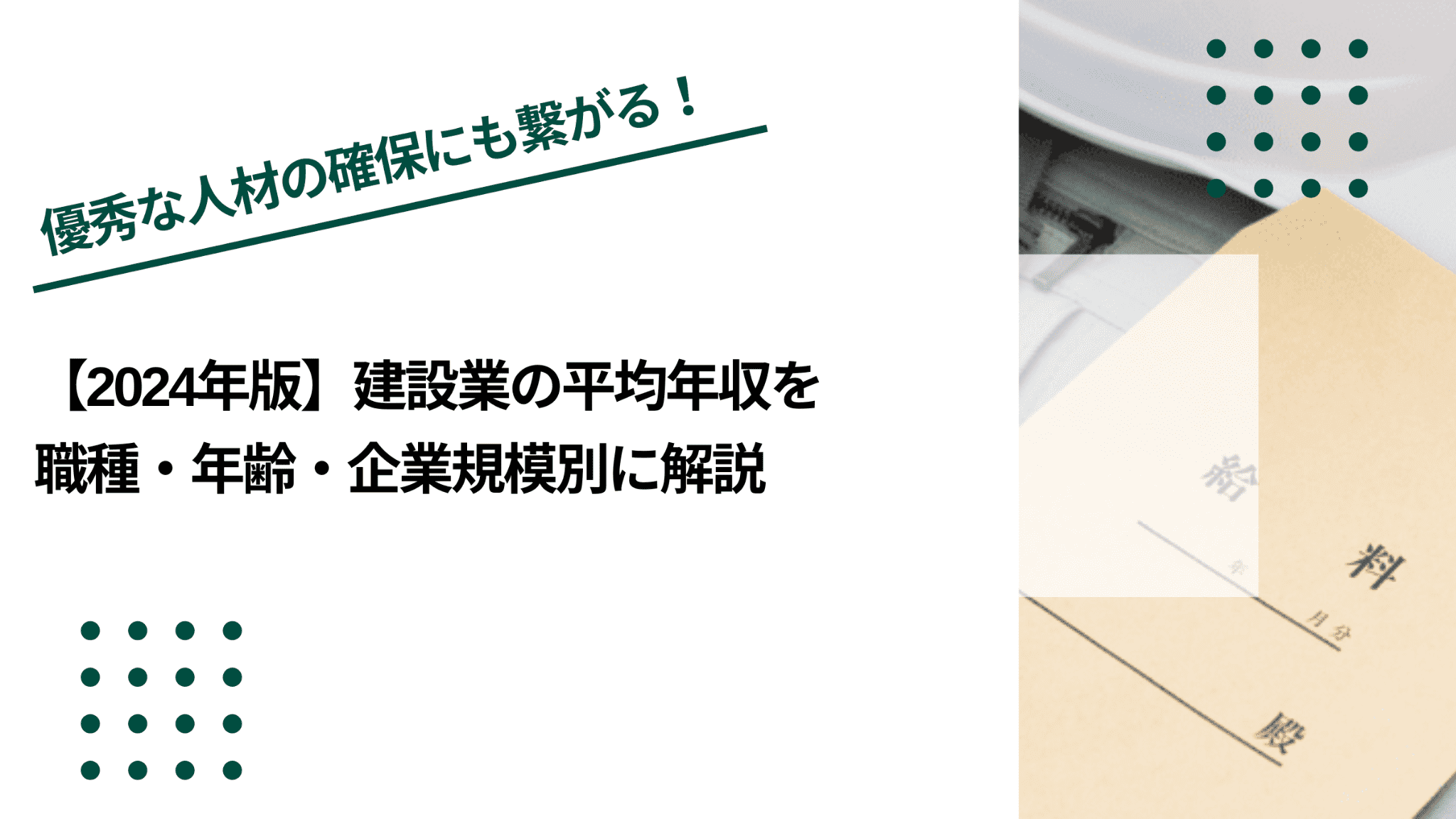
目次
建設業界の平均年収を正しく把握することは、企業が自社の給与体系を見直し、求職者を効果的に募るうえで不可欠です。本記事では、2024年段階の建設業の平均年収について、以下の視点から解説します。
- 他業種との比較
- 年代別の年収
- 職種別の年収
- 企業規模別の年収
さらに、建設業における年収アップのための具体的な方法についても取り上げています。自社の給与体制を改善し、優秀な人材を確保する際の参考に、ぜひ本記事をお役立てください。
【他業種との比較】建設業の平均年収

人材不足が深刻化している建設業界では、優秀な人材を確保するために、給与水準の見直しを迫られています。 ここでは建設業の平均年収について、他業種との比較という視点から解説します。
建設業全体の平均年収
国税庁の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、建設業の平均年収は567万円です。 従業員数10人以上の企業から算出されたデータで、基本給に加えて、以下が含まれています。
- 職務手当
- 精皆勤手当
- 家族手当
- 時間外勤務手当
全産業の平均年収が485万円であるため、 建設業の年収は全産業平均と比較して高い水準にあると言えるでしょう。
他業種と比較した年収の高さ・低さ
建設業の平均年収は全産業平均よりも高水準ですが、業種によってはさらに高い年収を得られる場合があります。 令和1年の民間給与実態統計調査によると、電気・ガス・熱供給・水道業の平均年収は824万円で、全業種の中で最も高くなっています。 また、金融業・保険業も平均年収が627万円で、建設業よりも高めです。
建設業全体の平均年収が高い理由
建設業の平均年収が高い理由にはまず、深刻な人手不足が挙げられます。企業は、人材を確保するために賃金を引き上げているのです。
次に、高度な専門性も年収が高くなる要因です。建設業は技術や知識が重要なため、優秀な人材に高い給与を提示する傾向が強まっています。
最後に、公共工事入札での優位性があります。賃上げを実施している企業が優遇される制度により、多くの企業が賃金を引き上げました。加えて、建設業は景気の影響を受けやすく、好景気時には賃金が上昇しやすい特徴も持ち合わせています。
【年代別】建設業の平均年収

建設業界では、年代によって平均年収が大きく変動します。ここでは、各年代の平均年収と特徴について詳しく解説します。
20代
厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、建設業の20代の平均年収は以下のとおりです。
- 20~24歳:359.5万円
- 25~29歳:461.7万円
20代前半は、建設業界ではまだ経験が浅い段階です。そのため、他の年代と比較すると平均年収の水準が低くなっています。
しかし、20代後半になると、平均年収は461.7万円まで上昇します。30代以降で必要となる資格取得を見据え、20代後半から専門知識やスキルを習得し、昇給や昇格を目指す人が増えることが要因です。
30代
30代になると、建設業では多くの現場で中心的な役割を担うようになります。責任も増してくるため、年収も以下のように上昇傾向にあります。
- 30~34歳:523.9万円
- 35~39歳:566.4万円
30代前半では平均年収が523.9万円に達し、全産業平均を上回ります。30代後半になると、さらに平均年収は566.4万円まで上昇します。なぜなら、30代では多くの従業員がより専門性の高い資格を取得したり、管理職に昇進したりするためです。
40代
40代になると、建設業では豊富な経験と知識を活かして、現場を管理する立場になることが多くなるでしょう。
- 40~44歳:584.7万円
- 45~49歳:632.3万円
40代は多くの社員が現場監督や管理職などの重要なポジションに就く年代であるため、上記のような高い収入を得られるようになるのです。特に40代後半は、平均年収が600万円を超えることも珍しくありません。
50・60代
50代以降の建設業の平均年収は、次のとおりです。
- 50~54歳:695.1万円
- 55~59歳:696.6万円
- 60~64歳:549.3万円
50代前半から後半にかけては、建設業で最も高い年収水準となります。長年の経験と知識を活かし、高度な管理業務や指導的な役割を担うためです。
しかし、60代になると定年退職や再雇用の影響で年収は減少傾向にあります。それでも60代前半までは、全産業平均を上回る水準を維持しているのが特徴です。
【職種別】建設業の平均年収

ここでは、建設業における代表的な職種の平均年収について、それぞれ詳しく解説します。
- 一級建築士
- 技術士
- 掘削作業主任者・発破技士
- 電気工
- 測量技術者
- 配管工
- 鉄工
- 玉掛け作業員
建設業では、職種によって求められる専門性や責任の度合いが異なり、比例して年収にも差が生じます。
一級建築士
一級建築士は、建築物の設計や工事監理が可能になる国家資格で、建設業界において最も高い専門性と地位を持つ職種の一つです。建物の規模や用途に制限がなく、あらゆる建築物を設計できます。そのため、一級建築士の平均年収は630万円と高額です。
技術士
建設部門の技術士の平均年収は、615万円です。科学技術に関する高度な専門知識と応用能力を持つ技術者を認定する国家資格であり、土木・建築・環境など幅広い分野における以下を担当します。
- 計画
- 設計
- 施工
- 管理
高度な専門性が求められるため、高収入につながっています。
掘削作業主任者・発破技士
掘削作業主任者や発破技士は、建設現場で掘削や発破作業を安全に行うために取得が必要な国家資格です。特に、土木工事やトンネル工事といった大規模な現場で欠かせません。収入の面でも高水準を誇り、2019年のデータでは平均年収は564万円ほどとなっています。危険を伴う業務であり、専門性が非常に高いことから、責任の重さが報酬の高さに反映されていると言えるでしょう。
電気工
電気工の平均年収は、約550万円となっています。職務内容としては、建物の電気設備や配線に関する工事が挙げられ、電気工事士という国家資格が必要です。電気工事士の資格には第一種と第二種の2種類があり、建設業に限らず鉄道の運行に必要な電気工事など、さまざまな分野で活躍する機会があります。専門性の高さと需要の増加が、安定した高収入につながる要因です。
測量技術者
測量技術者は、建設工事を始める前に、土地の位置や形状を正確に測定する役割を担っています。国家資格である測量士が必要な職種で、測量法に基づいた業務を遂行することが求められます。平均年収は、約466万円ほどです。
配管工
配管工は、建物内の水道管やガス管、排水管の工事を担当する職種です。配管は建物のライフラインを支える重要な要素であるため、高い技術力と精度が求められます。配管工の平均年収は418万円となっており、需要の高い職種であると言えるでしょう。
鉄工
鉄工の平均年収は367万円で、鉄骨や鋼材を加工して建築物や橋梁などの構造物を作り上げる仕事です。建物の骨組みを形成するという非常に重要な役割を担っており、技術力と豊富な経験が求められます。
玉掛け作業員
玉掛け作業員はクレーンなどの揚重機を使用して、資材や重量物を吊り上げる作業に従事します。安全に重量物を吊り上げるには、専門的な知識と技術が不可欠であり、玉掛け技能講習の受講が義務付けられています。玉掛け作業員の平均年収は、370万円です。
【企業規模別】建設業の平均年収
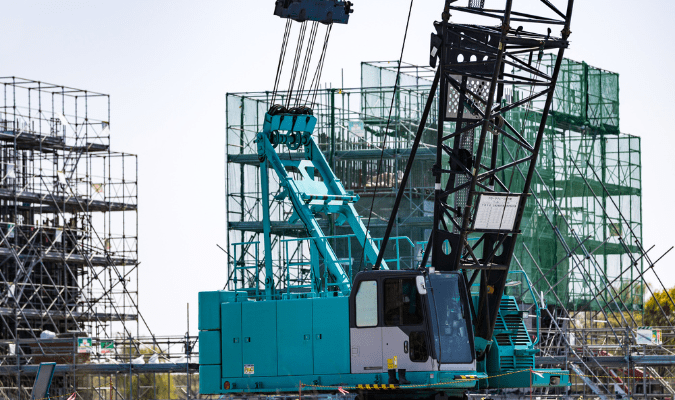
以下では、企業規模別に平均年収の特徴を解説します。
- スーパーゼネコン
- 準大手ゼネコン
- 中堅・地場ゼネコン
建設業の平均年収は、企業の規模によっても大きく異なります。一般的に、企業規模が大きいほど事業の幅も広くなり、従業員の待遇も向上する傾向にあるでしょう。
スーパーゼネコン
スーパーゼネコンは、日本を代表する大手建設企業で、売上高が1兆円を超える規模があります。平均年収が900万円から1,100万円と高水準であり、福利厚生も充実しているのが特徴です。代表例として、以下が挙げられます。
- 大林組
- 鹿島建設
- 清水建設
- 竹中工務店
- 大成建設
大規模プロジェクトに携わる機会が多く、技術力の向上やキャリアアップを目指す方にとって魅力的な環境です。
準大手ゼネコン
準大手ゼネコンは売上高が3,000億円以上の建設企業を指し、長谷工コーポレーションやフジタ、五洋建設や戸田建設、前田建設工業などが含まれます。平均年収は800万円から900万円程度で、スーパーゼネコンに次ぐ高い給与水準です。特定の分野で強みを持つ企業も多く、専門性を磨きたい方に適しています。
中堅・地場ゼネコン
中堅ゼネコンや地場ゼネコンは、地域に密着した事業展開を行う企業で、主に以下が挙げられます。
- 奥村組
- 鴻池組
- 東亜建設工業
- 福田組
- 大豊建設
平均年収は700万円から800万円程度で、地域のニーズに応えることで安定した業績を維持しています。
企業規模と年収の関係性
建設業では企業規模が大きくなるほど、平均年収が高くなる傾向にあります。大企業が多くの資本や人材を活用して大規模プロジェクトを遂行し、高い利益を上げているためです。しかし、中小企業でも独自の技術や専門性で高収益を実現している場合もあります。
建設業で年収を上げる方法
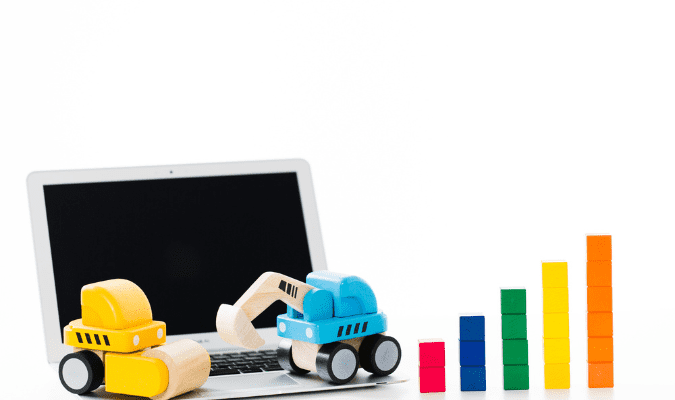
ここでは、建設業で年収を上げるために効果的な以下4つの方法について解説していきます。
- 資格取得
- キャリアアップ
- 独立
従業員の福利厚生を整えるヒントにもなり得るため、ぜひ参考にしてください。
資格取得
資格取得は、年収アップに直結する効果的な方法です。建設業では専門的な資格を取得することで、高度な業務や責任あるポジションに就く機会が増えます。一級建築士や施工管理技士の資格を取得すれば、プロジェクトのリーダーとして活躍できるでしょう。結果、給与や待遇の向上につながります。
キャリアアップ
キャリアアップによって、年収を大幅に増やすことも可能です。経験を積み重ねて現場監督やマネージャーなど上位の役職に就くことで、責任も増えますが報酬も高くなります。また、専門分野のスキルを磨きスペシャリストとして評価されれば、さらに高い収入を得ることにつながるでしょう。
独立
建設業界では、自分の会社を立ち上げて独立する人も少なくありません。独立すれば、自らの判断で業務を進められ、収入を大幅にアップできる場合があります。独立の大きなメリットは、顧客と直接契約を結ぶことで中間マージンを省き、より高い報酬を得られる点です。しかし、独立には事業計画の策定や資金の確保、顧客の開拓といった多くのハードルがあります。
まとめ
本記事では、建設業界の平均年収について多面的な視点から解説しました。建設業は他業種と比較しても高めの年収が特徴ですが、職種や年齢、さらには企業規模によっても大きな違いが見られます。
自社の給与体系を見直す際は、本記事で解説した情報を参考にするとともに、従業員のスキルアップやキャリア成長を後押しする制度の導入を検討することで、企業全体の成長が実現しやすくなるでしょう。
