【建設業】36協定の特別条項における記載例
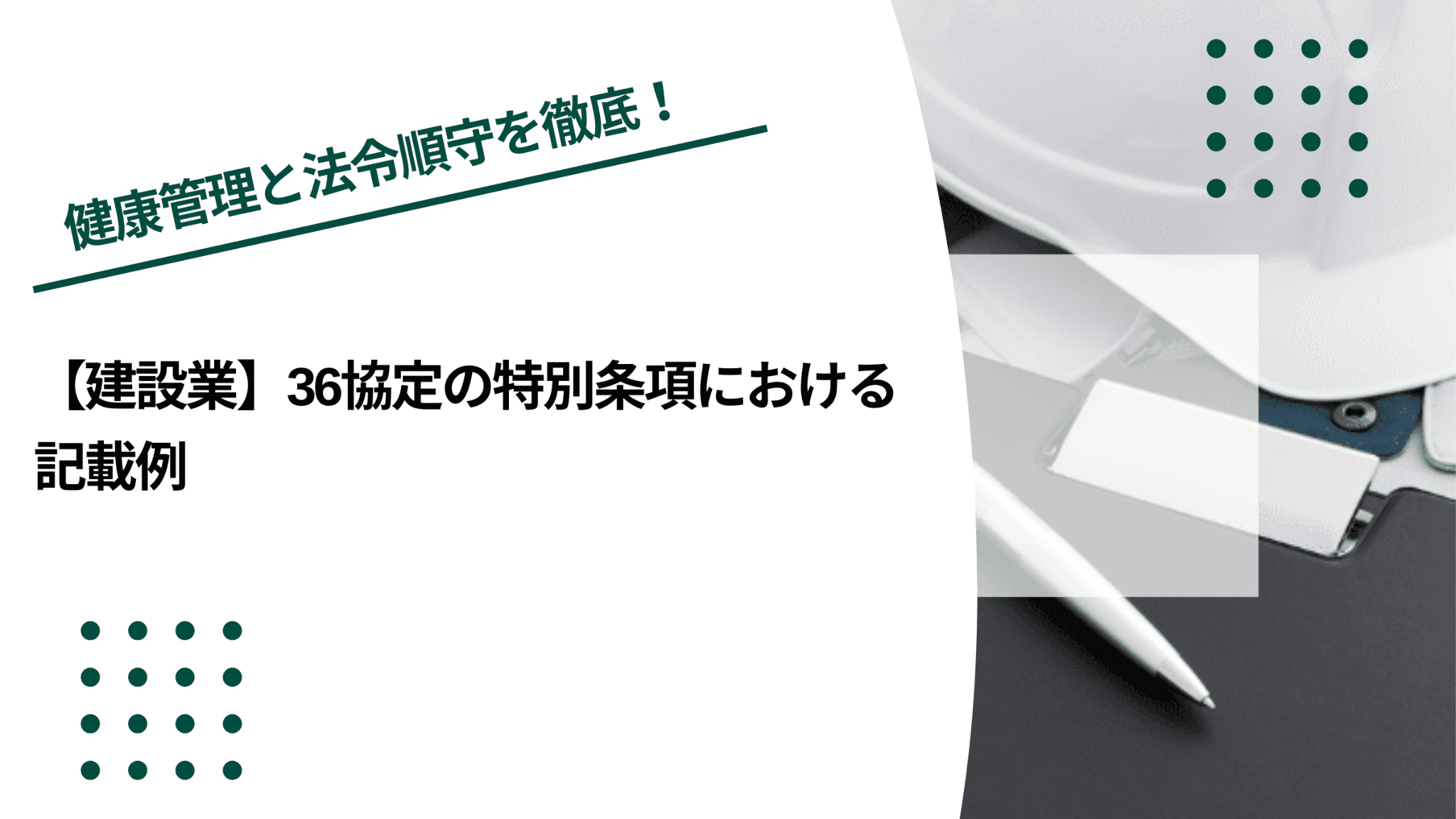
目次
建設業では、工期の遅れや突発的なトラブルにより時間外労働が避けられない場面が多くあります。
「36協定」は、時間外労働を適正に管理するために必要です。
特に、限度時間を超えた労働を認める「特別条項」は、一定の条件のもとで活用できます。
本記事では、36協定の特別条項の仕組みや適用条件、具体的な記載例を紹介します。
建設業における適切な労務管理のために、特別条項をどのように活用すべきかを詳しく解説するのでぜひ参考までにご覧ください。
そもそも「36協定」とは

36協定とは、法定労働時間を超えて労働をさせるために、企業と従業員の間で締結する協定です。
事前に協定を結び、労働基準監督署に届け出ることで、法律の範囲内で時間外労働が可能になります。
日本の労働基準法では、1日8時間・週40時間の労働が原則とされています。
しかし、業務の都合でそれ以上の労働が必要になる場合、36協定の締結が不可欠です。
特に建設業では、工期の遅れや突発的なトラブルに対応するため、時間外労働が発生しやすいでしょう。
そのため多くの企業がこの協定を活用し、適正な運用を行っています。
36協定に関する詳細は、以下の記事も参考にしてください。
建設業における36協定の現状とは?働き方改革を促進する方法も解説
建設業において36協定が適用除外となるケースは?適用外となる業務も解説
建設業36協定の特別条項とは

建設業では業務の特性上、突発的な工期変更や天候の影響により長時間労働が避けられないことがあります。
そのため、通常の36協定に加え、特別条項を設定することで、限度時間を超えた時間外労働を認める仕組みが用意されています。
ただし、適用には厳格な条件があり、無制限に残業をさせることは不可能です。
ここでは、特別条項の基本的な仕組みや適用条件、実際の活用方法について詳しく解説します。
一般条項との違い
36協定には「一般条項」と「特別条項」の2種類があり、それぞれ適用条件が異なります。
一般条項では、時間外労働は月45時間・年360時間が上限とされ、計画的な労働管理が求められます。
一方、特別条項は突発的な業務増加や納期厳守が必要な場合に適用され、年間720時間以内、月100時間未満などの制限が設けられています。
特別条項を適用するには、労働者の代表との合意を得たうえで労働基準監督署へ届け出る必要があります。
また、健康診断や勤務間インターバルの確保など、長時間労働のリスクを軽減する措置も求められるでしょう。
企業は、業務の状況に応じて適切な条項を選択し、法令を遵守しながら労働環境を整えることが重要です。
特別条項が必要とされる背景
建設業では天候不順や資材の納品遅れ、突発的な設計変更など、計画通りに工事が進まないケースが多くあります。
そのため、限度時間を超える残業が避けられない場面も出てきます。
しかし通常の36協定では、月45時間・年360時間の時間外労働が上限とされており、この範囲を超えて働かせることは認められていません。
こうした事情を踏まえ、特別条項付きの36協定が活用されます。
特別条項を設定することで一時的に限度時間を超えた労働が可能となりますが、そのためには労使間で明確な合意を取り、労働基準監督署への届け出を行わなければなりません。
無計画な長時間労働を防ぐためにも、特別条項の適用範囲やルールを十分理解しておくことが求められるでしょう。
36協定の特別条項に定められる条件
特別条項を設ける場合、どの企業でも自由に時間外労働を設定できるわけではありません。
法律上、特別条項を適用できるのは「臨時的な特別な事情」が発生した場合に限られます。
「臨時的な特別な事情」とは、予測が難しい突発的な業務の増加や、納期を厳守しなければならない状況などが該当します。
また、特別条項を設ける際には、労働時間の上限にも制約があることも覚えておきましょう。
- 年間720時間以内
- 月100時間未満
- 2~6か月の平均で80時間以内
基本的に、上記を超える残業は認められません。
さらに、特別条項を適用できるのは年6回までとされており、常態的に長時間労働が続くような運用は違法となります。
このため、建設業の現場では特別条項の導入に際し、綿密な労務管理が必要とされます。
特別条項を適用する際の実務的なポイント
特別条項を締結する際は、企業と労働者の双方が納得できる形で合意を形成することが重要です。
具体的には、まず労働者の代表を選出し、特別条項の必要性や適用条件について説明したうえで合意を得る必要があります。
その後協定書を作成し、労働基準監督署へ届け出を行います。
加えて、特別条項を適用する場合には、労働者の健康と安全を確保するための措置を講じることが重要です。
- 長時間労働が続かないよう定期的な健康診断を実施する
- 勤務間インターバルを確保する
上記のように、適切な配慮を行う必要があります。
これらの取り組みを怠ると、企業としての信頼を損なうだけでなく、行政指導や罰則の対象となる可能性もあるため注意が必要です。
36協定の特別条項を活用する際の注意点
特別条項を適用することで短期間の業務増加に対応しやすくなりますが、常に適用する前提で運用することは認められていません。
特別条項の対象となる業務が本当に「臨時的な特別な事情」に該当するのか、慎重に判断することが重要です。
また、労働基準監督署への届出が適正に行われているか、企業として定期的にチェックすることも求められます。
不適切な運用が発覚した場合、企業には罰則が科せられるだけでなく、社会的信用を失うリスクもあります。
そのため、特別条項を活用する際は、必要性を慎重に検討し、適切な管理体制を整えることが不可欠です。
【パターン別】36協定の特別条項の記載例
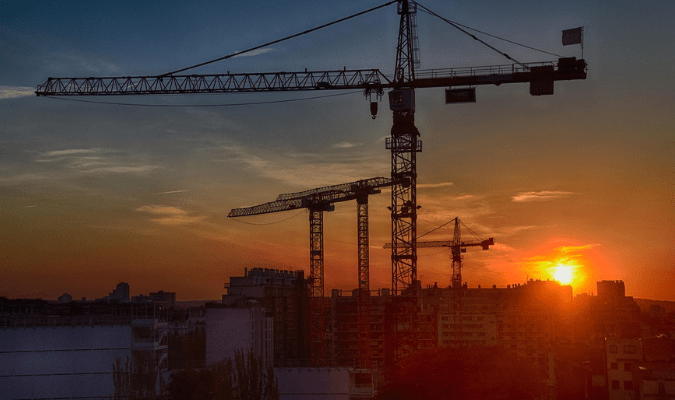
建設業における36協定の特別条項は、業務の特性に応じた適用が求められます。
工期の遅れや突発的な業務増加など、状況によって記載内容が異なります。
ここでは、さまざまなケースに対応した特別条項の記載例を紹介し、それぞれのポイントを詳しく解説するのでぜひ参考にしてください。
短期間の業務集中が予測される場合の記載例
一定の期間に業務量が増える場合、特別条項を活用することで効率的な労働管理が可能になります。
例えば、大型工事の最終工程で突貫作業が必要な場合、従業員に一時的な長時間労働を求めることがあります。
このようなケースでは、以下のような具体的な記載が必要です。
業務の繁忙期における納期厳守のため、臨時的に時間外労働を実施する |
ただし、特別条項が適用されるのは年間6回までであり、上限を超えた運用は認められません。
企業は、計画的に特別条項を活用し、過度な負担が発生しないよう管理することが重要です。
突発的なトラブル対応を想定した記載例
建設現場では機械の故障や天候不良による作業遅延など、予期せぬトラブルが発生することがあります。
こうした場合、短期間での集中的な作業が求められるため、特別条項を活用する必要があります。
特別条項には、以下の文言を明記することが適切です。
設備の故障や天候の影響により工事が遅延した際、復旧作業を迅速に行うため、臨時的に時間外労働を実施する |
加えて、過労防止のための対策として、適切な休息時間の確保や健康管理措置を記載しておくと、労使双方にとってより明確な取り決めとなります。
工期変更による残業対応の記載例
発注者の都合や設計変更などにより、工期が急遽変更されることがあります。
このような場合、納期を守るために特別条項を適用し、時間外労働を実施するケースが考えられます。
協定書には、以下の記載が必要です。
発注者の要求により工期が短縮された場合、工程を遅延なく進めるために時間外労働を行う |
ただし、労働基準法の上限規制を超えないよう、年間720時間以内・月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内の制約を遵守することが求められます。
適切な運用を行わないと、行政指導の対象となる可能性があるため、慎重な管理が必要です。
災害復旧に伴う緊急対応の記載例
地震や台風などの自然災害が発生した場合、建設業では復旧作業にあたることが求められます。
このような状況でも特別条項を適用し、労働時間を一時的に延長することが認められます。
記載例としては、以下のとおりです。
災害発生時において、社会インフラの復旧作業を速やかに進めるため、臨時的に時間外労働を実施する |
ただし、労働者の安全確保が最優先されるため、過重労働にならないよう十分な配慮が必要です。
具体的には、交代勤務の導入や休息時間の確保といった対策を明記することで、安全な労働環境を維持できます。
まとめ
36協定の特別条項は、建設業において突発的な業務増加や納期厳守の必要がある場合に有効な手段です。
ただし、年間720時間以内や月100時間未満などの上限が設けられ、適用には慎重な判断が求められます。
適切な記載例を参考にしながら、労働者の健康管理と法令順守を徹底することが重要です。
特別条項を適切に運用することで、企業の信頼を守りつつ、柔軟な労務管理を実現しましょう。
