【建設業向け】 特別教育一覧|必要性や実施方法について
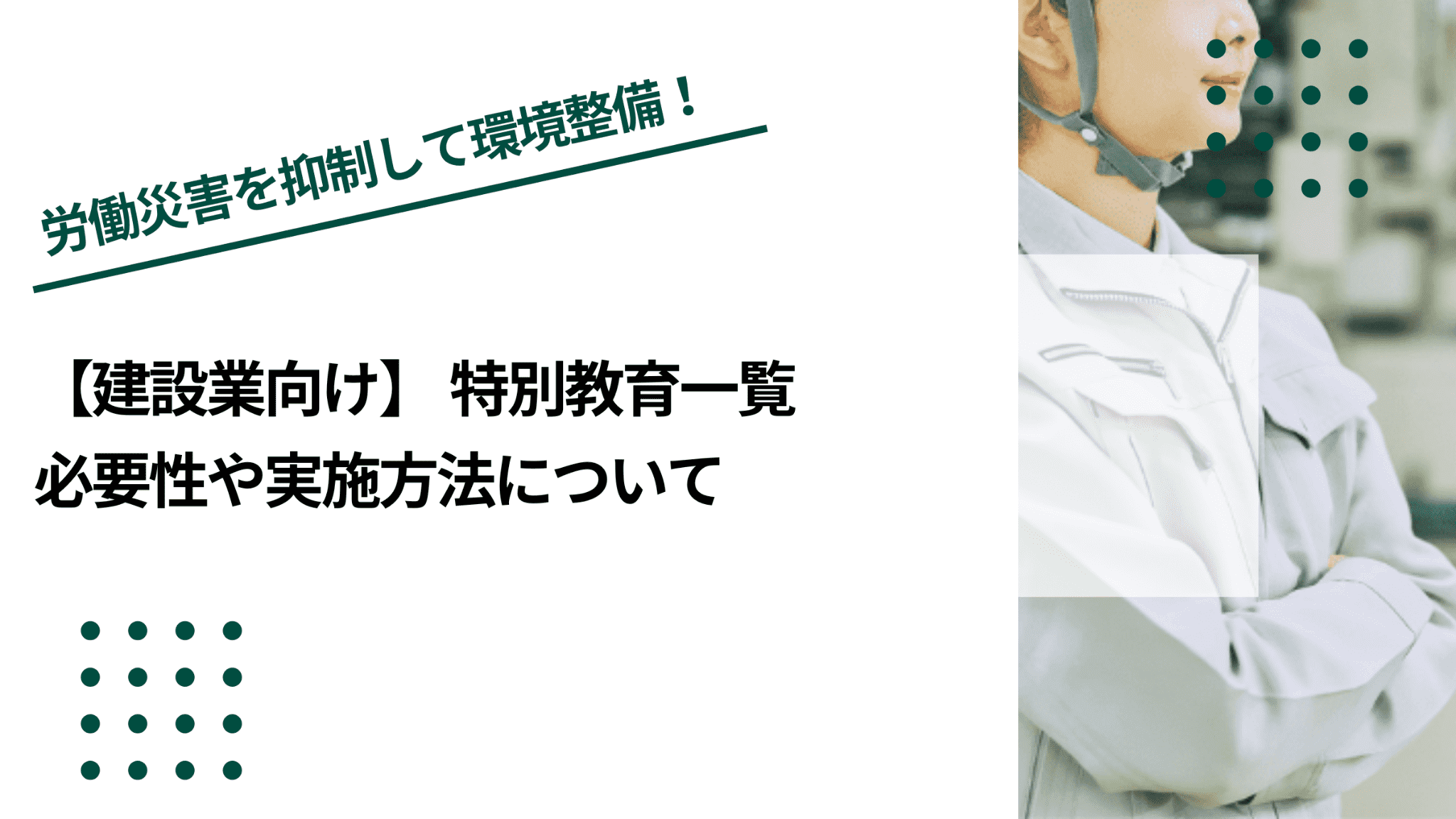
目次
建設業に携わる労働者の安全を確保し、企業としての責任を全うするためには、特別教育が不可欠です。本記事では、建設業における特別教育について、以下の観点から詳しく解説します。
- 特別教育の概要や必要性
- 特別教育に関する労働者・事業者のメリット
- 建設業で必要な特別教育一覧
- 特別教育の実施方法
安全かつ生産性の高い職場環境を構築するために、特別教育の重要性を理解し、適切な実施方法を学んでいきましょう。
特別教育とは

特別教育とは、労働安全衛生法で定められた安全衛生教育の一種です。危険または有害な業務に従事する労働者の労働災害や健康被害を防止するために、事業者が実施します。
例えば、建設業ではクレーン運転や高所作業車運転、アーク溶接など、多くの業務が特別教育の対象です。特別教育を通じて、事業者自身も安全管理の意識を高めることが求められています。
建設業における特別教育の必要性

建設業は他の業種に比べて労働災害の発生率が高く、特に死亡事故の割合が突出しています。特別教育は、業務従事中に発生するさまざまな危険を防止するために不可欠です。
労働者に危険作業の知識や安全対策の技能を習得させることで、安全意識を高める効果があります。特別教育の実施は、自身と周囲の安全を守るための重要な取り組みと言えるでしょう。
特別教育を受講する労働者側のメリット

特別教育を受講すると、労働者は自身の安全と健康を守るための知識と技能を身につけられます。ここでは、特別教育を受講する労働者側のメリットを以下の視点から解説します。
- 安全に業務を遂行するための知識と技能を習得できる
- 就業制限業務に従事できるようになる
労働者側のメリットを把握しておくことは、事業者として特別教育の重要性を理解するきっかけになるでしょう。
安全に業務を遂行するための知識と技能を習得できる
特別教育は、業務に潜む危険性や安全な作業手順、保護具の正しい使用方法などを学ぶ機会になります。労働安全衛生法第59条3項において、事業者は労働者が安全かつ健康に業務を遂行できるよう、必要な知識と技能を習得させる義務があるとされています。
特別教育を受けることで、労働者は法律で定められた安全基準を理解し、安全な作業方法を身につけられ、結果として労働者自身の安全を守ることにつながるのです。
就業制限業務に従事できるようになる
労働安全衛生法第61条では就業制限が設けられており、一定の危険有害業務には、特別な資格を持たない労働者を就業させることが禁止されています。
特別教育を受講し修了することで、就業制限業務に従事することが可能になります。つまり特別教育は、労働者にとってキャリアアップの道を開き、より多くの業務に携わるチャンスをもたらすと言えるでしょう。
特別教育を取り入れる事業者側のメリット

特別教育は労働者だけでなく、事業者側にも以下のメリットをもたらします。
- 労働災害の発生を抑制できる
- 企業の社会的責任を果たせる
- 生産性の向上につながる
ここで紹介するメリットを踏まえ、改めて特別教育の重要性を理解しましょう。
労働災害の発生を抑制できる
特別教育を導入することで、労働災害の発生を抑制できます。労働者が危険な作業に関する正しい知識と安全な手順を身につけられ、安全意識が向上するためです。
例えば高所作業や重機の操作では、適切な教育を受けることで事故のリスクを大幅に軽減できます。結果として、人的損失の軽減や企業の信頼性向上につながります。
企業の社会的責任を果たせる
特別教育の実施は、企業が社会的責任を果たすうえで不可欠です。なぜなら、労働者の安全と健康を守ることは企業の基本的な義務であり、法律でも求められているためです。
労働安全衛生法に基づいて適切な教育を行うことで、法的義務を遵守し、社会からの信頼を得られるでしょう。企業イメージの向上や、ステークホルダーからの支持を得ることにもつながるでしょう。
生産性の向上につながる
特別教育を実施することで、労働者が安全かつ効率的に作業を行えるようになるため、生産性の向上も期待できます。安全な作業手順を習得することで、無駄な動きを減らし作業効率を高められます。
労働災害の減少と合わせた、企業全体の生産性向上につながるのが特別教育のメリットです。
建設業で必要な特別教育一覧

建設現場には多くの潜在的な危険が存在し、安全を確保するためには適切な教育が欠かせません。そのため、労働安全衛生法において、特定の危険または有害な業務に従事する労働者に対し、事業者が特別教育を実施することを義務付けているのです。
建設業の現場で安全に作業を行うための特別教育として、以下のようなものが挙げられます。
- アーク溶接特別教育:アーク溶接機を使用する際に必要な、安全な作業方法や関連法令を学べる
- クレーン運転特別教育:クレーンを運転する際に必要な知識や技能を習得できるつり上げ荷重やクレーンの種類によって、必要な教育内容が異なります。
- 移動式クレーン運転特別教育:移動式クレーンを運転するために必要な知識や技能を学べる
- 玉掛け特別教育:クレーン等を用いて玉掛け作業を行う際に必要な知識や技能を習得できる
- フォークリフト運転特別教育:フォークリフトを運転する際に必要な知識や技能を学べる
- ショベルローダー等運転特別教育:ショベルローダーなどを安全に運転するために必要な知識や技能を習得できる
- 高所作業車運転特別教育:高所作業車を運転する際に必要な知識や技能を学べる
- 不整地運搬車運転特別教育:不整地運搬車を運転するために必要な知識や技能を学べる
- 揚貨装置運転特別教育:揚貨装置を運転するために必要な知識や技能を学べる
- 巻上げ機運転特別教育:巻上げ機を運転するために必要な知識や技能を学べる
- 低圧電気取扱特別教育:低圧の電気を取り扱う際に必要な知識や技能を習得できる
- 自由研削といし取替試運転作業者特別教育:研削といしを取り扱う際に必要な知識や技能を習得できる
- 動力プレス業務特別教育:動力プレスの金型等の取付け、取外し、調整の業務に従事する際に必要な知識や技能を学べる
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育:酸素欠乏・硫化水素が発生する可能性のある場所で作業する際に必要な知識や技能を学べる
- 石綿作業従事者特別教育:石綿取扱い作業に従事する際に必要な知識や技能を習得できる
- ダイオキシン類作業従事者特別教育:ダイオキシン類取扱い作業に従事する際に必要な知識や技能を習得できる
- 粉じん作業特別教育:粉じんが発生する作業に従事する際に必要な知識や技能を学べる
- 丸のこ等取扱作業従事者教育:丸のこ等を取り扱う際に必要な知識や技能を習得できる
- 振動工具取扱作業者安全衛生教育:振動工具を取り扱う際に必要な知識や技能を習得できる
- 刈払機取扱作業者安全衛生教育:刈払機を取り扱う際に必要な知識や技能を習得できる
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育:フルハーネス型墜落制止用器具を使用する際に必要な知識や技能を習得できる
- 足場組立等特別教育:足場の組立て、解体、変更の作業に従事する際に必要な知識や技能を学べる
- 職長教育:職長として必要な知識や技能を習得できる
特別教育と技能講習・免許との違い
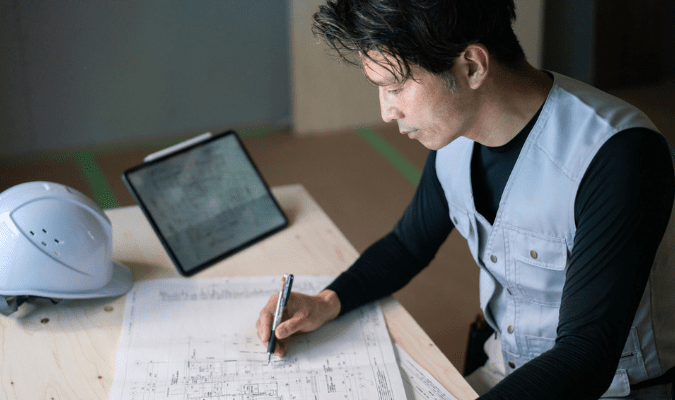
特別教育と混在しやすい技能講習・免許との違いは、資格の有無や義務の対象などが挙げられます。
特別教育
特別教育は、事業者が労働者に対して行う安全衛生教育です。危険や有害な業務に従事させる際に必要とされますが、資格取得ではありません。
特別教育自体は社内で実施可能です。修了証の発行義務はありませんが、教育記録を3年間保存する必要があります。
労働者の安全意識を高め、労働災害を防ぐための基本的な教育と言えるでしょう。
技能講習
技能講習は、都道府県労働局長の登録を受けた機関が実施する講習で、修了すると資格を取得できます。特に危険度の高い業務や、作業主任者として労働者を指揮管理するために必要です。
修了者には「技能講習修了証明書」が交付され、法律で定められた資格を有することになります。より専門的な知識と技能を身につけるための教育と言えるでしょう。
免許
免許は、国家試験に合格して取得する国家資格です。技能講習や特別教育よりも高度な専門知識と技能が求められます。
例えば、ボイラー技士やクレーン・デリック運転士などが該当します。免許を取得すると、法律で規定された業務を行うことが可能になり、同種の特別教育や技能講習の業務を実施することも可能です。
特別教育の実施方法

特別教育の実施方法は、自社で行うか外部機関に委託する場合の2つがあります。それぞれの方法にはメリットがあり、企業の状況やニーズに応じて選択することが重要です。
適切な実施方法を選ぶことで、労働者の安全意識を高め、労働災害の防止につなげられるでしょう。
自社で実施する場合
自社で特別教育を実施する場合、教育内容を自社の業務に合わせてカスタマイズできます。自社の現場で直面する、具体的な危険や課題を取り入れられるためです。
例えば、特定の機械操作や現場特有の安全対策を詳しく教えることが可能です。結果、労働者が実務に直結した知識を身につけられ、安全な作業が期待できます。
また、教育のスケジュールを柔軟に調整できる点も、自社で実施するメリットです。
外部機関に委託する場合
特別教育を外部機関に委託する場合、専門的な知識と経験を持つ講師から質の高い教育を受けられます。なぜなら、外部機関は最新の法令や業界の動向を踏まえた教育プログラムを提供しているためです。
労働安全衛生協会や建設業労働災害防止協会などの機関では、標準化された教材と設備が整っています。労働者は高度な知識を習得し、企業としても教育の手間を省けるでしょう。
さらに、自社で講師や教材を用意する必要がないため、効率的に教育を実施できます。
特別教育に関するよくある質問
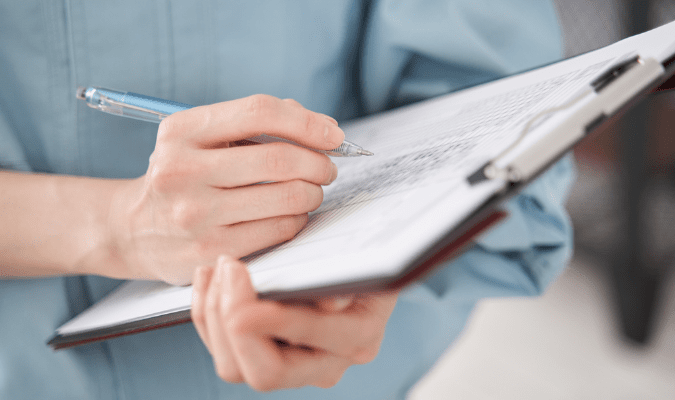
ここでは、特別教育に関するよくある質問に回答をしています。
特別教育の有効期限は?
特別教育には法律上の有効期限は設けられていません。一度受講すれば、その後も該当する業務に従事できます。
しかし、労働安全衛生法第60条の2では、機械設備の変更や技術の進歩に伴い、定期的な安全衛生教育の実施が求められています。法的な期限はないものの、安全性向上のために再教育は欠かせません。
したがって、企業としては定期的な再教育を行うことが望ましいでしょう。
特別教育の記録はどうすれば良い?
特別教育を実施した場合、受講者や教育内容を明確にするために一定の記録を作成し保存する義務があります。具体的な記録項目は、以下のとおりです。
- 受講者の氏名
- 受講年月日
- 教育内容(科目など)
- 講師名
また、保存した記録に関しては3年間保存しなければなりません。記録を適切に管理することは、法令遵守と安全管理の両面でメリットがあります。
まとめ
建設業における特別教育は、労働者の安全を確保し、企業の社会的責任を果たすうえで欠かせないものです。特別教育を適切に実施することで、労働災害の防止や生産性の向上など、多くのメリットが期待できます。
実施方法は、自社内での実施や外部機関への委託など、状況に応じて柔軟に選択可能です。労働者の安全と企業の成長のために、特別教育の導入や見直しを検討してみましょう。
