建設業者の決算報告とは?提出書類の一覧や提出しなかった場合の問題などを解説!
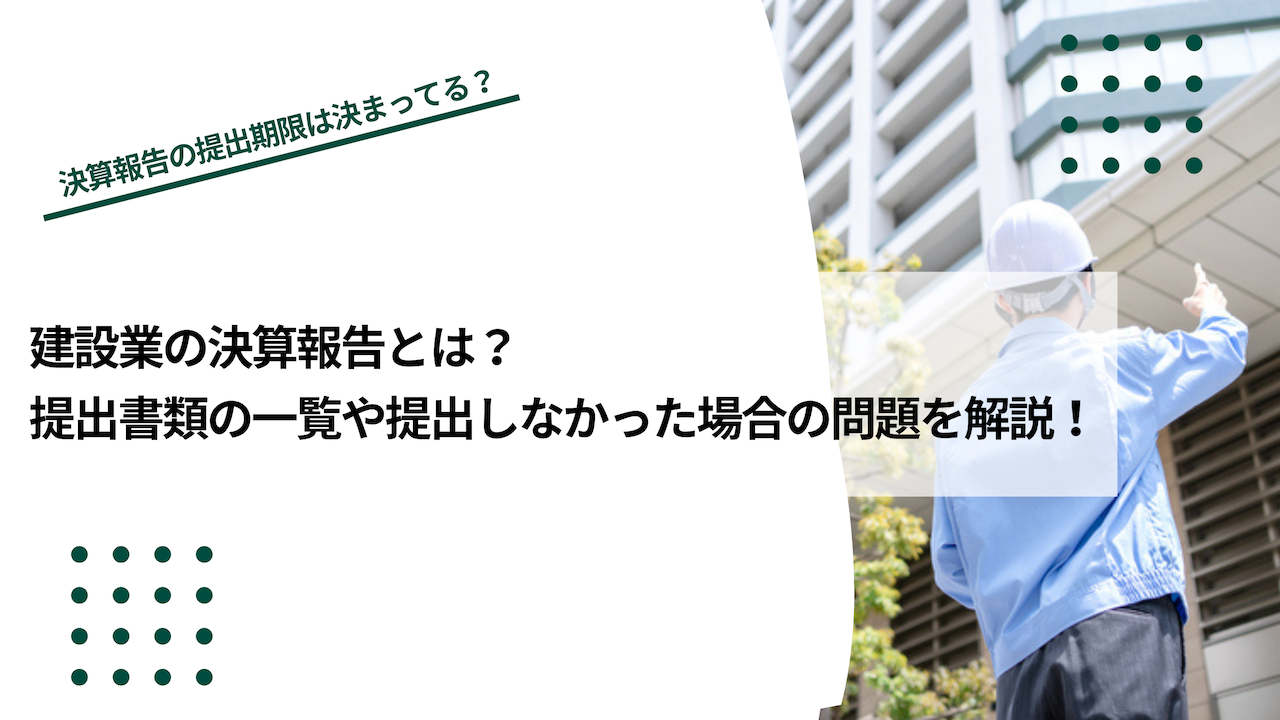
目次
建設業者にとって、決算報告の提出は重要な義務の一つです。
決算報告を提出しなければ、建設業許可の維持や更新、業界での信頼性確保などに悪影響が出るため、内容をきちんと把握して期限内に対応できるようにしましょう。
そこでこの記事では、
- 建設業の決算報告の概要
- 決算報告の役割
- 提出書類
- 提出方法
- 提出しなかった場合の影響
などを詳しく解説します。
最後まで読み進めることで、建設業の決算報告の重要性と提出書類を把握でき、毎年スムーズに対応できるようになるでしょう。
建設業者が提出する決算報告とは?

建設業者が提出する決算報告とは、事業年度ごとの経営状況(収支状況や工事施工実績など)を国土交通大臣または都道府県知事に報告する書類のことです。
以下のように建設業法に基づいて提出が義務付けられており、許可を受けたすべての建設業者が対象となります。
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
決算報告では、財務諸表や工事実績、技術者の状況など、建設業の経営に関する重要な情報を提出します。
単なる義務ではなく、建設業者自身にとっても自社の経営状況を客観的に分析する機会となるのです。
建設業の決算報告の役割

建設業の決算報告には、以下のような重要な役割があります。
- 建設業許可を更新する際の要件になる
- 建設業の適正な経営状況の把握に役立つ
それぞれ詳しく解説します。
建設業許可を更新する際の要件になる
決算報告は、建設業許可の更新時に必要不可欠な要件と言えます。
建設業許可は、5年ごとに更新が必要であり、更新時に決算報告書の提出が求められます。
提出を求められる理由は、建設業者が継続的に適正な経営を行っていることを証明するためです。
決算報告を怠ると、許可の更新ができなくなる可能性があり、毎年の決算報告を確実に行うことが、事業継続の基盤となります。
建設業の適正な経営状況の把握に役立つ
決算報告は、行政機関が建設業者の経営状況を把握するための重要なツールです。
提出された財務諸表や工事実績などの情報を基に、各建設業者の財務健全性や業務遂行能力が評価されます。
これにより、行政機関は建設業界全体の動向を把握し、必要に応じて適切な指導や支援を行えるのです。
また、建設業者自身にとっても、決算報告の作成過程は自社の経営状況を詳細に分析する機会となりますし、経営課題の早期発見や改善策の立案に役立てることが可能です。
決算報告で提出する書類一覧

東京都都市整備局が公表する資料をもとに、決算報告で提出が必要な書類を一覧にしました。
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 附属明細表
- 事業報告書
- 納税証明書
- 使用人数(変更時のみ)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(変更時のみ)
- 定款(変更時のみ)
なお、財務諸表については、税務署へ申告した決算書をそのまま提出するのではなく、建設業用に作成する必要があります。
これは、建設業特有の会計処理や開示項目があるためです。
より詳しい内容は、東京都都市整備局の「II 建設業許可の申請」を確認するか、所在地を管轄する役所に確認してみましょう。
建設業の決算報告の提出方法

建設業の決算報告は、事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。
提出先は、許可を受けた行政庁(都道府県知事または国土交通大臣)です。
提出方法は、直接持参するか郵送で行えます。
近年では、電子申請システムを導入している自治体も多く、各行政庁の指示に従って適切な方法を確認し提出しましょう。
建設業の決算報告を提出しなかった場合

建設業の決算報告を提出しなかった場合、以下のような影響が生じる可能性があります。
- 業種の追加ができなくなる
- 般特新規申請ができない
- 建設業許可の更新申請ができない
- 入札参加資格を得られない
- 取引先への信用悪化につながる可能性がある
それぞれ詳しく解説します。
業種の追加ができなくなる
決算報告を怠ると、新たな業種を追加する申請ができなくなります。
建設業は多岐にわたる業種があり、事業拡大のためには業種追加が必要不可欠です。
例えば、内装工事の許可を得て業務を行う会社が、新たに建築工事に取り組むために「建築一式」の業種追加を行おうとした場合、決算報告の提出を怠っていると、業種追加を行うことはできません。
未提出となっている決算報告を先に提出して認められてからでなければ、業種追加ができないため、すぐに新たな事業を始められないのです。
般特新規申請ができない
一般建設業から特定建設業への変更(般特新規申請)も、決算報告の提出が前提条件となります。
元請業者として請け負う工事の規模が大きくなると、一般建設業許可から特定建設業許可への変更を検討する方も少なくありません。
特定建設業へ移行することは、大規模工事の受注や下請け業者の活用など、事業を拡大する上で欠かせないポイントです。
「特定許可」では、財産的要件として以下のような情報を用いて、直前決算期の決算報告の書類で確認されます。
- 欠損比率
- 流動比率
- 資本金額
- 自己資本
つまり、決算変更届で未提出の状態であると、特定建設業の申請ができないのです。
建設業許可の更新申請ができない
最も深刻な影響は、建設業許可の更新ができなくなることです。
建設業許可は5年ごとの更新が必要ですが、その際に過去5年分の決算報告が提出されていることが条件となります。
当然、決算変更届を1期分でも提出できていないと更新申請ができません。
また、決算報告の提出日は、毎年期限が決まっており、1日でも過ぎると受け付けてもらえない可能性があります。
必要書類を集めるのに時間がかかると、提出期限に間に合わない可能性もあるので注意しましょう。
建設業許可を維持できないと、建設業を営めなくなってしまいます。
入札参加資格を得られない
多くの公共工事では、入札参加資格の審査において決算報告の内容が考慮されます。
決算報告を提出していない場合、入札参加資格を得られず、公共工事の受注機会を失う可能性があります。
取引先への信用悪化につながる可能性がある
決算報告の未提出は、法令遵守の姿勢に欠けるとみなされ、取引先からの信用を失う可能性があります。
特に、大手ゼネコンや公共機関との取引では、コンプライアンスが重視されるため、決算報告の未提出は取引関係に悪影響を及ぼすと考えておきましょう。
これらの影響を考慮すると、決算報告の提出は単なる義務ではなく、建設業を継続的に営むための重要な経営行為であると言えます。
適切なタイミングで正確な決算報告を行うことが、事業の安定と成長につながります。
建設業の決算報告でよくある質問
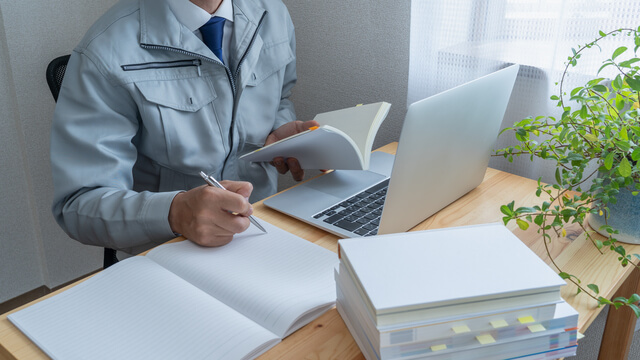
建設業の決算報告でよくある質問として、以下の3つが挙げられます。
- 決算報告に提出期限はありますか?
- 税理士が作成した決算書をそのまま使用してもよいのですか?
- 申請書類はどこにありますか?
各質問の回答をまとめたので、確認してみてください。
決算報告に提出期限はありますか?
決算報告には提出期限があり、事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。
例えば、3月決算の場合、7月末日が提出期限となります。
期限を過ぎると、前章で説明したような不利益が生じる可能性があるため、必ず期限内に提出するように前もって準備して対応しましょう。
税理士が作成した決算書をそのまま使用してもよいのですか?
「決算報告で使用する財務諸表は、税理士が作成したものでもいいのでは?」と考える人も多いですが、税理士が作成したものをそのまま使用することはできません。
建設業の決算報告には、建設業特有の会計処理や開示項目があるため、税務申告用の決算書とは異なる形式で作成する必要があります。
建設業に精通した税理士や行政書士に相談し、適切な形式で作成することをお勧めします。
申請書類はどこにありますか?
申請書類は、各都道府県の建設業許可担当部署のウェブサイトからダウンロードできるケースが多く見受けられます。
また、直接窓口に問い合わせて入手することも可能です。
電子申請システムを導入している自治体もあるため、最新の情報を確認することが重要です。
まとめ

建設業の決算報告は、法令遵守と経営の健全性を示す重要な手続きであり、建設業法でも毎年の提出が義務付けられています。
適切に提出することで、建設業許可の維持や更新、新規事業の展開、公共工事の受注機会の確保など、多くのメリットがあります。
一方、提出を怠ると、業務拡大の機会損失や許可の取り消しなど、深刻な影響が生じる可能性があるのです。
そのため、決算報告を単なる義務ではなく、事業継続と成長のための重要な経営行為として捉えることが大切だと言えます。
正確な書類を期限内に作成・提出し、行政機関との良好な関係を維持することで、建設業者としての信頼性を高め、持続可能な事業運営につなげられるでしょう。
