建設業における電子契約の扱いとは?押さえるべき3つの要件や導入するメリットを解説
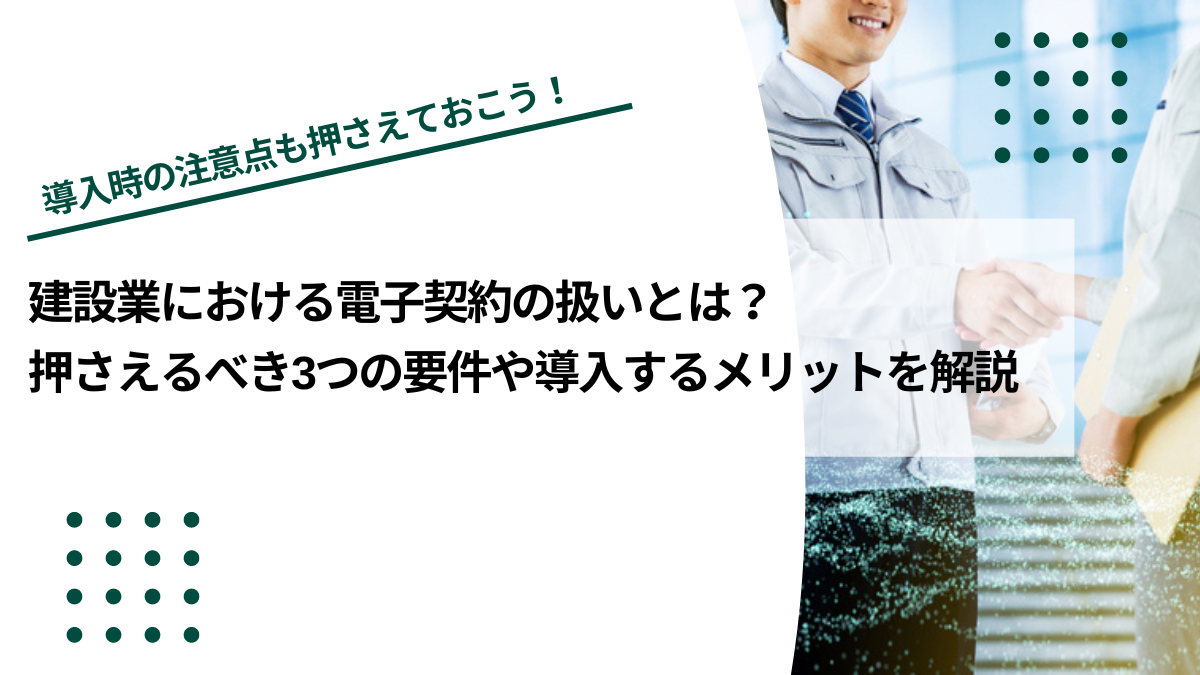
目次
建設業では、紙による契約だけではなく、電子契約も導入可能です。
電子契約とは、電子署名を施した電子ファイルをインターネット上で公開して、企業が保有するサーバーやクラウドストレージなどに保管しておく契約方式です。
インターネットやクラウドなどを使うことから敬遠する人もいますが、業務の効率化やコストの削減につながるため、企業にとって大きなメリットをもたらします。
そこで本記事では、
- ・建設業において電子契約の可否
- ・建設業における電子契約の歴史
- ・建設業の電子契約に欠かせない3つの要件
- ・建設業で電子契約を行う3つのメリット
などを詳しく解説します。
建設業において電子契約は可能なのか?

建設業界における電子契約の利用は認められています。
2001年の建設業法改正により、従来の書面交付だけではなく、電子契約が法的に認可されました。
具体的には、以下のような書面で電子契約を利用可能です。
- ・建設工事請負契約書
- ・賃貸借契約書
- ・売買契約書
- ・発注書 など
これらの契約書面を電子化することで、業務効率の向上やコストの削減が期待できます。
ただし、導入には一定の要件を満たす必要がありますが、メリットも多いため導入する企業も増えています。
建設業における電子契約の歴史

建設業における電子契約の歴史は、2001年にまで遡ります。
建設業法の改正が行われた2001年とグレーゾーン解消制度への回答の2018年の2つについて詳しく解説します。
2001年:建設業法の改正
2001年の建設業法改正により、建設業において契約書面の電子契約化が可能になりました。
元々、建設業法第19条の規定は、以下のように契約の当事者間で必ず書面の取り交わしが必要だと記載されていました。
"請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。引用:建設業法第十九条(建設工事の請負契約の内容)"
しかし、2001年4月に法改正が行われ、以下の建設業法第十九条3項が追加されたのです。
"建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。 引用:建設業法第十九条(建設工事の請負契約の内容)"
上記の内容から、「相手の承諾」と「技術的要件」を満たすことで、電子契約が認められるようになりました。
2018年:グレーゾーン解消制度への回答
2018年、建設業における電子契約の位置づけがさらに明確になりました。
国土交通省は、「グレーゾーン解消制度」を通じて、電子契約の適法性に関する見解を示したのです。
2001年の建設業法の改正後も、「具体的にどのような情報通信技術を指すのか」「技術的基準はどのように定めるのか」などが問題視されていました。
このような問題を解決するために決められたのが、「グレーゾーン解消制度」です。
経済産業省と国土交通省は、「グレーゾーン解消制度」においてクラウド電子契約サービスが適法と正式に認め、建設業における電子契約普及の流れを促進させました。
建設業の電子契約に欠かせない3つの要件

建設業で電子契約を導入する際には、法的効力を確保するために、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- ・見読性
- ・原本性
- ・本人性
これらの要件は、従来の紙の契約書と同等の信頼性と証拠能力を電子契約に持たせるために不可欠です。
それぞれ詳しく解説します。
見読性
見読性とは、契約内容を書面やディスプレイによって、容易に確認できる状態を指します。
電子契約において、関係者が必要に応じて契約書の内容を閲覧し、理解できる環境を整えなければなりません。
具体的には、一般的なパソコンやタブレット端末で契約書を表示したり、長期保存を考慮し、ソフトウェアやハードウェアの変更にも対応したりすることです。
さらに、契約書の検索や抽出が容易にできる仕組みも重要です。
これらの条件を満たすことで、紙の契約書と同等の利便性と透明性が確保されます。
原本性
原本性とは、電子契約書が改ざんされていないことを証明する要件のことです。
電子データは、容易に複製や変更が可能なため、契約内容の信頼性を担保する仕組みが不可欠です。
この要件を満たす方法として、国土交通省の技術的基準に関わるガイドラインにおける「公開鍵暗号方式」による電子署名が挙げられます。
公開鍵暗号技術とは、情報を復号するために、公開鍵と秘密鍵の2つの鍵を用いた暗号技術のことです。
公開鍵暗号技術を活用していると、万が一、第三者に公開鍵を見られたとしても秘密鍵を知られることはないため安全性を担保できます。
本人性
本人性は、契約当事者が本人であることを確認できる仕組みです。
電子契約において、なりすましや不正な契約締結を防ぐために重要な要件になります。
本人性を満たすには、電子署名法に基づく電子署名の利用が有効で、電子証明書を用いた認証や、生体認証技術の活用も検討されています。
建設業で電子契約を活用するメリット

建設業界における電子契約の導入は、従来の紙ベースの契約手続きと比較して、大幅なコスト削減や業務効率の向上が期待できます。
具体的なメリットは、以下の3つです。
- ・収入印紙代や郵送費の削減
- ・業務プロセスの効率化
- ・コンプライアンスの強化
各メリットを詳しく解説します。
収入印紙代や郵送費の削減
電子契約の導入により、収入印紙代や郵送費などの直接的なコスト削減が実現します。
従来の紙の契約書では、契約金額に応じて収入印紙を貼付する必要がありました。
しかし、電子契約では印紙税法上の「文書」に該当しないため、印紙税が課税されません。
大規模な建設プロジェクトになるほど、収入印紙代の削減は効果的ですし、契約書の郵送や宅配便の利用が不要となるため、送料の大幅削減も期待できます。
さらに、紙の保管スペースが不要となるため、オフィスの有効活用にもつながります。
業務効率化
契約書の作成から締結までのプロセスを電子化することで、手続きにかかる時間を短縮でき、建設業務の効率化が期待できます。
例えば、契約書の印刷や押印、郵送などの物理的な作業が不要となり、即時の契約締結も実現します。
また、複数の関係者間での確認や承認プロセスもオンラインで完結するため、スピーディーな意思決定が可能です。
さらに、契約書の検索や管理も容易になり、過去の契約内容の確認や分析にかかる時間も削減できます。
コンプライアンスの強化
電子契約を導入することで、コンプライアンスの強化にもつながります。
契約プロセスを電子化することで、各段階での操作ログが自動的に記録されるだけではなく、契約書ごとでアカウントの閲覧権限を設定できます。
そのため、契約書に関する者だけが契約内容を確認でき、契約書の書き換えや改ざん、流出などの不正リスクを防ぐことが可能です。
なお、契約書はクラウド上で一元管理できるため、プロジェクトごとの契約に関して、「誰が」「何を」「どこまで」進めているのかも容易に把握できます。
自分が扱うプロジェクトの契約だけではなく、マネージャー層においては、チームメンバーの業務進捗管理がしやすくなります。
このような仕組みにより、企業のリスク管理体制の強化と業務の透明性の向上につながるのです。
建設業で電子契約を導入する際に気をつけるべきこと

建設業における電子契約の導入は、多くのメリットをもたらす一方で、慎重な準備と対応が求められます。特に注意すべき点として、以下の2つが挙げられます。
- ・社内ワークフローの調整
- ・取引先への丁寧な説明
それぞれ詳しく解説するので、参考にしてみてください。
社内ワークフローの調整
電子契約の導入に伴い、既存の社内ワークフローの見直しと調整が必須になるでしょう。
従来の紙ベースの契約プロセスから電子化への移行にあたって、業務フローの大幅な変更は避けられません。
まず、契約書の作成から承認、締結までの各段階における責任者と権限を明確にする必要があります。
また、電子署名の運用ルールや、契約データの保管方法についても新たな規定が求められるでしょう。
さらに、契約後に行う社内の関連部署への連携や、セキュリティポリシーの見直しも重要です。
契約の前後も含めて必要な改善ポイントを洗い出し、電子契約に適した新しいワークフローを構築します。
ワークフローを一新したあとは、従業員への研修やマニュアルの整備を行うことも大切です。
取引先への説明
電子契約の導入を成功させるには、取引先への丁寧な説明と協力要請が欠かせません。
建設業界では従来の紙ベースの契約に慣れた企業も多く、電子契約を導入していない企業も多くいます。
そのため、電子契約で進める旨の同意を得た上で、電子契約のメリットや操作方法を分かりやすく伝える必要があります。
取引に対して安心感を持ってもらうには、セキュリティ面での安全性や法的有効性について詳しく説明することが重要です。
また、取引先の規模やITリテラシーに応じて、段階的な導入や紙の契約書と電子契約書の並行利用も検討してみましょう。
複数回取引をしたことのある顧客であれば、信頼度も高いため、快く電子契約に対応してくれる可能性もあります。
さらに、電子契約システムの利用方法に関するサポート体制を整えることで、取引先の不安を軽減可能です。
まとめ:電子契約を導入して社内の業務効率化を図ろう

建設業における電子契約は、契約方法の一つとして法的に認められています。
建設工事請負契約書や発注書などの契約書面を電子化できると、業務効率の向上やコストの削減、コンプライアンスの強化が期待できます。
ただし、導入には以下の3つの要件を満たす必要があり、従来の紙の契約書と同等の信頼性と証拠能力が必要不可欠です。
- ・見読性
- ・原本性
- ・本人性
従来の紙の契約書に慣れている人は、セキュリティ面での不安やクラウドの扱いに難しさを感じるかもしれませんが、企業のメリットも大きいのでぜひ導入を検討してみてください。
また、業務効率化を促進する方法の一つとして、弊社クラフトバンクが提供する「クラフトバンクオフィス」もおすすめです。
同システムでは、見積・請求や案件管理、日報、勤怠管理といった各業務を一元管理でき、膨大な時間を使っている事務作業の労力を軽減できます。
また、売上管理の自動集計や出面の自動生成なども可能で、自社のコンディションを容易に可視化できます。
建設業の業務効率化ツールに興味がある人は、ぜひ以下のリンクから導入を検討してみてください。
