建設業会計の勘定科目一覧|一般会計との違いや仕訳例を紹介
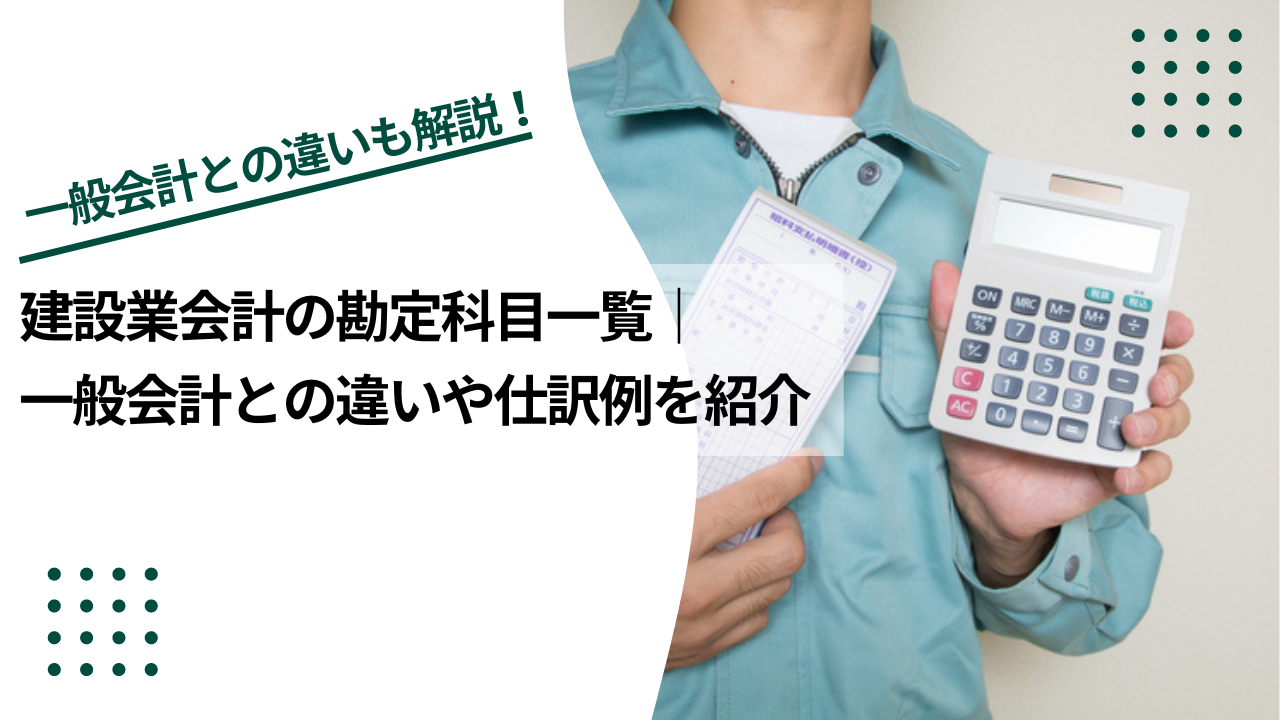
目次
- 建設業における勘定科目とは
- そもそも建設業会計とは
- 建設業会計と一般会計との違い
- 一般会計と異なる勘定科目を使用する
- 工事進行基準と工事完成基準の2つの基準がある
- 原価計算の方法が複雑
- 建設業会計が一般会計と異なる理由
- 【仕訳例あり】建設業会計で使用する勘定科目一覧
- 完成工事高
- 完成工事原価
- 完成工事総利益
- 未成工事支出金
- 完成工事未収入金
- 未成工事受入金
- 工事未払金
- 建設業会計と一般会計の勘定科目対応表
- 建設業会計の勘定科目に関して、よくある質問
- 建設業会計に建設業経理士の資格は必須?
- 会計処理は工事ごとに行う?
- 工事契約に関係しない項目も建設業会計で処理する?
- 建設業会計で用いられる引当金は?
- まとめ:建設業の基礎知識として勘定科目を理解しておきましょう
勘定科目とは、取引で発生する金額の流れを分類し、記録する項目です。
建設業会計では、一般会計と異なる勘定科目を使用するため注意が必要です。
この記事では、建設業会計の勘定科目や一般会計との違い、仕訳例を解説します。
建設業会計と一般会計の勘定科目対応表も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
建設業における勘定科目とは

勘定科目とは、取引で発生するお金の流れを分類・記録するための項目です。
お金の性質を表す見出しのような役割を果たし、「なぜ入金が発生したのか」「何に・いくら使ったのか」などが記載されます。
建設業では、貸借対照表や損益計算書といった決算書類を作成する際に、勘定科目が使用されます。
入金・出金の予定を明確にして、経営状況を正しく把握するためには、勘定科目を活用した仕訳が不可欠です。
そもそも建設業会計とは

そもそも建設業会計とは、建設業を営む会社に適用される特殊な会計方式を指します。
基本的には一般会計をベースとしますが、他業種とは異なる勘定科目や基準を使用する点が特徴です。
建設業者は一定規模の工事を請け負う際に、建設業許可の取得が求められます。
その建設業許可を取得するには、建設業会計にもとづいて財務諸表を作る必要があるのです。
ただし、以下の条件を満たす場合であれば、建設業許可は不要となります。
建築一式工事 | ①1件の請負代金が税込1,500万円に満たない ②請負代金にかかわらず、木造住宅で延床面積が150平方メートルに満たない 上記①または②に該当する |
|---|---|
建築一式工事以外の工事 | 1件の請負代金が税込500万円に満たない |
参考URL:建設業の許可とは
建設業許可に関しては、以下の記事も要チェックです。
>>>建設業許可申請のポイント解説① そもそも誰に相談すればいい?【行政書士監修記事】
建設業会計と一般会計との違い

建設業会計と一般会計との違いは、主に3つあります。
- 一般会計と異なる勘定科目を使用する
- 工事進行基準と工事完成基準の2つの基準がある
- 原価計算の方法が複雑
建設業の会計処理について理解を深めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
一般会計と異なる勘定科目を使用する
建設業会計では、一般会計と異なる勘定科目を使用して仕訳をします。
たとえば、一般では「売上高」を使う際に、建設業では「完成工事高」という勘定科目を使用します。
他業種にて会計業務の経験がある方でも、建設業独自の勘定科目に慣れるまでには時間がかかるでしょう。
工事進行基準と工事完成基準の2つの基準がある
建設業会計では
- 工事進行基準
- 工事完成基準
上記2つの基準があります。
現場の進捗に合わせて、売上を計上する方式が「工事進行基準」です。
工事の途中でも費用や経費、売上を分散して計上できるため、長期間に渡る大規模な工事に向いています。
一方、「工事完成基準」は工事完了後に費用の計上をまとめて行う方式です。
工事進行基準よりもシンプルな方式であり、小規模な工事で採用される傾向にあります。
参考として、以下の3つの要件をすべて満たす工事は「長期大規模工事」と認識されます。
- 工事着手日から引渡期日までが1年以上である
- 請負対価が10億円以上である
- 請負対価の2分の1以上が、引渡日から1年内に支払われる場合
長期大規模工事では、工事進行基準が強制的に適用されるので注意しましょう。
参考URL:別紙 JV工事の場合の長期大規模工事の判定について
原価計算の方法が複雑
一般会計における原価は、材料費・労務費・経費の3つをまとめたものです。
対して、建設業の原価では上記3つに「外注費」を加えます。
一般会計よりも分類項目が多いことで、建設業会計では原価計算の方法が複雑になりがちです。
複雑な原価計算をスムーズに進めるコツは、建設業会計に対応したシステムを導入することです。
弊社クラフトバンクが提供するクラフトバンクオフィスならば、建設業特有の勘定科目や原価計算に対応しています。
また、工事原価について知りたい方は、ぜひコチラの記事もご覧ください。
>>>工事原価とは?工事原価を構成する4つの要素や粗利益を増やす方法も解説
建設業会計が一般会計と異なる理由

建設業会計が一般会計と異なるのは、長期間の工事に対応するためです。
建設業の場合、工事の着工から完成・引き渡しまでに、1年以上かかるケースもあるでしょう。
建設業が一般会計の方式で仕訳をすると、工事が完了したタイミングで多額の金額を計上しなければいけません。
「着工した年に利益を計上できない」などの不都合も起こりえます。
そこで、建設業では独自の会計方式を採用しているのです。
【仕訳例あり】建設業会計で使用する勘定科目一覧

建設業会計で使用する勘定科目を紹介します。
- 完成工事高
- 完成工事原価
- 完成工事総利益
- 未成工事支出金
- 完成工事未収入金
- 未成工事受入金
- 工事未払金
仕訳例を見ながら、1つずつ説明していきます。
完成工事高
完成工事高は、一般会計の「売上高」に該当する勘定科目です。
【300,000円で契約していた工事が完了し、引き渡しが済んだ場合】
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
完成工事未収入金 | 300,000円 | 完成工事高 | 300,000円 |
建設工事が完了し、引き渡し時に発生する収益は「完成工事高」として計上します。
完成工事原価
完成工事原価は、一般会計でいう「売上原価」に当たります。
建設工事で必要となる原価は、完成工事原価として計上しましょう。
【工事進行基準を適用された契約にて、引き渡し完了に伴い、未成工事支出金200,000円を完成工事原価に振り替える場合】
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
完成工事原価 | 200,000円 | 未成工事支出金 | 200,000円 |
完成工事原価は「材料費・労務費・外注費・経費」の4区分で構成されます。
完成工事総利益
完成工事総利益は、一般会計の「売上総損益(粗利)」に相当する勘定科目です。
請け負った工事における粗利益を計上します。
【完成工事総利益の計算方法】
完成工事総利益=完成工事高-完成工事原価
完成工事高から完成工事原価を差し引くと、完成工事総利益を算出できます。
未成工事支出金
未成工事支出金は、一般会計の「仕掛品」に当たる項目です。
【工事進行基準を適用した工事にて、材料費30,000円と労務費6,000円、経費4,000円を計上した場合】
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
未成工事支出金 | 40,000円 | 材料費 | 30,000円 |
労務費 | 6,000円 | ||
経費 | 4,000円 | ||
工事に取りかかっているものの未完成な段階であれば、費用を一度「未成工事支出金」として計上しなければいけません。
工期が1年以上となる大規模工事にて、用いられることの多い勘定科目です。
完成工事未収入金
完成工事未収入金は、一般会計の「売掛金」と同様の役割を果たします。
【20,000円が当座預金に入金されて、完成工事未収入金として計上する場合】
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
現金預金 | 20,000円 | 完成工事未収入金 | 20,000円 |
完成工事未収入金を使用するのは
- 工事完成の翌期に請負代金が振り込まれる
- 完成工事未収入金として計上した債権を回収した
上記のような場合です。
完了した工事の請負代金のうち、未回収の代金は完成工事未収入金として計上します。
未成工事受入金
未成工事受入金は、一般会計でいうと「前受金」に該当する項目です。
工事の完成前に入金された代金は、未成工事受入金として扱います。
【30,000円が当座預金に入金されて、未成工事受入金として計上する場合】
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
現金預金 | 30,000円 | 未成工事受入金 | 30,000円 |
建設工事では、工期が長期間となるケースが珍しくありません。
そのため、完成前に対価を分割して受け取る場合があります。
工事未払金
工事未払金は、一般会計の「買掛金」に該当します。
工事が完了した段階で、支払いが済んでいない費用を分類するための勘定科目です。
【進行途中の工事にて、材料費10,000円と外注費30,000円が発生し、工事未払金として計上した場合】
借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
材料費 | 10,000円 | 工事未払金 | 40,000円 |
外注費 | 30,000円 | ||
材料費や外注費などが、工事未払金として分類される可能性があります。
建設業会計と一般会計の勘定科目対応表

建設業会計と一般会計の勘定科目対応表は、次のとおりです。
一般の勘定科目 | 建設業会計の勘定科目 |
|---|---|
売上高 | 完成工事高 |
売上原価 | 完成工事原価 |
売上総損益(粗利益) | 完成工事総利益 |
仕掛品 | 未成工事支出金 |
売掛金 | 完成工事未収入金 |
前受金 | 未成工事受入金 |
買掛金 | 工事未払金 |
間違った勘定科目を使用しないように、注意しながら決算書類の作成を進めましょう。
建設業会計の勘定科目に関して、よくある質問

建設業会計の勘定科目に関して、よくある質問を4つ紹介します。
- 建設業会計に建設業経理士の資格は必須?
- 会計処理は工事ごとに行う?
- 工事契約に関係しない項目も建設業会計で処理する?
- 建設業会計で用いられる引当金は?
1つずつ見ていきます。
建設業会計に建設業経理士の資格は必須?
建設業経理士とは、建設業関連の会計知識・会計処理能力を証明する資格です。
建設業会計に、建設業経理士の資格は必須ではありません。
しかし、必須ではないものの、取得しているほうが会計処理をより正確に行えます。
参考として、建設業経理士の合格レベルを見てみましょう。
級別 | 合格レベル |
|---|---|
1級 | ・上級の建設業簿記、建設業原価計算および会計学を修得している。 ・会社法その他会計に関する法規を理解している。 ・建設業の財務諸表の作成および、それにもとづく経営分析が行える。 |
2級 | ・実践的な建設業簿記、基礎的な建設業原価計算を修得している。 ・決算等に関する実務を行える。 |
3級 | ・基礎的な建設業簿記の原理および記帳並びに初歩的な原価計算を理解している。 ・決算等に関する初歩的な実務を行える。 |
4級 | ・初歩的な建設業簿記を理解している。 |
加えて、建設業経理士を有する企業は、公共工事の受注を有利に進められます。
参考URL:建設業経理検定試験とは
参考URL:経営事項審査における建設業経理士の評価
会計処理は工事ごとに行う?
建設業の会計処理は工事ごとに行います。
複数の工事を並行するときは、計上漏れがないように注意しましょう。
現場ごとに処理することで、利益や費用を正確に把握でき、人材や材料を適切に管理できます。
工事契約に関係しない項目も建設業会計で処理する?
工事契約に関係しない項目は、一般的な勘定科目を使って処理します。
具体的に
- 通信費
- 広告宣伝費
- 消耗品費
などは、一般的な勘定科目で処理をします。
建設業会計で用いられる引当金は?
建設業会計で用いられる引当金を、3つピックアップしました。
引当金 | 内容 |
|---|---|
工事損失引当金 | 工事で発生するコストが、収益の総額を上回る可能性が高い場合に使用する。 |
完成工事補償引当金 | 引渡しが完了した工事において、欠陥があった場合に備えて計上する。 |
修繕引当金 | 建物・機械などの固定資産の機能を、維持するために用意するメンテナンス費用。 |
将来に発生する可能性が高い支出に備えて、あらかじめ見積計上する金額を「引当金」と呼びます。
つまり、発生の可能性が低ければ、引当金として計上できません。
まとめ:建設業の基礎知識として勘定科目を理解しておきましょう

今回の記事は、建設業会計の勘定科目や一般会計との違い、仕訳例を紹介しました。
建設業では長期間の工事に対応するため、他業種とは異なる次のような勘定科目を用います。
- 完成工事高
- 完成工事原価
- 完成工事総利益
- 未成工事支出金
- 完成工事未収入金
- 未成工事受入金
- 工事未払金
建設業独自の勘定科目に対応するならば、弊社クラフトバンクが提供するクラフトバンクオフィスがおすすめです。
建設業に特化したシステムなので、建設業会計を正確かつスムーズに行えます。
ご興味のある方は、サービス資料をダウンロードしてみてください。
